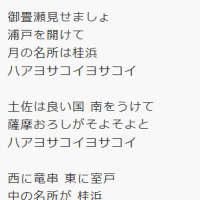2022年5月18日(水) 流浪の民に寄せて
〇先日夜、合唱曲「流浪の民」の夢をみた。自分で歌ったことはないが、よく知っている曲だ。家内は、高校生の頃から知っていて、合唱サークルでも歌っているという。
ネットで調べたら、この曲は、著名なドイツの音楽家 ロベルト・シューマンが作曲している。シューマンと言えば、子供の情景の「トロイメライ」でよく知っている。
流浪の民の歌詞は、ドイツの詩人、エマニュエル・ガイベルの詩という。原語はドイツ語だが、明治40年に、石倉小三郎氏が、翻訳を発表しているようで、下記に出ている。
(流浪の民 歌詞の意味・和訳 合唱曲 世界の民謡・童謡.html )
歌詞の始まりは、以下だ。七・五調を基本にしている、言葉のリズムが素晴らしい。
♪ ぶなの森の葉隠(はがく)れに 宴(うたげ)寿(ほが)ひ賑はしや
松明(たいまつ)明(あか)く照らしつつ 木(こ)の葉敷きて うついする
これぞ流浪の人の群れ 眼(まなこ)光り髪清ら
ニイルの水に浸されて きららきらら輝けり ♪ ♪
---以下 省略----
寿という字は良く見るが、手持ちの広辞苑によれば、ことほぐ、という意だ。ほぐ、
ほがう、とも言うようだ。
うついするは、聞き慣れない言葉だが、坐り込む、と言った程の意味だろう。
石倉氏の、文語調の超意訳に驚いたことだが、この歌詞で、現在もよく歌われているうだ。
原語と、石倉氏の訳を対比した、下記サイトも見つかったが、これ以上、詳細には立ち入らないこととしたい。
(「流浪の民(合唱)」の解説(歌詞・和訳) 原語と石倉訳の対比.html )
〇ジプシーと音楽
誰でも聞いたことがある、ツイゴイネルワイゼン(Zigeunerweisen)は、
ドイツ語で、下記サイト
(「ツィゴイネルワイゼン」とはどういう意味?ドイツ語で「Zigeunerweisen」と記述するとの事。)
によれば、
Zigeuner:ジプシー(ロマ)
Weisen:旋律
の意のようで、スペインの音楽家 サラサーテの作曲になるものだ。
改めて、手持ちのCDで聞いてみると、以下の三部構成になっている。下記のネットの解説記事を参照。(ツィゴイネルワイゼン - Wikipedia.html)
第一部 物悲しいながらも堂々とした旋律
第二部 印象的なリズムで、解説書によれば、ハガリー民謡に題材をとっているようだ
第三部 急速なテンポの技巧的な奏法。リストのハンガリー狂詩曲の旋律に使われているという。
上述の、石倉小三郎訳の、流浪の民の歌詞の最後は以下である。
♪ 慣れし故郷を放(はな)たれて 夢に楽土(らくど)を求めたり
東(ひんがし)空(そら)の白(しら)みては 夜の姿かき失(う)せぬ
ねぐら離れ鳥鳴けば いづこ行くか流浪の民 ♪
居場所を定めず、さすらう人たちの様子が浮かび上がってくる。
〇世界のロマの人たち
流浪の民は、一般には、「ジプシー」(jipsy)と呼ばれるが、差別用語とも言われて、最近は、あまり使われず、「ロマ」(roma)と呼ばれるようだ。
下図は、ロマの旗で、地理的な国ではなく、民族を現していると言う。
(ロマの人々 - ウィキペディア.html 参照)

流浪の民だけに、ロマの人たちがどの位いるのか、正確なデータはないようだ。
ロマの人たちの世界の人口は可なり不確定で、下図にある一覧は、世界の人口だが、世界全体では、1000万~2000万人とも言われている。
(ロマの人々 - ウィキペディア.html を参照)

下図は、ロマの人口を、欧州の国別に示したもので、東南欧の、バルカン半島地域に多いようだ。(ロマ人(ロマ族)|ジプシーと軽蔑される人々の生活・歴史・特徴 _ 世界雑学ノート.html 参照)