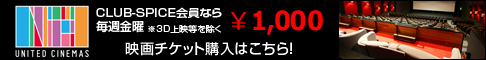前回の「維新・改革の正体」の書評では、プラザ合意1985年(昭和60年)からバブル崩壊の頃のことなどを説明して終わってしまった。
ここでバブル崩壊の前後を説明したのは、「維新・改革の正体」の中で述べられている「日本機関車論」、「日本財布論」に関わると思えるからである。
著書では、「『日本財布論』の出現」でその典型例として「金融の自由化」(1990年中盤から進められた金融ビッグバン)と書かれている。
確かにそれは間違いないとしてもその根はプラザ合意からだと思う。このプラザ合意によって日本は米国より常に金利が低い水準に押さえられることになった。それは日本の資金が米国に流れる様にということで、日本は米国債を毎年いくら買うのかということを押しつけられた。
それで毎月、当時の大蔵省は生保などの機関投資家に米国債をいくら買ったかを報告させるという「バブル期の総量規制」のような越権行為をしていた。
米国がそこで日本の機関投資家にもうけさせるということをするはずがない。
結局円高を誘導して、最終的に機関投資家に大損をさせるという荒技を行った。その結果どうなったかと言えば、その後に多くの生保が統合されるかカタカナの名前になったことからもよくわかる。
本来危なくなれば大蔵省が助けてくれるはずだったのが、破綻となれば「自己責任」とされたのである。こうしてバブル崩壊以降日本国民の金は米国に流出してしまった。
ちなみに小生の保険金も生保が破綻して、外国の保険会社になり戻ってきたのは4割を切ったはずであった。
この利回りが急速に悪くなる状況で出現した「金儲け」の本が今の民主党の海江田万里代表の著書。
ここで、「民主・海江田(万里)代表『安愚楽牧場』投資推奨で窮地」とJ-CASTニュースで報じられている。(2013/01/19)
このネタは随分前のものだが、J-CASTニュースでは推奨記事の部分が書かれているのが興味深い--ここで保存用に引用転記してみる。
「元金確実で、しかも年13.3%と考えれば、他の金融商品はまっ青!」(「今どうすれば一番損をしないか‐このままではいると5年で、はだか同然」1987年6月、青春出版社)
「和牛の死亡率は0.4%と低く、また万一そのような事態があっても代わりの牛が提供されるので、契約どおりの利益は保証されます」(「BIGMAN」1988年3月号)
「知る人ぞ知るといった高利回りの利殖商品」「むろん元本は保証付き」(「海江田万里の金のなる本」1989年8月、双葉社)
「この利益は申し込み時に確定していて,リスクはゼロ」(「女性セブン」1992年7月2日号)
「利益は申し込みをした時点で確定していますから,リスクもありません。」(「月刊DoLive」1992年9月号)
海江田万里の著書は、元々は野末陳平氏との共書という形式が多くその後単独で発行された。
その本の内で持っていたのが多分この「とにかく速く自分のお金が二倍になる本」(カッパ・ホームス) [新書] (1988/06)など。
この頃の著書というのはかなり胡散臭く、著書で金貨購入を勧めて「金の価格は変わりません」とあったのだが、当時半年で金価格が大幅に下落して信じて金貨や金を買った人は大損をしたはずである。
多少はなしは逸れた。
昭和48年の石油ショックで日本の高度成長が終わり、日本中が一瞬に大不況になって昭和50年から深刻な就職難になった。
その不況を日本の技術力で一番先に脱出した後が「日本機関車論」のころである。
そしてバブルが到来して米国の主要なビルが買収されたなどと騒がれた後のバブル崩壊後が「日本財布論」である。
実を言えばこのバブル経済も米国にとっては日本は良い財布になった。
売れなかったビルを高値で買い取らせ後で、バブル崩壊の後遺症で日本から二束三文で買い戻すという美味しい話だった。
それで日本はどうして日本を豊かにしようという政策がとられないのか、なぜ「日本財布論」という結果になるのかという政策過程を思い出してみよう。
それは、まずバブル経済のハードランディングはどうして行われたのかである。
バブル経済の時は、国民で景気が良くて喜んでいなかった人はいなかったはずなのだが、面白くなかった人、苦々しく思っていた人たちがいた。
それがまず景気がよくなっても給料が上がるわけでない中央省庁の官僚と大学の学者。
そして、日本が景気が良くなっては共産主義革命が遠のくと思っていた共産主義者や左翼人士。
不動産の価格が上がるのはけしからぬ、不動産の価値(価格)は限りなくゼロにして場合によっては国有化しろという主張の「財団法人 建設経済研究所常務理事(当時)・長谷川徳之輔氏」などの共産主義かぶれの人物。
そして、本来なら景気が良くなって広告宣伝費で大もうけのはずの新聞社と儲かっている実感のないその記者たち。
最後に米国。
ここで起こったのが、バブル経済潰しのキャンペーンである。又、米国から日本政府に「バブル経済のハードランディング」を強要したという話もある。
まず新聞が、一斉にバブル経済が過熱するのは良くないと書き、連日のキャンペーン。
だから「国鉄分割民営化」の後に余った土地を売る話も凍結になった。
そうして新聞報道が過熱したところで、NHKは2時間以上の「バブル経済潰し」の特別番組を放映。
このNHKの報道を契機としてこのバブル潰しが「民意」だとして突然、政府は「バブル経済のハードランディング」の不動産総量規制を発動したわけである。
当時の新聞報道では、大蔵省銀行局長の土田正顕に大蔵大臣であった橋本龍太郎氏が「バブル経済を潰すのにはどうしたらよいか」と尋ねたという。
そこで土田大蔵省銀行局長は、「かなり違法に近い禁じ手だと思った」が、橋本大蔵大臣に「こんな手もあります」と提案したという。(常識ではそれはまずいという下策)
そのとき橋本大蔵大臣はなんと言ったか・・・・
「そんな方法があったのならなぜ早く言わなかった」と即刻採用したので驚いたという。
橋本補佐の面目躍如というべきものであった。
ここで小泉改革の頃まで、どういう手法で政治が大きな決断をするのかということを考えてみると、まず新聞報道による連日のキャンペーンで世論を作り出すと言うことであった。読売新聞の渡辺恒雄社主が1,000万読者によって世論を作り出すと豪語したのはあながち間違いではなかった。
しかし、新聞各社が一斉にキャンペーンをやったとしても政府はなかなか動かず最後にNHKが特別番組を作ってだめ押しをするというパターンである。
そのパターンは確か住専(住宅金融専門会社)処理問題(1996平成8年)でも同じだった。そしてそのときの総理大臣がまたしても橋本龍太郎氏。
本当に日本の節目節目に橋本龍太郎氏が出て来る。
しかし、この「新聞各社が一斉にキャンペーン」・・・「NHKが特番で世論を確定」という手法は今や通用しない。
なぜなら今では情報は新聞社だけが持っているのではなく、いつでも調べられるからである。
又、NHKの反日報道というものが問題視され、今やNHKの中立性も公共性も疑問視され続けている。
新聞に情報を独占させないというのは、ツイッター(Twitter)などで直接情報発信する安倍首相が新聞社の「ぶら下がり取材」に応じないということからでも判る。
考えて見れば、この藤井聡・著「維新・改革の正体」という本の宣伝は新聞には載らないし、市内の紀伊國屋書店でも見つからない。それだけでなく推薦となっている中野剛志氏の本も三橋貴明氏の本もほとんど見かけない。
ネット情報でやはり世界は変わって行くだけでなく、フィルターのかかったTV、新聞報道では、新たな「安愚楽牧場」投資などの正邪はわからないというものである。
尚、著書「維新・改革の正体」の「第六章 維新で踊るダメ人間」のなかで「むしろ一人一人は『善意』の人々」という記載がある。
これを「学校秀才の人たち」と考えるとよくわかる。要するに他人から教わった事柄でしか判断できない人たちで、学校で習った「刷り込み」でしか考えられない人たちである。