
■ 2014.01.18 我が家のFITハイブリッド、私の最終(?)評価
■ 2013.09.08 新型FIT、想定していた以上にいい車だ
1月18日の記事で「私の最終(?)評価」と書いたのだが、2月10日の3回目のリコールによって、その最終評価も幾分変わった。
まず、2月10日リコール届出に対して、Honda 技研の修正プログラム変更準備等が20日ほどかかったようで、我が家のFITがHonda Carsでチェックを受けたのが3月4日となった。
技研も想定外のトラブル対応に手間取ったようで、3月4日までは技研の指示通りSモードで走行となる。
で、そのCars店で、栄えある、ミッション取り換えの第1号車となった。
まあ、いろいろと症状も出ていたので、それは予想していた。
(該当車は、このCars店で80数台中12台だったようだ)
車が戻ってきたのは4月8日で、35日間の想定外の長期入院となってしまった。
もちろん、35日間修理をしていた訳ではなく、単に取り換え用のミッション待ちというだけのことだ。
このミッション、特許のミッションのようで、技研としても待ちの状態だったようである。
その間は、Cars店から1500ccガソリン車が代車として貸与され、日常生活には何ら支障は無かった。
また、私としては、FIT3購入の、当初考えていた車種が1500ccガソリン車であったので、十分過ぎる期間でチェックをすることができ、ありがたかったのだが、やはり、人の車を長く乗るのは気を使う。
因みに、1500ccガソリン車の、私の評価の概要も書いておきたい。
まず、当然かも知れないが、新開発LEBは、やはりL15Bにくらべ勝っているようだ。
(ただ、これは、エンジンだけの問題ではなくDCTの成果かも知れない(?))
この1500ccガソリン車に初めて乗った瞬間から、L15Bエンジンが、かなり非力に感じた。
つまり、(DCT+)LEBエンジンは、かなり、吹き上がりの良い、力強いエンジンに仕上がっているように感じる。
つぎに、意外だったのが、この2車の足回りの違いだ。
こんなに異なるとは思っていなかった(タイヤはまったく同じものだ)。
ハイブリッド車が、ピシッと、しっかりコーナーを決めてくれるのにくらべ、ガソリン車の方は、けっこう軟弱な足腰である印象を受ける。
Carsの技術の方に確認すると、部材、設定は同じのようで、どうやらバッテリーの重さによるバランスのようだ。
(当然、設計はハイブリッド車に合わせている筈なわけで)
さらに、1500ccガソリン車と比較することで、ハイブリッドの出足の良さを改めて実感した。
やはり、出足に関しては、かなりモーターが活躍しているのだろう。
(ただ、後述するが、この強烈な出足感は、今回のリコール3改善措置後、少し薄らいでしまったのだが)
とにかく、当初、購入車種に決めていたガソリン車からハイブリッド車へ変更した理由は、価格と経済性だったのだが、今回1500ccガソリン車を貸与してもらったお陰で、走りの性能からも、ガソリン車でなく、ハイブリッド車の選択で正解だったと確信した。
というか、エンジン関連性能と足回りが、こんなに違うとは、やはり、乗ってみないと判らないものだ。
で、退院後の、我が家のFITハイブリッドに対しての評価を以下に記載する。
まず思うのが、今の車は、プログラムの書き換えで、こんなにも違うものか、ということだ。
別人のように変わり、なんだか、新入社員が扱かれて大人しく社会人になったかのように感じる(笑)。
つまり、全体的に、ソフトでマイルドな大人しい静かな車となった。
私としては、あの尖がった感じが好きだったので、少し非力な印象となり残念ではあるが。
どうやら、デュアルクラッチのシフトアップを早めに設定し直したようで、スタートでのグインと引っぱる力強さは消えてしまったが、全体としてはこれでいいのかも知れない。
で、まず、Sモードだが、かなり静かになった。
通常走行時の音は、1500ガソリン車とほとんど変わらないくらいで、私が思うタイミングでシフトアップしてくれているようで、異常に引っぱり続けることが無くり、気持ちよく、違和感無く運転することができるようになった。
以前40km/h~60km/hあたりから、アクセルを急に深く踏み込み込んで、急加速した場合の、遅れてエンジンが吹きがる違和感があったのだが、マイルドになった分、(とくに、エコモードで)その違和感が和らいだ。
(ただし、Sモードに関しては、以前と変わらない、かなり尖った段差となって今も現れる)
クリープ現象が、リコール2改善措置後よりも、さらによくなり、すぐに現われるようになった。
(一般のオートマチック車とほとんど変わらなくなった)
ただ、エンジンが冷えていると、やはり、1秒弱ほど動かないのだが、暖機した後に動かすと、すぐに動く。
ただし、なぜか、不思議なことに、Sモードではエンジンが温まった後も、やはり1秒ほど動かない。
(この、エンジン温度の関係と、Sモードについては、Carsの技術の方に問い合わせをしている)
驚いたのが、モーターだけでの走行で、時速40kmに成功したことだ(笑)。
(なかなか、平坦な道路と後方車との条件が揃うのが難しいのだが)以前は、ゆるい下り坂でも、すぐエンジンが始動していたが、40km/hどころか60km/hまでも、モーターだけで走行することが実現でた。
ただし後方に車両が無い場合で、60km/hの場合は、緩やかな下り坂でのことだが、それでも運転者としては、それなりの加速感を感じての結果である。
そもそも、モーターだけの走行表示で、速度計が60km/hを示しているのを見た時は驚いた(笑)。
これで、せめて、バスの後ろについて行けるくらいの加速ができればいいのだが。
で、意識をして運転すると、モーターだけで走っている時間を、かなり増やすことができ、もしかすると、燃費がかなり良くなる可能性がある。
ただ、バッテリーの充電量(残量)表示は、見る間に無くなってしまい、そうなると、今度はバッテリーの寿命が心配とはなる。
そして、今回、性格が穏やかになったことで、アクアとの燃費比較の比重が大きくなるのではないだろうか。
で、それと関係するのかどうか判りらないが(たぶん、しているのような(?))、アクセルワークでの、エンジンまでの距離が以前より、より深くなったように感じる(たぶん、間違いないであろう)。
アクセルペダルの上層部数センチは、いくらペダルを上下しても、エンジンとはなんら関係無いようで、これは、以前の関係無かった深さ(上下長さ)より、明らかに大きく変化したように思う。
最後に、これが問題なのだが、シフトダウンのタイミングを、今回、早くし過ぎたように思える(Sモードも同様)。
ちょっとした登り坂でも(というか、考えられない、思わぬところでも)、不必要と感じるシフトダウンをする場合が有り、非常に違和感を感じ、かなり不快に感じるほどエンジンブレーキがかかる場合が有る。
その時の条件(要素)にもよるのだとは思うが、そういうシーンを、この数日間の試し走行で、けっこう経験した。
事実の一例としては、ある上り坂となっているヘアピンカーブで、以前と同じ速度で進入すると、シフトダウンしてしまいエンジンブレーキがかかり、音もうるさく不愉快となる。
進入速度をいくらか変えて試みても同じ結果で、以前は進入直前の速度のままで、少し加速気味に気持ちよくコーナーリングできたのだが、いまでは走り方を変えて、コーナー直前で必要以上にスピードを落とし進入し、加速しながら曲がるようにしなけれがならなくなった(残念)。
(これに関しては、プログラム修正をお願いしたもだ)
以上だが、概して言えば、あの鋭い出足感が無くなったのは誠に残念だが、万人向けのファミリーカーとしては良くなったと言えるのではないだろうか(悪く言えば、より普通な車に近づいたとも言えるが)。
ところでFIT3、リコール続きで販売台数がガタ落ちかと思っていたのだが、2月はたしかにかなり落ち込んだが、意外にも、3月の数字は、辛うじてだが、1位を奪還している。
結局、去年の10月から、2月の激減を除くと、連続1位のようである。
私としても、HONDAに対して(意外ではあったが)とくに不満はなく、とくにCars店の対応には満足している。












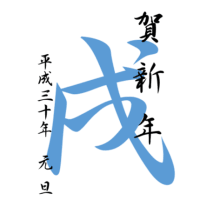







ちょうど先々週でしたか、トヨタが新世代エンジンの発表を行いましたが、新聞発表等もありましたからご記憶に残っていますか? 高効率化がテーマで、燃費性能の引き上げ(省燃費=排出ガス量の低減、すなわち環境性能の向上です)が狙いです。ハイブリッドを手掛ける以上、内燃機関の高効率化は不可欠ですから、まさに正攻法と言えるものです。市場の目は、どうしてもモーター機関回りに行きますが、カギはむしろ内燃機関です。
ECUが車両のドライバビリティを決定する時代です。しかも、エンジン、ミッション、デフ、サスペンション、ブレーキ、ステアリングとメカニカル系全体を協調制御しながら一括一元管理で掌握するというのが、現代の自動車です。そしてその制御モードは自由自在に設定可能です。電子制御スロットルなどは、その最たる例でしょう。
たとえば、ドライバーのペダル踏み込み量に対してスロット開度が多めとなる設定としたらどうなるでしょうか? ドライバーは、アクセルの踏み込み量に対する加速感を経験的に持っていますから、軽く踏み込んだだけでも鋭い加速を示すと「加速がいい」「パワフル!」といった印象を持ちます。とくに、踏み込み初期で鋭く反応すると、無条件で素晴らしいエンジンといった印象を持ちますが、実はこれは錯覚です。アクセルの踏み込み量に対してスロットル開度が大きくとられているだけの話ですから、加速がよく感じられるのは当たり前です。
こうしたセッティングは、優れたエンジンを持つ強力な競合車があるような場合、性能的に劣る側のメーカーがよく使う手ですが、ドライバビリティに不満を持つユーザーに対しても有効な対応策となりますから、案外多用されています。ただし、過渡特性を変えているだけで、絶対性能を引き上げているものではありません。こうした車両は、動力性能を計測すると一発で分かります。発進加速、最高速度といった簡単なチェックですぐに分かります。体感的にはすごく速いと感じた車両が、動力性能を測ってみたら遅かったということはけっこうあります。一般公道での走行で、通常のドライバーが全負荷走行を行うことはまずありませんから。言い方は少々乱暴ですが、過渡特性がよければピーク性能はそれほど重要ではない、と言ってもよいでしょう。しかし、多くのユーザーは、特性ではなくカタログ数値のピーク値だけを気にしているようです。
スロットル開度だけではなく、自動断続機能を持つクラッチの断続タイミング設定などでも同じことが言えます。ポイントは、どう設定すればドライバーに違和感なく受け容れてもらえるか、ということです。これは、反応が速くても遅くても、鋭くても鈍くてもいいんです。要は、操作するドライバーの感性にどれだけ合っているか、合わせられるか、ということでしょう。
ですから、極論すればchoongwheeさんのFITも、choongwheeさんの操作タイミング、リズム、感性に合った個別仕様が可能です。もちろん専用の制御MAPを作らなければいけませんが、モータースポーツのカテゴリーでは、あるレベル以上の競技車両になればこうしたドライバー個別対応というのはもはや常識化しています。市販車の場合は、不特定多数のユーザーが相手となるためベースMAPがひとつあるのみで、なにか問題があった場合に対策型のMAPが用意されるという流れでしょうか。
話題転換 choongwheeさん、最初の頃仰っていた直進安定性の問題は解決しましたか?
なるほど「カギはむしろ内燃機関です」か。
「ECUが車両のドライバビリティを決定する時代」、そして、「制御モードは自由自在に設定可能」は、この度、実感でしょうか。
「ドライバーのペダル踏み込み量に対してスロット開度が多めとなる設定としたらどうなるでしょう」、なるほど。
(ただ、吹き上がり「感」は、そのエンジン特性が現われるとは思いますが - また、慣れも出てくるような)
いずれにしても、騙されないようにしなくては(笑)。
「専用の制御MAP」、各ユーザーのための、各ユーザーが自分で調整できる時代が来るれば、本当の意味でのコンピューター制御(自動制御)な車と言えるでしょう。
(いまのコンピューター制御車は、ドライバーがコンピュータープログラムに使われて運転している)
「直進安定性」は、その後100km/h以上で走っていませんから分りません。
というか、これは、ボディーの空気抵抗的なことだと思いますので、変わらないのでは(?)。
改めて直進安定性についてお伺いしたのは、ひょっとしてサスペンションアライメントが狂っているのでは、と思ったからです。choongwheeさんのFITは、何度か整備工場のお世話になっているようですが、その際、アライメントテスターでチェックを受けたことはありますでしょうか。トー調整だけでも直進安定性は変わります。もし、直進安定性が気になるようでしたら、アライメントチェックを受けて適正値に合わせ直すこと、適正値内で収まっているのでしたら、許容範囲内でトーイン方向に振り込んでみる、という方法があります。サスペンションアライメントに異常がなく、それでも直進安定性が気になるような場合は、タイヤで改善するという方法があります。もちろん現在使用中のOEMタイヤの溝が十分に残ってる状態でしたら、もったいないのでこのアイデアはなしですが、直進安定性を増す方法としては、回転方向に指定のあるワンウェイパターンのタイヤを履かせる手法があります。この場合、トレッドセンターの周方向がグルーブ(溝)ではなく、リブ(山)となっているトレッドパターンのほうが、直進安定性は強めに出ます。ご参考までに。
「サスペンションアライメントが狂っている」、なんと(ドキッ)。
しかし、であれば、80km/hでも、何らかも違和感が生じると思っているのですが(?)。
「アライメントテスターでチェック」はしていないと思います(?)。
また、日常での走行に関しては、とくに気になるような違和感を経験したことはありません。
80km/h~100km/h以上で感じる直進性の悪さは、空力の問題だと思っていましたが、一度Carsの技術の方に確認してみます。
(長さ、幅に対して高さが、少し高い所為だと思っているのですが(?))
ありがとうございます。
また、80km/h近辺ですでに直安の悪さを感じられているということですが、エアロダイナミクス面から見た80km/hという速度域は低中速域にあたり、空力の影響が明らかに出る速度域より下の領域となります。非合法ではありますが、たとえば120km/h走行時に直安が悪く(正確に言えば、80km/h時より症状が顕著に)なっていなければ、まず空力ではないと思います。
現行FIT-HVには乗っていないので断定的なことはまったく言えないのですが、直安の悪さに結びつくメカニズム面での要素は、サスペンションアライメントのほかに、広義に走行系の剛性不足も上げられます。たとえばリアサスペンションのブッシュコンプライアンスなどです。路面入力が常に一定ではなく、小刻みに変化しているような状態ではブッシュの変形が起こり(ボディ側、ホイール側ともに)、それによるトーやキャンバーに変化が起こり、直進性に障害が生じるというものです。タイヤトレッドブロックの剛性不足もこうした症状につながります。これはサマータイヤとスタッドレスタイヤを同条件で較べたケースを考えれば、すぐにお分かりいただけるかと思います。
直進安定性という言葉の定義についても再確認しておく必要があるかと思います。直進走行時、ステアリングを中立状態で保持しているにもかかわらず、クルマが微妙に左右に振られる、というのも直安の悪さ、と表現する場合があります。さらにやっかいな例ですと、クルマが小刻みにフラついているように感じられながらも、結果的にクルマはまっすぐ走っている、という状態です。本来的な直進性の悪さは、絶えずステアリングを修正していないと、クルマがまっすぐ走らない、というケースです。常識的に、現代ではこんなクルマは、事故車でそれも修正が不十分な状態でなければ、まず起こりようもありません。
一方で、たとえばメルセデス・ベンツのようにトレール角を大きくとったサスペンションだと、ステアリング中立付近で「溝」にはまったようなズッシリとした手応えがあり、初期転蛇の際にはその「溝」を乗り越すようなはっきりとした手応えがあります。手放しでもまっすぐ走ると表現される状態ですが、かといって、とくに明確なセンタリング感があるわけでもないのにふらつき感もなく自然に直進性を保つBMWのようなハンドリング例もあります。
なんとなく直進安定性の悪さを感じる、という印象は、案外多くあるものです。ただ、上記のような例もあり、その原因は多岐におよびます。私事で恐縮ですが、趣味のマイカーとしてFRのスポーツカーを1台持っています。応答性をよくするため(というより曖昧さを消すため)に、フロントサスペンション(Wウィッシュボーン)ロワアームの№1ブッシュを純正のラバーから剛体であるピロボールに変えましたが、結果的に、進行方向からの入力をいちばん大きく受けるこの位置のピボットを剛体化したことで、直進安定性まで向上する効果がありました。
choongwheeさんもお書きになっていたよう、次にディーラーに入庫した際、アライメントチェックを受けておく(再調整しておく)のは正解でしょう。そこで問題がなく、なおかつ直安が気になるようでしたら、そこで次の手を考えればよいかと思います。文面から察する限り、今のところそれほど大きな問題ではないと判断しました。
「直進安定性」、そうなんだ。「空力が原因となる直進安定性の悪さというのは考えにくい」のですか。
そして、「FITのボディバランス」って悪くないのですか。
「120km/h走行時に直安が悪く(正確に言えば、80km/h時より症状が顕著に)なっていなければ、まず空力ではないと思います」
私の書き方が悪かったかも知れませんが、80km/h辺りまでは特に違和感が無く、100km/h前後から120km/h辺りで不安定になります。もっとも、あの日は風もあったからではないかと思っているのですが(?)。
(軽いから吹き飛ばされた)
「走行系の剛性不足」、「タイヤトレッドブロックの剛性不足」に関しては、確認しようがありません。
私が言っている、高速での直進性の悪さとは「直進走行時、ステアリングを中立状態で保持しているにもかかわらず、クルマが微妙に左右に振られる」ことです。
「手放しでもまっすぐ走ると表現される状態」は、大昔のブルーバードがそうだったような(確か(?))。
とにかく、次回、無風の時に高速道路を走った際、再度確認してみます。
その上で、サスペンションアライメントチェックを、一度サービスの方にお願いしてみます。
ありがとうございました。
ここからは、あくまで参考意見としてとどめて欲しいのですが、市販車にはクラスメントによる基本構造の違いという設計・生産上の問題がついて回ります。平たく言えば、販売価格に反映される製造コストの問題です。高額車両は、開発コストを投入しても販売価格で回収できますが、普及価格帯のモデルはコストをかけられず、また製造原価と販売価格(正確にはディーラーへの卸価格ですね)のマージンも少なく、かなり合理的(と言えば聞こえはいいですが、端的には省コストですね)に作らなければ利益に結び付きにくくなるわけです。
さて、軽自動車も含め、国内市場の動向に目を向けると、やはり普及価格帯に需要が集まっていることがよく分かります。とくに1000~1500ccクラスは激戦区と言ってよいでしょう。当然ながら、設計・生産にかけるコスト削減策は相当なものです。言葉は悪いのですが、安く作るための定番テクノロジー(メカニズム)というものがあります。
その代表例がリアサスペンションのビームアクスル方式です。リアアクスルを文字通りビーム(梁)で支える方式で、部品点数が減らせ、製作コストを低く抑えることのできる方式です。90年代前半、バブル経済崩壊後、コストを抑えた車両生産が迫られる状況で、FF車のリアサスペンションとして考え出された方式です。もちろん、公道を走る量産車用のサスペンションとして開発された形式ですから、通常使用においてなんら問題はありません。ただ、構造的に見ていくと、アクスルの支持剛性やキャンバー剛性が独立懸架式と較べると確保しにくいという特徴があります。
一方、ストラット式やセミトレーリング式、さらにはマルチリンク式(基本的にはダブルウィッシュボーン式と見なして結構です)といった独立懸架方式は、複数のアームや支持点によりリアタイヤを保持することになりますしバネ下重量も軽く抑えられるので、キャンバー、トーといった対地アライメント変化に対して優れた特性を発揮します。
ビームアクスル式のリアサスペンションを持つ車両すべてではありませんが、後輪(後車軸)に大きな入力があった場合、アクスル部分が微振動を起こし、直進安定性を妨げる場合があります。装着するタイヤや路面状況によっても変わってくることなので、断定的なことは言い難いのですが、高速直進時なんとなく落ち着かない、微妙に揺れる(振られる)といった症状を示すことがあります。コンプライアンスを持つラバーブッシュ類を廃し、ピロボールのような剛体支持としてしまう方法もありますが、リアアクスル自体の剛性が十分でないと、こうした対策(レーシングカーの手法ではありますが)を施しても、なおかつ直視安定性に不満が残る、といったケースがあります。
車両を開発する際、どこまでの性能をギャランティするか、というテーマがあると思いますが、実際にはネガティブ(とくに安全性でマイナスとなる要素)な面は慎重に対処するようですが、ここをこうすればこれぐらいよくなる、といったポジティブな要素に対しては、思いのほか消極的である場合が多いようです。もちろんその理由は、費用を要するというこの1点に尽きるのですが。
消費税の引き上げで、ガソリン代がさらに厳しくなりました。燃費に優れたクルマはオーナー孝行かと思います。こうしてお借りしているスペースだと、なかなか十分な説明が出来ず、歯がゆい思いをしています。もし、不明な点や補足の説明が必要な場合には、以下のアドレスまでご連絡ください。可能な限り対応させていただきます。yyenjoy@excite.co.jp
たしかに、このコメント欄でご説明いただくだけでは「歯がゆい思いを」されているだろうことはよく分ります。
一応、Wikipediaなどを参考にしながら、私の少ない知識をもとに、何をおっしゃりたいかは、おぼろげながらですが解りました(完全に理解することは無理ですが)。
また、Carsの技術の方(工場長)にはメールでサスペンションアライメントチェックの打診はしております。
今度お会いした時、短時間に簡単にできるのであれば実施してもらうつもりです。
ただ、理屈は解ったとしても、現実に、Carsとしても技術的に限界が有るのでは(そういう車という可能性も)。
まあ、とりあえずは、100km/h以上で走行することは年に何回もありませので。
かねてより病気療養中だった妻が、昨晩、他界いたしました。お顔も、お名前も存じ上げぬchoongwheeさんやmisawa_karaさんから、いたわりや励ましの言葉をいただき、ありがたさが身に染みいる思いでした。こちらはchoongwheeさんのブログとなりますが、片隅をお借りして、改めてお礼を申し上げたいと思います。その折は、大変ありがとうございました。
正直、物凄い喪失感と挫折感を味わっていますが、これまでの妻の愛情と支援に応えるためにも、自分らしさのある生活を取り戻そうと気持ちを固めつつあります。これから葬儀の準備のため、出かけなければなりませんが、掛け値なしの意見交換をさせていただいているこちらのブログが気持ちの拠り所のようにも思え、これまでのお礼を兼ねて私事をお伝えすることにいたしました。
実は、妻が亡くなる直前に、最新アップのIU記事に目を通し、リリース曲を聴かせていただいた次第です。
そうなんですか。
快方に向かっているものと思って、正直、奥さまのことは忘れてしまっていました(申し訳ありません)。
「お礼」なんてとんでもないです。
「喪失感と挫折感」、我が妻は元気ですが、愛する人を失くすことはよく解っているつもりです。
あまり、慌てず、無理せず、気持ちに正直に、いま、泣けるだけ泣いて、ゆっくりと日常を取り戻してください。
おそらく、本当の喪失感は、暫く時間が経過した後に、激しく襲ってくるはずです(そして後悔の念も)。
その為にも、しっかりと、いま、お泣きになることが最善かと思います(経験的にも)。
そして、奥さまをよくご存じの方と、たくさんお話になることがいいかと。
とにかく、いまのお気持ちに素直に、一日一日をお過ごしください。
こればかりは、時間しかありませんので。
ご冥福をお祈りいたします。