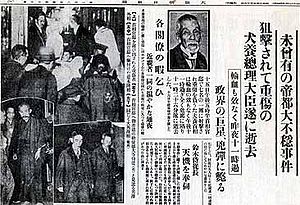「小雪さん、上がらしていただくは」
と、あれ以来、もう何回となく小雪のこの部屋に来られているものですから、お須香さんは、場所柄か何か後ろめたい気分に駆られるような真木を引っ張るようにしてずんずんと上がってまいられました。
小雪の部屋の小さな違い棚には、赤漆で縁取りしている丸い洒落た色紙入れに、お喜智さまの、『なごりなく消えしは春の夢なれや卯の花垣につもる白雪』というお歌が入れてありました。その下に置いてある備前の花瓶には卯の花がこぎれいに活けてあり、そのうす黄色がかった白い5、6枚の花びらとと額斑の赤色とが美しく調和され、部屋全体に、新緑の清々しい初夏が鮮明に描き出されているような感じられました。
「まあ、大奥様のお歌が」と、目ざとく眼にされたお真木さん
「あああれ、この前、小雪ちゃんに頼まれていた大奥さまのお歌を貰ってきてあげたの。あれだわね」
お須香さんは『小雪ちゃん』と「ちゃん」付けで小雪の事を呼ぶようになっていました。
「座らせて頂くは」と、お山の緑がよく見えると所を選んで、ご自分で隅に置いてあった座布団を片手でひょいと掴み上げてお座りになるお須香さん。「あなたもここへどうぞ」と、お真木さんにも自分の横を指差します。
そこへ、「ようこそ・・・」と、お粂さんがしおらしくもお茶など運んできてくれるのでした。二言三言お須香さんと、あいさつの言葉を交わしてお粂さんは、とっとと、下に下りて行かれました。
軟らかい初夏の香が、細谷の流れの音に乗って、部屋一杯に入り込んできます。
「今日は、前々からぜひお願いしますと頼んでいた、京での新之介をお聞きに来ました。あなたが見たままのことをこの真木とともに聞かせてもわうわ。よろしく頼むは小雪ちゃん」
ぴょこんと頭をお下げになします。横のお真木までもが『よろしくお願いします』と深々とお辞儀をされました。この二人の姿があまりにも違うのに小雪のほうも返って面食らうばかりです。
「前々から、お真木さまのお前で、お話しなくては、と覚悟はしていたのどすが、あまりにもむうごうて残酷なお話しどすさかい、できたらそんな機会がなければと、思うておりました。・・・・・・・・・でも、とうとうその日が・・・」
それから小雪は、ゆっくりとゆっくりと、始めて新之介と会ったときからの話を始めるのでした。「とっても新之介様とのことを話すなんてできそうもないは」と、心の内では思っていたのですが。いざお話を始めてみると、自分でも驚くように、あれもあったこれもあったとその当時のことが、次々と頭の中にはっきりと浮かび出て、それが自分の言葉になって二人に話をしているのではない、自分に言い聞かせているかのように小雪は話します。
と、あれ以来、もう何回となく小雪のこの部屋に来られているものですから、お須香さんは、場所柄か何か後ろめたい気分に駆られるような真木を引っ張るようにしてずんずんと上がってまいられました。
小雪の部屋の小さな違い棚には、赤漆で縁取りしている丸い洒落た色紙入れに、お喜智さまの、『なごりなく消えしは春の夢なれや卯の花垣につもる白雪』というお歌が入れてありました。その下に置いてある備前の花瓶には卯の花がこぎれいに活けてあり、そのうす黄色がかった白い5、6枚の花びらとと額斑の赤色とが美しく調和され、部屋全体に、新緑の清々しい初夏が鮮明に描き出されているような感じられました。
「まあ、大奥様のお歌が」と、目ざとく眼にされたお真木さん
「あああれ、この前、小雪ちゃんに頼まれていた大奥さまのお歌を貰ってきてあげたの。あれだわね」
お須香さんは『小雪ちゃん』と「ちゃん」付けで小雪の事を呼ぶようになっていました。
「座らせて頂くは」と、お山の緑がよく見えると所を選んで、ご自分で隅に置いてあった座布団を片手でひょいと掴み上げてお座りになるお須香さん。「あなたもここへどうぞ」と、お真木さんにも自分の横を指差します。
そこへ、「ようこそ・・・」と、お粂さんがしおらしくもお茶など運んできてくれるのでした。二言三言お須香さんと、あいさつの言葉を交わしてお粂さんは、とっとと、下に下りて行かれました。
軟らかい初夏の香が、細谷の流れの音に乗って、部屋一杯に入り込んできます。
「今日は、前々からぜひお願いしますと頼んでいた、京での新之介をお聞きに来ました。あなたが見たままのことをこの真木とともに聞かせてもわうわ。よろしく頼むは小雪ちゃん」
ぴょこんと頭をお下げになします。横のお真木までもが『よろしくお願いします』と深々とお辞儀をされました。この二人の姿があまりにも違うのに小雪のほうも返って面食らうばかりです。
「前々から、お真木さまのお前で、お話しなくては、と覚悟はしていたのどすが、あまりにもむうごうて残酷なお話しどすさかい、できたらそんな機会がなければと、思うておりました。・・・・・・・・・でも、とうとうその日が・・・」
それから小雪は、ゆっくりとゆっくりと、始めて新之介と会ったときからの話を始めるのでした。「とっても新之介様とのことを話すなんてできそうもないは」と、心の内では思っていたのですが。いざお話を始めてみると、自分でも驚くように、あれもあったこれもあったとその当時のことが、次々と頭の中にはっきりと浮かび出て、それが自分の言葉になって二人に話をしているのではない、自分に言い聞かせているかのように小雪は話します。