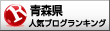名久井農業高校から臨む名久井岳。
5月も中旬となり新緑が増えてきました。
名久井岳は麗岳ともいわれる標高615mの山。
それほど高い山ではありませんが
周辺の市町村からよく見えることから
この地域のシンボル的な存在となっています。
チームはこの名久井岳の麓にある法光寺で
ハスの復活プロジェクトに取り組んでいます。
では法光寺のあるところはいったい標高何mでしょうか?
地形図で調べてみると約標高220mと意外と高くありません。
それではこの名農の標高はどれぐらいでしょうか。
スマートフォンのアプリは50m前後を示しています。
自分の住んでいるところの高さなどあまり気にすることはありませんが
615mという名久井岳を眺めるたびについつい考えてしまいます。
さてチームは本日、サクラソウの保全について情報交換するため
宮城県の国営公園を目指します。
そこではどんな美しい景色を見ることができるのは今から楽しみです。
5月も中旬となり新緑が増えてきました。
名久井岳は麗岳ともいわれる標高615mの山。
それほど高い山ではありませんが
周辺の市町村からよく見えることから
この地域のシンボル的な存在となっています。
チームはこの名久井岳の麓にある法光寺で
ハスの復活プロジェクトに取り組んでいます。
では法光寺のあるところはいったい標高何mでしょうか?
地形図で調べてみると約標高220mと意外と高くありません。
それではこの名農の標高はどれぐらいでしょうか。
スマートフォンのアプリは50m前後を示しています。
自分の住んでいるところの高さなどあまり気にすることはありませんが
615mという名久井岳を眺めるたびについつい考えてしまいます。
さてチームは本日、サクラソウの保全について情報交換するため
宮城県の国営公園を目指します。
そこではどんな美しい景色を見ることができるのは今から楽しみです。