本来は国立劇場で開催されていましたが、今は建て替えの為に会場を借りて歌舞伎鑑賞教室を開催しています。言葉は悪いですが、どさ廻りです。今回はサンパール荒川大ホールが会場です。既設の花道などはありませんが、それなりに努力されていました。国立劇場のスタッフも大変です。
個人的には史実ですから、その時代の庶民の心情など色濃く残った脚色になったのは致し方ありません。また、その行間に流れる江戸庶民の心と今の日本人の心が相通じる所が有ると思っています。
観劇してみて、長い時代を経て安全で言葉に出さずにしても心が通じる阿吽の呼吸と言うか、心の底流に流れる考えを色濃く感じた今回の演目「歌舞伎の演目「土屋主税(つちやちから)」でした。
忠臣蔵の外伝として知られる作品です。特に、初代中村鴈治郎が得意とした「玩辞楼十二曲」の一つとして知られています。この作品は、吉良邸討ち入り前夜を舞台に、赤穂浪士の一人である大高源吾と、吉良邸の隣に住む旗本・土屋主税との交流を描いています。(Search Labs | AI による概要からの部分引用です。)
国立劇場六月歌舞伎鑑賞教室 土屋主税 一幕二場(サンパール荒川)を鑑賞してきました。
今回はサンパール荒川での鑑賞にお邪魔してきました。
歌舞伎鑑賞教室として初心者でも分かりやすい事も相まって、一番理解できた演目でした。
サンパール荒川には都電に乗って向かいました。

東池袋四丁目停留所です。

荒川区役所前で下車して徒歩2分でした。

サンパール荒川のホール内に金魚のオブジェがありました。

前方は中学生や高校生などの鑑賞教室の団体席です。


大まかなあらすじをそのまま拝借しました。

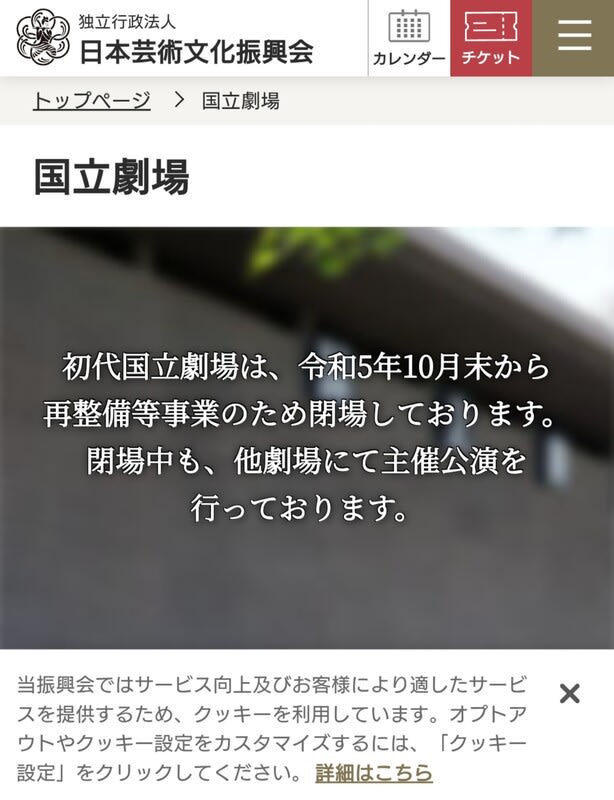
99


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます