 |
ジャーナリズムは歴史の第一稿である。 (「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」記念講座2018) |
| 瀬川 至朗 | |
| 成文堂 |
 |
言論の自由―拡大するメディアと縮むジャーナリズム (叢書・現代社会のフロンティア 20) |
| 山田 健太 | |
| ミネルヴァ書房 |
 |
権力と新聞の大問題 (集英社新書) |
| 望月 衣塑子,マーティン・ファクラー | |
| 集英社 |
●新聞と新聞紙がなくなる日 どこか寂しいのだが
以下のコラムは、磯山友幸氏の新聞が滅びる日を案じるコラムだ。
筆者も新聞購読は、だいぶ昔にやめている。
たしかに、紙の新聞社が現実に存在するから、当該新聞社の電子版でニュース情報を入手しているのは事実だ。
ただ、同氏が心配するところの、ジャーナリズムが消えてしまうと云う心配は、おおむね杞憂なのではないかと考えている。
一定の“メディアリテラシー”があれば、ニュースの事実関係を確認するだけの情報があれば、そこから先は不要である。
仮に、耳慣れない言葉などが含まれている場合には、ググることで、おおむね情報は入手できる。
そのような日常を考えると、紙の新聞が必要かどうか聞かれたら、不要と答える。まぁ「共同通信」の配信だけは必要だと答える。
日本から“ジャーナリズム”がなくなると言われても、そもそも、現在の新聞からジャーナリズム精神を感じることは稀であり、左右或いは中道のネット媒体の情報を吟味すれば済む話で、特に痛痒はない。
この点は、テレビにおけるニュース報道にしても、どの局のニュースを見ても、どこかで誰かが編集したものを順番を変えて報道している?と疑いたくなるほど似ているわけで、大きな違いを見ることは稀である。
無論、本コラムの新聞記事も9割方は同じで、残り1割において、その新聞社の立ち位置、政権寄りか、政権批判新聞かを競っている。
競っていると言っても、多くは ”解説” 部分で違っているわけで、記者クラブと云う ”村社会” のルール内での違いを出している程度である。
将来的に、紙の新聞は、現在の発行部数の半分くらいまで落ち込むのではないかと想像することが出来る。
到底、これからの若い世代が新聞を積極的に定期購読するインセンティブは見当たらない。
無論、情報を入手しようと云う意欲までがなくなることもないので、ネットから各新聞社等にアクセスする選択になるものと思われる。
ただ、経営上、マイナス要素の多い“紙の新聞”も、読売、朝日、日経などは発行し続ける可能性が高い。
おそらく、現在の発行部数の半分程度が、この世の紙新聞の“閾値”なのではないだろうか。
場合によると、定期購読と云う宅配システムがなくなる可能性もあるだろう。販売店の経営維持費と購読料が同レベルであるなら、新聞販売が、コンビニとキオスク等での販売ルートのみになる可能性はある。
筆者などは、節目のニュースがあった時は、読売、朝日、東京の3紙をコンビニで購入する。
限りなく怪しい「改元」“令和”の時には、夕刊朝刊を6紙も買ったので、かなり財布が軽くなった。
新聞社は生き残るが、その社会との接点が、限りなく通信社と同種のものとなり、生き残りや独自性を出すための“調査報道”に特色を出していければ、それなりに固定の読者を囲い込むことは可能かもしれない。
最近では、新聞紙を濡らして丸め、掃き掃除に使う家庭もないだろうし、引越しも、業者が色々便利なものを持ってくるので、新聞紙の用途も減ってきた。
ガンバレ新聞と言いたいところだが、あまり勝ち目を見つけることは出来ない。
≪ 新聞部数が一年で222万部減…ついに「本当の危機」がやってきた
新聞は不要、でいいんですか?
■ピークの4分の3
ネット上には新聞やテレビなど「マスコミ」をあげつらって「マスゴミ」呼ばわりする人がいる。論調が自分の主張と違うとか、趣味に合わないとか、理由はいろいろあるのだろうが、「ゴミ」と言うのはいかがなものか。ゴミ=いらないもの、である。新聞は無くてもよいと言い切れるのか。
新聞を作っている新聞記者は、全員が全員とは言わないが、言論の自由や報道の自由が民主主義社会を支えているという自負をもっている。権力の暴走をチェックしたり、不正を暴くことは、ジャーナリズムの重要な仕事だ。日本では歴史的に、新聞がジャーナリズムを支えてきた。
だが今、その「新聞」が消滅の危機に直面している。毎年1月に日本新聞協会が発表している日本の新聞発行部数によると、2018年(10月時点、以下同じ)は3990万1576部と、2017年に比べて222万6613部も減少した。14年連続の減少で、遂に4000万部の大台を割り込んだ。
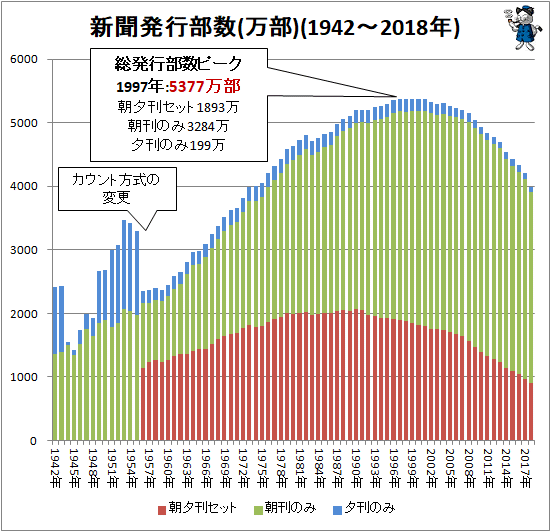
(他サイトのグラフ)
新聞発行部数のピークは1997年の5376万5000部だったから、21年で1386万部減ったことになる。率にして25.8%減、4分の3になったわけだ。
深刻なのは減少にまったく歯止めがかかる様子が見えないこと。222万部減という部数にしても、5.3%減という率にしても、過去20年で最大なのだ。
新聞社が販売店に実際の販売部数より多くを押し込み、見かけ上の部数を水増ししてきた「押し紙」を止めたり、減らしたりする新聞社が増えたなど、様々な要因があると見られるが、実際、紙の新聞を読む人がめっきり減っている。
このままでいくと、本当に紙の新聞が消滅することになりかねない状況なのだ。
若い人たちはほとんど新聞を読まない。新聞社に企業の広報ネタを売り込むPR会社の女性社員でも、新聞を1紙もとっていない人がほとんどだ、という笑い話があるほどだ。
学校が教材として古新聞を持ってくるように言うと、わざわざコンビニで買って来るという笑えない話もある。一家に必ず一紙は購読紙があるというのが当たり前だった時代は、もうとっくに過去のものだ。
「いやいや、電子版を読んでいます」という声もある。あるいはスマホに新聞社のニュースメールが送られてきます、という人もいるだろう。新聞をとらなくても、ニュースや情報を得るのにはまったく困らない、というのが率直なところに違いない。
■このままいくと…
紙の発行部数の激減は、新聞社の経営を足下からゆすぶっている。減少した1386万部に月額朝刊のみとして3000円をかけると415億円、年間にすればざっと5000億円である。新聞の市場規模が20年で5000億円縮んだことになる。
新聞社の収益構造を大まかに言うと、購読料収入と広告収入がほぼ半々。購読料収入は販売店網の維持で消えてしまうので、広告が屋台骨を支えてきたと言える。
発行部数の激減は、広告単価の下落に結びつく。全国紙朝刊の全面広告は定価では軽く1000万円を超す。その広告単価を維持するためにも部数を確保しなければならないから、「押し紙」のような慣行が生まれてきたのだ。
「新聞広告は効かない」という声を聞くようになって久しい。
ターゲットを絞り込みやすく、広告効果が計測可能なネットを使った広告やマーケティングが花盛りになり、大海に投網を打つような新聞広告を志向する会社が減っているのだ。
新聞社も企画広告など様々な工夫を凝らすが、広告を取るのに四苦八苦している新聞社も少なくない。
筆者が新聞記者になった1980年代後半は、増ページの連続だった。ページを増やすのは情報を伝えたいからではなく、広告スペースを確保するため。
第三種郵便の規定で広告は記事のページ数を超えることができなかったので、広告を増やすために記事ページを増やすという逆転現象が起きていた。増ページのために膨大な設備投資をして新鋭輪転機を導入した工場などをどんどん建てた。
確かに、今はデジタルの時代である。電子版が伸びている新聞社も存在する。だが、残念ながら、電子新聞は紙ほどもうからない。広告単価がまったく違うのだ。
海外の新聞社は2000年頃からネットに力を入れ、スクープ記事を紙の新聞よりネットに先に載せる「ネット・ファースト」なども15年以上前に踏み切っている。日本の新聞社でも「ネット・ファースト」を始めたところがあるが、ネットで先に見ることができるのなら、わざわざ紙を取らなくてよい、という話になってしまう。
紙の読者がネットだけに移れば、仮に購読料金は変らなくても、広告収入が減ってしまうことになるわけだ。
欧米では新聞社の経営は早々に行き詰まり、大手メディア企業の傘下に入ったり、海外の新聞社に売り飛ばされたところもある。このままでいくと、日本の新聞社も経営的に成り立たなくなるのは火をみるより明らかだ。
■「紙」の死はジャーナリズムの死
当然、コスト削減に努めるという話になるわけだが、新聞社のコストの大半は人件費だ。記者の給料も筆者が新聞社にいた頃に比べるとだいぶ安くなったようだが、ネットメディアになれば、まだまだ賃金は下がっていくだろう。
フリーのジャーナリストに払われる月刊誌など伝統的な紙メディアの原稿料と比べると、電子メディアの原稿料は良くて半分。三分の一あるいは四分の一というのが相場だろうか。新聞記者の給与も往時の半分以下になるということが想像できるわけだ。
問題は、それで優秀なジャーナリストが育つかどうか。骨のあるジャーナリストは新聞社で育つか、出版社系の週刊誌や月刊誌で育った人がほとんどだ。
逆に言えば、ジャーナリズムの実践教育は新聞と週刊誌が担っていたのだが、新聞同様、週刊誌も凋落が著しい中で、ジャーナリスト志望の若手は生活に困窮し始めている。
そう、新聞が滅びると、真っ当なジャーナリズムも日本から姿を消してしまうかもしれないのだ。紙の新聞を読みましょう、と言うつもりはない。
だが、タダで情報を得るということは、事実上、タダ働きしている人がいるということだ。そんなビジネスモデルではジャーナリズムは維持できない。
誰が、どうやって日本のジャーナリズムを守るのか。そろそろ国民が真剣に考えるタイミングではないだろうか。
*磯山友幸 硬派経済ジャーナリスト。
1962年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。日本経済新聞社で証券部記者、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、日経ビジネス副編集長・編集委員などを務め2011年3月末で退社・独立。著書に『国際会計基準戦争・完結編』『ブランド王国スイスの秘密』など。早稲田大学政治経済学術院非常勤講師、上智大学非常勤講師、静岡県“ふじのくに”づくりリーディングアドバイザーなども務める。
≫(現代ビジネス:社会:ジャーナリズム)
 |
新聞社崩壊 (新潮新書) |
| 畑尾一知 | |
| 新潮社 |
 |
新聞の運命 ―事実と実情の記事 |
| 山本 七平 | |
| さくら舎 |
 |
変容するNHK――「忖度」とモラル崩壊の現場 |
| 川本 裕司 | |
| 花伝社 |












 https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif
https://blogimg.goo.ne.jp/img/static/admin/top/bnr_blogmura_w108.gif




