単なる故事の話
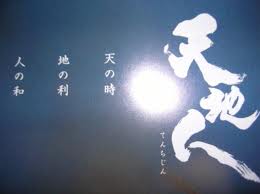
孟子曰
天時不如地利
地利不如人和
孟子いわく、
天の時は地の利に如かず
地の利は人の和に如かず
孟子は言う。
天のもたらす幸運は地勢の有利さには及ばず、
地勢の有利さは人心の一致には及ばない。
この孟子が戦略について語ったとされる言葉を、通常はこう解釈する。
何かを達成しようとするとき、
天の時を得ていても、
地の利がなければ成就することはできず、
地の利を得ていても、
人の和がなければ、これも成就することはできない。
人の和が何よりも重要である。
と。
「人は財なり」とよく言う。
個人的には、この言葉をさらにもう少しだけ進めて解釈することも優位であろうと思う。
実は、この言葉には続きがある。
(訳は面倒なので、ネットからコピペします。)
http://members.jcom.home.ne.jp/diereichsflotte/XunziMencius/LuckyIsNotAsLooksIsNotAsCooperation.html
三里之城、七里之郭、環而攻之而不勝。
夫環而攻之、必有得天時者矣。
然而不勝者、是天時不如地利也。
城非不高也。
池非不深也。
兵革非不堅利也。
米粟非不多也。
委而去之、是地利不如人和也。
故曰、
『域民不以封疆之界、
固国不以山谿之険、
威天下不以兵革之利。』
得道者多助、
失道者寡助。
寡助之至、親戚畔之、
多助之至、天下順之。
以天下之所順、攻親戚之所畔。
故君子有不戦。
戦必勝矣。
三里四方の内城と七里四方の外城を持つ程度の、たいして大きくもない町を攻囲しても勝てない。
そもそも攻囲を行っていれば、必ず天のもたらす幸運が訪れるときがある。
それなのに勝てないのは、天のもたらす幸運が地勢の有利さには及ばないからである。
城壁が高くないわけではない。
堀が深くないわけではない。
武器が鋭くなく、防具が頑丈でないわけではない。
食料が足りないわけではない。
それなのに、これらを放棄して退却せねばならなくなるのは、
地勢の有利さが、人心の一致に及ばないからである。
だから、
『民衆を領内のとどめるのに、盛り土による境界線を使わず、
国の守りを固くするのに、地形の険しさを頼らず、
天下を自らの威令の下に敷くのに、軍事力の優越を用いない。』というのである。
正しい道を心得ている者は、多くの援助が得られ、
正しい道を失っている者は、少ない援助しか得られない。
援助が少ない者の、極端な場合には、親戚さえもこれに背き、
援助が多い者の、極端な場合には、天下さえもこれに従う。
天下が従うところを以て、親戚さえも背くところを攻める。
だから、君子は戦うまでもないのだ。
戦えば必ず勝つ。
端的に言うと、正しい道を進めば、天下さえも従い、戦うまでもなく勝つことができる。
ということだが、結論だけに注目して、ついつい「人の和」に注目してしまいがちだ。
ただ、孟子が言いたかったことは、「人の和」が何より大事というようなことではなく、
「天の時」「地の利」「人の和」の3つを得ることが大事なのだが、
その3つを得るためには「人の和」を重んじることが大事だということだと私は思う。
それゆえ、「人」というより「天地人」というフレーズで覚えた方がいいのではないだろうか。
なにゆえ、このような話をしているかというと、「チャンスの順番」という言葉が多用されるにつき、誤解の可能性を感じるからだ。
人によって解釈が変わるこの言葉で、もちろん非常に立派な理解をしている人も多いのだが、そうでもない人も中にはいる。
そういう場合、「チャンスの順番」=「天地人」と解釈したら、わかりやすいのではないかという気がする。
かえってわかりにくいという人は、使わないでください(笑)
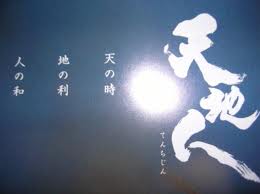
孟子曰
天時不如地利
地利不如人和
孟子いわく、
天の時は地の利に如かず
地の利は人の和に如かず
孟子は言う。
天のもたらす幸運は地勢の有利さには及ばず、
地勢の有利さは人心の一致には及ばない。
この孟子が戦略について語ったとされる言葉を、通常はこう解釈する。
何かを達成しようとするとき、
天の時を得ていても、
地の利がなければ成就することはできず、
地の利を得ていても、
人の和がなければ、これも成就することはできない。
人の和が何よりも重要である。
と。
「人は財なり」とよく言う。
個人的には、この言葉をさらにもう少しだけ進めて解釈することも優位であろうと思う。
実は、この言葉には続きがある。
(訳は面倒なので、ネットからコピペします。)
http://members.jcom.home.ne.jp/diereichsflotte/XunziMencius/LuckyIsNotAsLooksIsNotAsCooperation.html
三里之城、七里之郭、環而攻之而不勝。
夫環而攻之、必有得天時者矣。
然而不勝者、是天時不如地利也。
城非不高也。
池非不深也。
兵革非不堅利也。
米粟非不多也。
委而去之、是地利不如人和也。
故曰、
『域民不以封疆之界、
固国不以山谿之険、
威天下不以兵革之利。』
得道者多助、
失道者寡助。
寡助之至、親戚畔之、
多助之至、天下順之。
以天下之所順、攻親戚之所畔。
故君子有不戦。
戦必勝矣。
三里四方の内城と七里四方の外城を持つ程度の、たいして大きくもない町を攻囲しても勝てない。
そもそも攻囲を行っていれば、必ず天のもたらす幸運が訪れるときがある。
それなのに勝てないのは、天のもたらす幸運が地勢の有利さには及ばないからである。
城壁が高くないわけではない。
堀が深くないわけではない。
武器が鋭くなく、防具が頑丈でないわけではない。
食料が足りないわけではない。
それなのに、これらを放棄して退却せねばならなくなるのは、
地勢の有利さが、人心の一致に及ばないからである。
だから、
『民衆を領内のとどめるのに、盛り土による境界線を使わず、
国の守りを固くするのに、地形の険しさを頼らず、
天下を自らの威令の下に敷くのに、軍事力の優越を用いない。』というのである。
正しい道を心得ている者は、多くの援助が得られ、
正しい道を失っている者は、少ない援助しか得られない。
援助が少ない者の、極端な場合には、親戚さえもこれに背き、
援助が多い者の、極端な場合には、天下さえもこれに従う。
天下が従うところを以て、親戚さえも背くところを攻める。
だから、君子は戦うまでもないのだ。
戦えば必ず勝つ。
端的に言うと、正しい道を進めば、天下さえも従い、戦うまでもなく勝つことができる。
ということだが、結論だけに注目して、ついつい「人の和」に注目してしまいがちだ。
ただ、孟子が言いたかったことは、「人の和」が何より大事というようなことではなく、
「天の時」「地の利」「人の和」の3つを得ることが大事なのだが、
その3つを得るためには「人の和」を重んじることが大事だということだと私は思う。
それゆえ、「人」というより「天地人」というフレーズで覚えた方がいいのではないだろうか。
なにゆえ、このような話をしているかというと、「チャンスの順番」という言葉が多用されるにつき、誤解の可能性を感じるからだ。
人によって解釈が変わるこの言葉で、もちろん非常に立派な理解をしている人も多いのだが、そうでもない人も中にはいる。
そういう場合、「チャンスの順番」=「天地人」と解釈したら、わかりやすいのではないかという気がする。
かえってわかりにくいという人は、使わないでください(笑)









