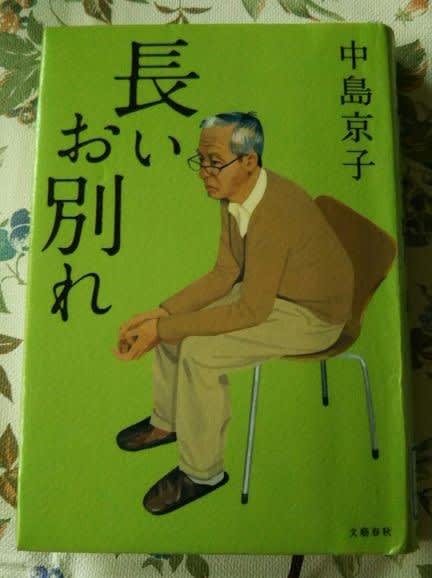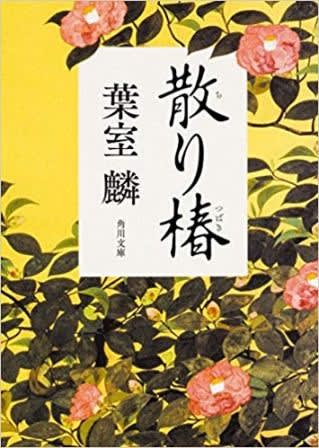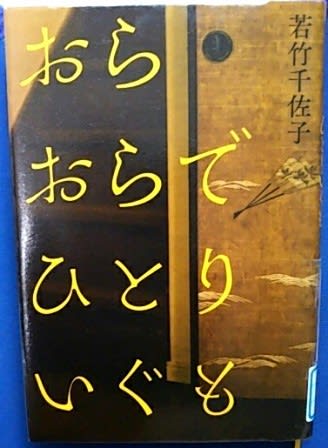本 「みかづき」: 森絵都 著、集英社 発行
永作博美、高橋一生主演のNHK土曜ドラマを見たのがきっかけ。 塾の問題、いや教育の問題がテーマ、舞台である八千代市が息子の住む家に近い、などの理由もあって、録画して最後まで見た。 直後、「あかね」のOさんの「本を読みましたよ」と言う言葉に思い立ち、図書館に予約。期間内に読み切れず延長して読んだ。
大河小説とも言うべき、家族4代にわたる長編小説。ハードカバーの分厚い本だ。
《あらすじ》
1961年、千葉県習志野市の小学校の用務員だった大島吾郎は、用務員室で私的な勉強会を始めていた。そこに来る児童のひとり、赤坂蕗子に吾郎は非凡なものを認める。蕗子の母の千明は、文部官僚の男との間に設けた蕗子を、シングルマザーとして育てていたのだった。2人は結婚し、近隣の八千代市に塾を開き、着実に塾の経営を進めていく。吾郎はワシリー・スホムリンスキーの評伝を書き、2人の間に娘も2人生まれ、千明の母の頼子も塾にくる子どもたちの成長に心を配る。しかし、2人の塾経営をめぐる路線の対立(吾郎はあくまでも補習塾を目指し、千明は塾を進学塾に変えようとする)のため、吾郎は家を出、千明の塾はさらに大規模になり地域の有力な存在となってゆく。
長女の蕗子、次女の蘭、三女の菜々美のその後の人生を通し、さらに蕗子の長男の一郎の世代まで、家族の物語でありながら戦後の日本の教育の物語だと思った。
大島吾郎は、昭和14年生まれで私と同じ。昭和21年に国民学校に入学し年度途中で小学校に変わり教科書を墨で塗りつぶした世代だ。妻の千明は昭和9年生まれ、彼女曰く「私は小学校には通えなかった。国民学校ってところで変な教育を受けて、これがすごく嫌だった。だから今でも学校やお国を信じられない。」 軍事教育をしっかり受けた世代で、戦後先生たちがコロッと変わった姿を見て文部省(当時)は信用できない、いつか自由に教育ができる塾で子供たちがわかる勉強を教えてあげたい、「学校が太陽なら塾は月」と願っている。
戦後の教育の変遷と教育に携わる一つの家族の物語。ちょうど同じ時代に教育と関わって生きてきた身としては一つ一つの出来事や言葉が身に染みた。 教育に完成はない。満月たり得ない途上の月のようなもの。常に何かが欠けている三日月、教育も同様そんなものかもしれない。欠けている自覚があるからこそ、人は満ちよう、満ちようと研鑽を積む…。 こんな言葉が胸に響く。
そして最後に、祖父母の存在に圧倒され教育の世界を避けていた孫の一郎が、官民連携教育をスタートさせる。 貧しく塾に通えない子供のための無料の学習塾だ。ボランティアや周囲の知人の協力のおかげで、行政と塾が連携すると言うところで話は終わる。さらに最後にとても素敵なエピソードが紹介されている。一郎の塾に通っていたN君が少しずつ勉強がわかるようになりテストでいい点数をとった。ところがカンニングをしたと友達に言われ先生に手紙を書く。その時の母親の言葉がこうだ。「テストの点数が上がったことより、先生に自分の気持ちを伝えることができたことがうれしい。筆で自分の気持ちを人様に伝えられる子ではなかった。力を与えてくださって…。」 教育は子どもをコントロールするためでなく、不条理に抗う力、たやすくコントロールされないための生きる力を授けるためにある…と言われ続けて来たことを思い出し感動した。
全員クラブ制、週休二日制、偏差値教育、ゆとり教育…いろいろな形を試してきた教育の世界。 富山県では「七三教育体制」と言うのもあった。何が良くて何が悪かったのだろう? そして今はどうなのだろう? と久しぶりに自分の辿った道を振り返ってみた。