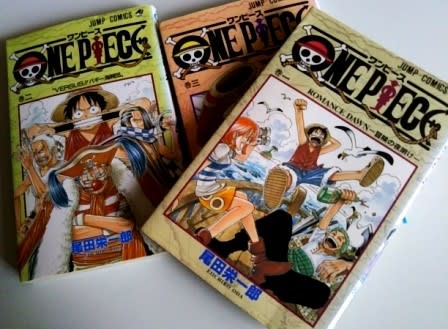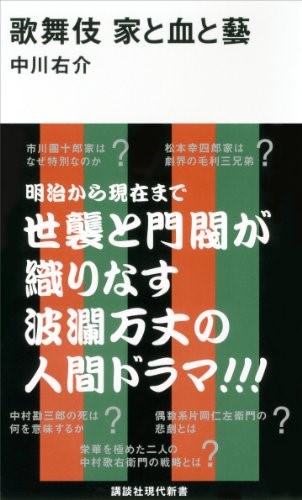なはさんからお借りした本、「『おかしないけ?』と、言い続けて」は伊藤冴子さんの半生記を、「NPO法人 Nプロジェクトひと・みち・まち」のメンバーが伊藤さんから聞き取りをして編集された本です。伊藤さんとなはさんは女学校の同級生だそうです。伊藤さんは中田にお住まいなので、私が中田で勤めていた頃名前だけ耳にしていました。かなり後になってから、高岡演劇鑑賞会の会合でお顔を拝見するようになりました。
1933年(昭和8年)、高岡市戸出大清水のお生まれで、6人姉妹の長女だったそうです。
大雑把に目次を追いますと:
はじめに
1.誕生から小学校入学まで
2.小学校時代
3.高等女学校入学、就職
4.結婚・出産、家業
5.仕事、高校入学、地域活動
6. 地域活動など、様々な活動に参画
私の想い
おわりに
お礼 となっています。 👇は、表紙です。
最初は、両親、祖父母など家族のことが語られます。そして子守や遊びの思い出…。私より6歳先輩なので時代背景がわずかズレています。が、戦後の暮らしぶりなどは似た部分がたくさんあります。
小学校では、とても正義感が強かった、と振り返っておられます。「おかしい」と思ったら先生にもきちんとお願いしたり、上級生の男の子ともケンカをしたそうです。国民学校卒業後は高岡高等女学校(4年制)へ進学、城端線での汽車通学、男女共学になったこと、村会議員選挙など私の体験と重なる部分が多くあります。戦後の民主教育が始まった頃でした。
そして戸出物産入社、労組活動、青年団活動、読書会…城端別院での青年団幹部研修会や当時の城端町長天富さんの名前などが出てきて、私には懐かしかったです。同級生のAさんが城端町で青年団活動をしておられたのです(少し後になるかもしれませんが)。
労組の婦人部長、全国婦人会議参加など体験され、結婚されます。長男を出産された後、家業の家庭薬配置業の仕事を、入院されたご主人に代わり継がれます。宮城県内をバイクで回ったそうです。長女出産後も14年間続けたそうです。配置業を辞めた後は、町の蕎麦屋に勤めながら定時制通信制の雄峰高校に入学しておられます。
そして長女が中学生の頃、中学校の先生(たぶんなはさん)に声をかけられ「読書会」を始められました(今も続いている)。30年以上世話役を続けたそうです。
今も、ベアテさんの会、シャキット富山35、尊厳死協会…等々での活動を続けておられる。
「人生経験が豊富な老人は、今までの経験をフルに生かして、個人が尊重され、戦争のない世の中を、子や孫に残してやることができる。それが人生最後の花道だと思う…」~おわりの言葉より。
「読み終わったら送るよ」と言っていた東京の同級生Aさんにさっそく郵送しました。彼女と6歳上の彼女のお姉さんにぜひ読んでもらって感想を聞きたいと思っています。同じ時代を生きた仲間として。