今から30年前、夫と最初で最後のヨーロッパ旅行に出かけた。イギリスから始まり、フランス、スイス、イタリア、ギリシャと5か国を回った。パリで1日か2日のフリータイムがあり、オルセー美術館、オランジェリー美術館、ルーブル美術館を見て回った。ルーヴルではツアーで回らなかった作品だけを見て回ったが、事前に先輩からミケランジェロの「奴隷」を観て来るようにアドバイスを受けていて、その彫像を探すのに苦労した想い出がある。
今年2月、銀座SIXの観世能楽堂へ「笛の会」を聴きに行き、翌日「新国立美術館」へ行った時「ルーヴル美術館展」のことを知った。9/2まで。うまい具合に8月末に城端小の同窓会をすると聞き、急きょ上京のプランを練った。1泊、1日目は美術館だけ、2日目新宿で同窓会(ランチの会)に出て帰る。心臓の手術を受けるかどうかまだ決心していない状態で、ゆったり一人旅ができるかどうかのテストの旅でもある。
「薪能」も終わり気分的には楽な頃、音訳ボランティアだけ休ませてもらうことにして上京した。月末になりまたまた暑さがぶり返した日、新幹線と地下鉄の利用だから炎天下は歩かない、つもり。
👇 地下鉄を何本か乗り継ぎ(距離が長くちょっと堪えた)、乃木坂から館内に入る。乃木坂入り口のポスター(企画展3つ)。
2時半頃着いたら入り口前に長い行列。でも待ち時間は10分とのこと。一番混む時間帯だ。が、大したことはない(8時まで開館しているが夜暗くなってホテルに着くのも嫌なので仕方がない)。
👇 4時半頃はこのように空いていた。 
👇 ルーブルの顔の中に、自分も入り写真を撮るコーナー。
「ルーヴル美術館展」~肖像芸術・人は人をどう表現して来たか。
「肖像は一人の少女がもうすぐ旅に出てしまう愛しい人をせめて何かの形として残したいという思いから始まった。」のだそうだ。
墓碑肖像:👆の写真で、ひときわ目を引くマスクは、およそ3000年前、棺に被せたマスク。来世をどんな顔で生きるか、その人が死後の世界を永遠に生きるための理想の顔が表現されたそうだ。…
権力の顔:
わずか5歳でフランスの国王になったルイ14世の胸像(真鍮)。
👇 フランス王妃マリー=アントワネットの胸像(磁器)
👇 「アルコレ橋のボナパルト」 1796年、27歳の将軍ナポレオン・ボナパルトはオーストリアとの戦いで、フランスを勝利に導いた。軍を率いている彼の強さと勇敢さを表す。(油彩) 
👇 戴冠式の正装のナポレオン1世の肖像(大理石)。…ガウンの襞が本物の布地のよう。音声ガイドでは、ここでベートーヴェンの交響曲「英雄」が流れます。 
コードとモード:長い歴史や肖像を作る時の決まり事(コード)を守りながらも、新しい時代の感覚や流行(モード)を取り入れた肖像作品。
👇 女性の肖像、通称「美しきナーニ」(油彩 カンバス)
胸に手を当て、不思議なほほえみをたたえた、一人の女性。彼女が誰か未だにわかっていない。16C、ルネサンス時代は王や貴族、皇帝だけでなく、より広い身分の人の肖像も作られた。どの角度から見ても目が合わない。
👇 赤い緣無し帽をかぶった若い男性の肖像(油彩 板)
👇 性格表現の頭像 鉛と錫の合金。モデルは、作者メッシャー・シュミット本人。心の病に悩んでいた彼は、このようなしかめっ面を作品にすることで、病に打ち勝とうとした。
”古代から18世紀まで、肖像の傑作が集結”と、パンフレットにあるようにまさに「ルーヴルの顔」110点が終結した。👆の写真は絵葉書やパンフからだが、他にも興味のある作品が多く、会場内もかなり混んでいたが途中何度か座って休みながらゆっくり眺めた。
ナビゲーターの高橋一生が音声ガイドで、彼自身のルーヴル探訪や注目作品について語り、興味深かった。説明文は学芸員の表現なのだろうが、彼独特のとつとつとした語りがわかりやすかった。






































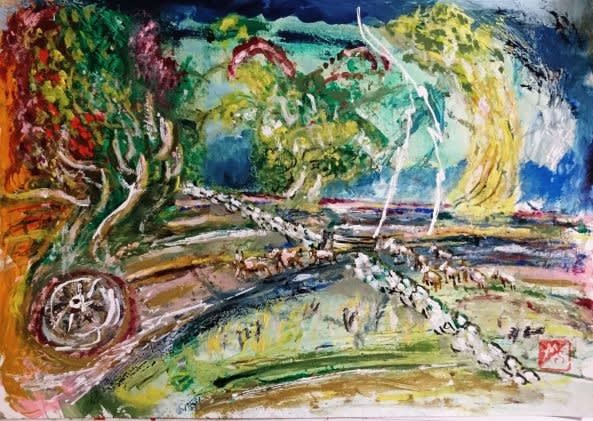

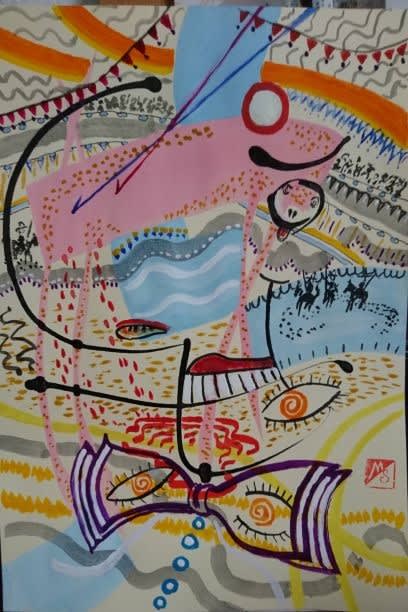




















































 「お茶教室」仲間のたくちゃんと恩師の有角先生の絵画作品展の案内をもらった。 名付けて「貴寿の会作品展」。なんと粋なネーミングだこと。米寿と喜寿だそうだ。 👇は案内状。 初......
「お茶教室」仲間のたくちゃんと恩師の有角先生の絵画作品展の案内をもらった。 名付けて「貴寿の会作品展」。なんと粋なネーミングだこと。米寿と喜寿だそうだ。 👇は案内状。 初......


























