全国高校サッカー選手権大会の富山第一高校の準決勝、決勝戦とも素晴らしい試合でしたね~。感動の涙、涙でした。14日の朝刊2紙を隅々まで読み返し、またまた涙がにじみました。
11日(土)の準決勝はずっと見ていたのですが、最後のPK戦は怖くて見られず音声だけ聞いていたのです。決勝は、しっかり観て応援しようと、テレビに向き合い目を離さず最後の瞬間までドキドキ、ハラハラしながら観戦しました。
13日(月)の星陵との決勝戦。2点差をつけられた後半42分、途中から入った高浪くんがゴール後すぐボールを持って駆け出す姿、時間がない、早く試合を続けようと言う気持ち、終了間際のPKを冷静に蹴ってゴールに入れた主将の大塚くん。同点で延長戦にもつれ込み、そこでも決まらずPK戦突入を目前に、村井くんが放ったゴール。ドラマの連続でした。99名の部員のほとんどが県内の生徒で自宅通学生だそうです。大塚監督の「子どもの頃から知っている者同士、田舎の子でも全国一になれることを証明でき嬉しい」の言葉を誇りに思った県民は多いことでしょう。
祝日だが息子は出勤しているか、家でテレビを見ていたか?と思いつつケータイにメールを入れました。「テレビ見ていましたか?感動的な試合だったね」と。折り返しの返事は「見ませんでしたが…、他の人からもその話でメールが来ました。」 会社の人か?同郷の友人か?でしょう。
さて、翌14日、近所の大木白山神社の左義長の日。朝、姫ちゃんの伏木・気多神社の左義長の様子をブログで見て思い出しました。大木白山神社は、高岡市大工中町、JR北陸線の線路南にある神社。ウイングウイングでのMiTuの練習日なので、途中神社に寄ってから行くことに。左義長は6時までなので、5時に家を出ました。雪がハラハラと落ちています。途中、お向かいのご夫婦と会いました。境内でも近所の方と数人会い、新年の挨拶を交わします。暗くなった境内で赤い炎が勢いよく燃え上がっています。 
↓ 拝殿前で、1年の無病息災をお祈りします。 
↓ 道路脇には、消防車が待機していました。 
↓ 線路側に回り、石垣の間から。 
この石垣と線路の間の道を駅方向へ進み、線路下の地下道をくぐると駅北へ出ます。たまに車か自転車で通りますが、めったに歩きません。地下道の両方の出入り口に、↓のような表示を見つけました。右は 階段、左はスロープです。この地下道の上を用水が流れていますから、浸水した時の目安でしょうか。見方がよくわからないけど、赤線まで達したら通行止めになるのでしょうか。 
7時の合唱までかなり時間があり、図書館で本を読んでいました。











































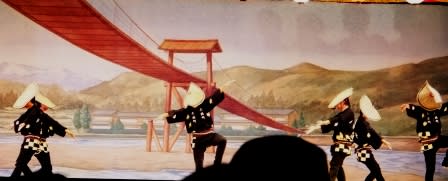











































 入浴料金「拾六園」から始っている。昭和30年代の料金表だった。
入浴料金「拾六園」から始っている。昭和30年代の料金表だった。





















































