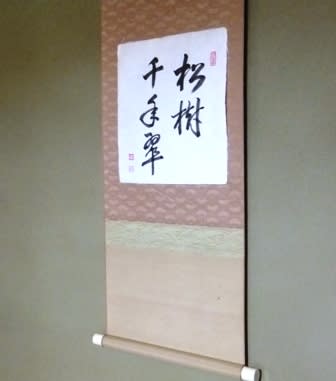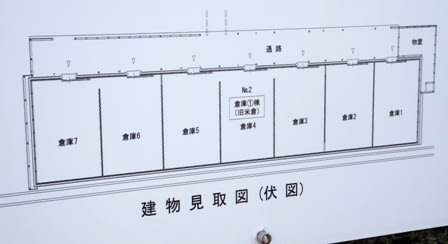9/27(日)、年に一度の大学支部同窓会が、富山高志の国文学館・ラベットラで開催されることになり、昨年欠席したので今年は出席を決めていた。福光の先輩も小矢部の同級生も欠席とのこと、が、蒼山会で一緒のSIさんが幹事であり、ブログ仲間の風子さんも出席と聞き、ホッとした。しかも、「ラベットラ・オチアイ」ではお茶を飲んだことしかないので、ランチが楽しみだった。
10時ギリギリに到着、どうやら駐車場に車を入れ会場の部屋に入るとまだ受付中で一安心。↓は、窓から見えるお庭。 
↓ 福岡町が舞台の「獅子舞ボーイズ」の制作にも関わられたと言う同窓生の竹内晶子さんのお話を聞く。今度の映画は「魚津のパン屋さん」。如月小春(久しぶりに聞くお名前)の劇団に入団したのがきっかけでその後演劇の仕事をしているそうだ。今の仕事は「俳優トレーナー」。女優としてもこの映画に出ておられる。東京と富山で半々に暮らしているとのこと。
ストーリーは、都会で失敗した若い女性が、パン店の開店を目指し、家族や魚津の人々と関わる中で成長する姿を描く。キャストの多くは地元でオーディションを行って決めたそうだ。なんと石井知事も出演、セリフもあるとか。「シアター大都会」で10/17から公開される。 
支部長さんの挨拶の後、テキパキとしたSIさんの司会で顔と名前だけの紹介、記念撮影が行われた。と言うのは、「ラベットラ」の食事時間がきっちり決まっているからだそう。レストランに入り、グループ毎に注文を取りに来られる。たくさんのチョイスができ迷ってしまう。最初は質問していたが、最後にはコレと指さす始末だ。↓は、店内の様子とメニューブック。PRANZOはイタリア語で ランチ。


↓ パン3種。
↓ 前菜。
ウにのパスタは写真の撮り忘れ。甘くてとろっと美味しかった。
↓ メインディッシュに選んだカジキのなんとか。
↓は、デザート。
↓は、玄関と知事公舎の頃のプレート。店の前には、次のグループの方たちがもう待っておられる。


再会を約束し、皆さんとはお別れ。風子さんは電車で来られたそうだ。私は娘たちとの待ち合せがハッキリ決まっていないのでひとまずそこでお別れした。駐車場は3時間は無料だと確かめ、後「○○してくださいね」の部分をいつもの早合点で聞き返しもせず、駐車場へ。さて、出口の料金精算機を見て驚いた。990円。タダかオーバーしても200円くらいのはず。文学館かラベットラで認証してもらわないといけないのだった。見れば後続の車が…。ええッ仕方がないと千円札を入れる。あ~あもったいない。