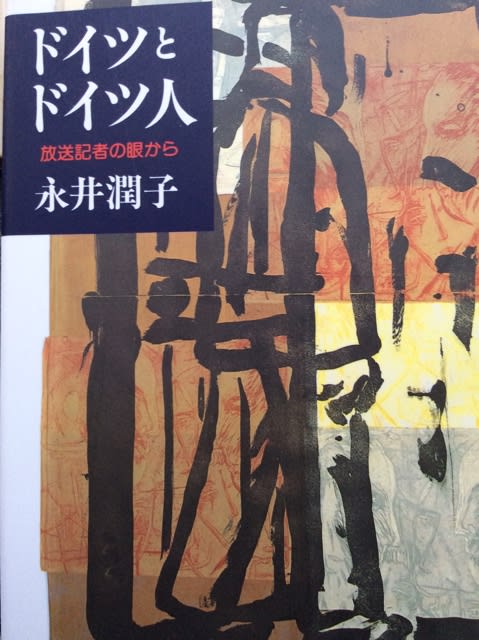8月末に花水木さんがブログでご紹介されていたので翌月(9月)に予定していた一時帰国で本を購入しようかとも思いましたが、帰独時の荷物はできるだけ少なくしたかったので電子書籍を購入しました。
読後2ヶ月以上経ってからの感想文です。
舞台は樺太(サハリン)で主人公は樺太アイヌのヤヨマネクフとポーランド人のブロニスワフ・ピウスツキです。
二人の共通点はヤヨマネクフは大日本帝国に、ピウスツキはロシア帝国に故郷の土地や統治権ばかりでなく言葉(母語)も奪われてしまったことです。
ヤヨマネクフは日本とロシアが勝手に締結した「千島樺太交換条約」により北海道に強制移住させられ、アイヌ語の代わりに日本語を学ばせられ、北海道から故郷の樺太(サハリン)に帰るときには「山辺安之助」という日本の旅券を作らなくてはなりませんでした。
一方ピウスツキは帝政ロシアにより解体させられたポーランド•リトアニア共和国の出身で、皇帝暗殺を企てた仲間の運動に巻き込まれて罪に問われ流刑地サハリンに送られてしまいます。その地で樺太アイヌの人々との交流が始まります。
因みにピウスツキの弟ユゼフは後にポーランド共和国の初代大統領となります。
この小説に登場するのは全て歴史上に実在した人物です。
後半アイヌ語辞典を編纂する金田一京助も登場しますが、同郷人として誇りに思いました。
この本を読書中また読後も強く感じたのは「祖国とは国語だ」ということです。
この言葉は敬愛する随筆家山本夏彦さんの本で知りました。
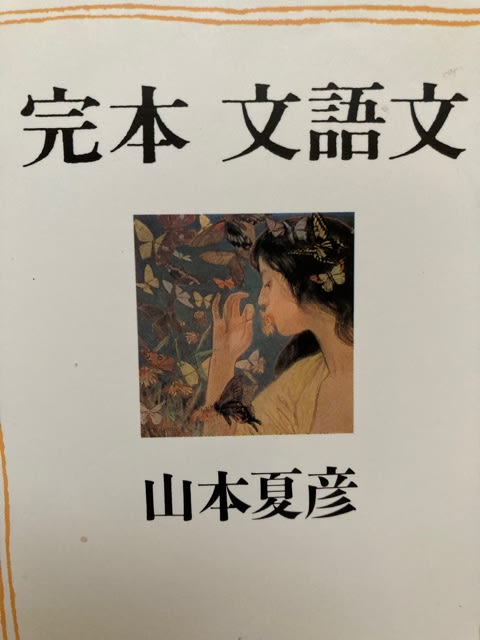
,
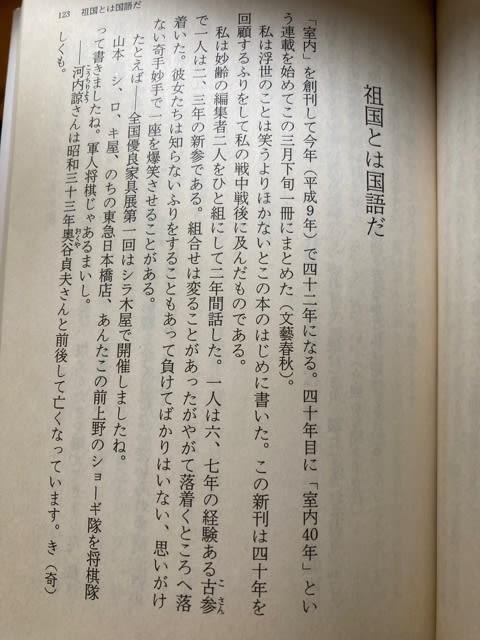
山本さんの言葉ではなくてルーマニアの作家で思想家のエミール・ミハイ・シオラン(1911-1995)の言葉だそうです。
「私たちは、ある国に住むのではない。ある国語に住むのだ。祖国とは国語だ。それ以外の何ものでもない」
この小説は2019年に出版され(第162回直木賞受賞)たのですが、電子書籍は2022年7月に出版された文庫本を底本としているため、中島京子さんのあとがきにはロシアのウクライナ侵攻についても記されています。
中島さんはーこの歴史小説の舞台は樺太(サハリン)であるが、いまを生きる私たちは「故郷」について、失われていく「文化」について、人の「帰るべき先」について考えさせられるーと記しています。
ロシアの侵攻により多くのウクライナの人々は故郷を離れなくてはなりませんでしたが、祖国でウクライナ語が話される限り、いくら廃墟になってもいつか故郷に戻るという意志は持ち続けることでしょう。その日が早く訪れるようお祈りします。