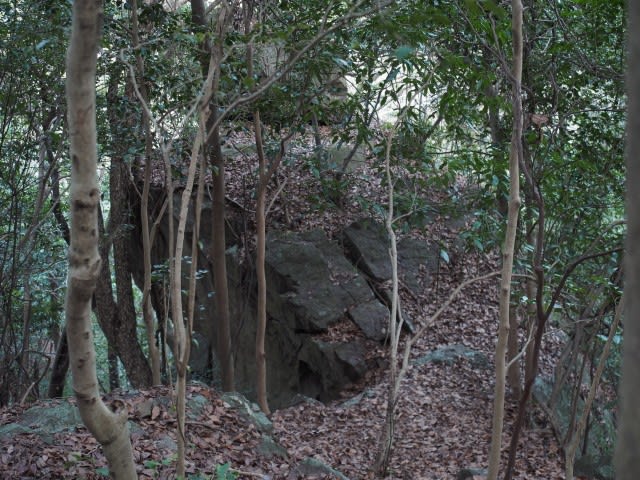妙見山上⇔妙見奥之院をピストン(その4)
登山道の行き先には歌垣山という山があり、この山行き計画時はそこまで行けないかと考えていた。
しかしポカポカ陽気のせいで脚の進みは悪く、廃墟で時間を使い、駐車場は16:30に閉まる。
到底到達できる見込みなし。
手前の妙見奥之院にお参りして引き返す事にした。

妙見奥之院へは道を間違えた。
歌垣山への道を分岐してすぐにまた分かれ道があったのだが、そこを右に曲がってしまったのだ。
歩いて行くと木々の間に大きな建物の屋根が垣間見えた。
山中にある奥之院という名前から、こじんまりとしたお堂がある位かと想像していたが、遥かに大きな寺院のようだ。
ところが近づいてみると、様子が変だ。
どうも建物の裏側に来てしまったみたいで、社務所らしき建物の隙間を通ってしか境内に入れない。
そんなところを通って怒られると嫌なので道を戻った。

木々の間から建物が見えた場所で道を間違えたのだと思い、登山道をさらに奥へと進む。
丸太を組んだ階段が設置されていたりして、道はしっかりしているのだが、道の真ん中に杉の木の幼木が何本も育ち始めていて、あまり人は歩いていなさそう。
進む方向もさっきの建物から離れていくので、これはもっと手前で道を間違えたなと本格的に引き返すことにした。
分かれ道まで戻り左側の道を行くと、すぐに奥之院の入口だった。

長い石段を上って境内に入ると、社務所があった。
さっき裏手から近づいた時、なにか機器の作動音がしていたので、誰か居るのだと思っていたが、入口や窓は閉まっており無人のようだ。
こんな山奥のお寺なのに常駐してるなんてすごいところだなと思ったが、さすがにそんなことは無かったようだ。
大きな本殿はさらに石段を上ったところに鎮座していた。
登山道の行き先には歌垣山という山があり、この山行き計画時はそこまで行けないかと考えていた。
しかしポカポカ陽気のせいで脚の進みは悪く、廃墟で時間を使い、駐車場は16:30に閉まる。
到底到達できる見込みなし。
手前の妙見奥之院にお参りして引き返す事にした。

妙見奥之院へは道を間違えた。
歌垣山への道を分岐してすぐにまた分かれ道があったのだが、そこを右に曲がってしまったのだ。
歩いて行くと木々の間に大きな建物の屋根が垣間見えた。
山中にある奥之院という名前から、こじんまりとしたお堂がある位かと想像していたが、遥かに大きな寺院のようだ。
ところが近づいてみると、様子が変だ。
どうも建物の裏側に来てしまったみたいで、社務所らしき建物の隙間を通ってしか境内に入れない。
そんなところを通って怒られると嫌なので道を戻った。

木々の間から建物が見えた場所で道を間違えたのだと思い、登山道をさらに奥へと進む。
丸太を組んだ階段が設置されていたりして、道はしっかりしているのだが、道の真ん中に杉の木の幼木が何本も育ち始めていて、あまり人は歩いていなさそう。
進む方向もさっきの建物から離れていくので、これはもっと手前で道を間違えたなと本格的に引き返すことにした。
分かれ道まで戻り左側の道を行くと、すぐに奥之院の入口だった。

長い石段を上って境内に入ると、社務所があった。
さっき裏手から近づいた時、なにか機器の作動音がしていたので、誰か居るのだと思っていたが、入口や窓は閉まっており無人のようだ。
こんな山奥のお寺なのに常駐してるなんてすごいところだなと思ったが、さすがにそんなことは無かったようだ。
大きな本殿はさらに石段を上ったところに鎮座していた。