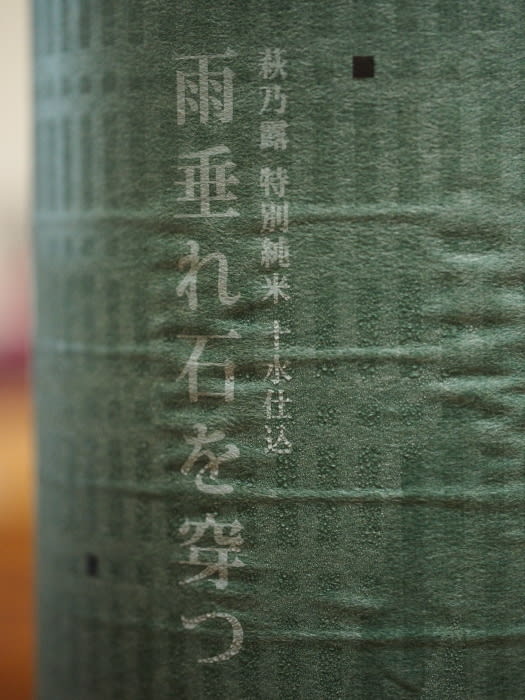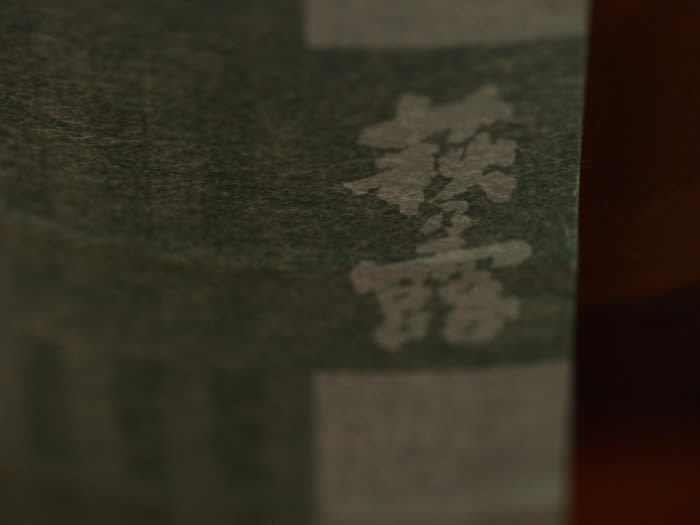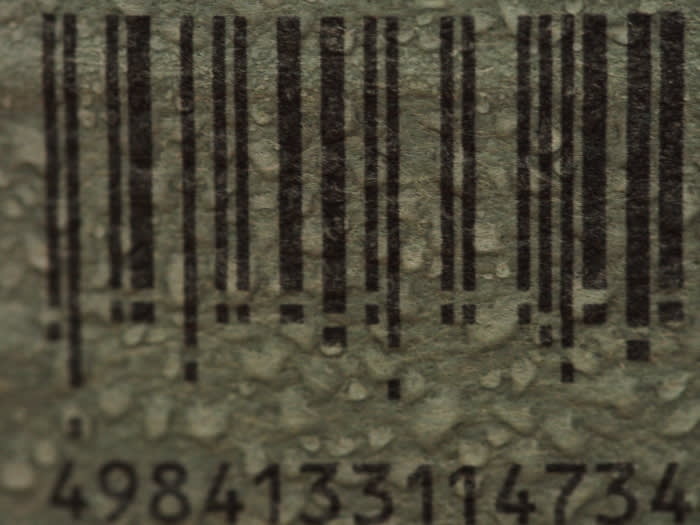満開ですな。
満開ですな。花が枝からこぼれ落ちそう。
朝晩の通勤時間が年に一度この時期だけスペシャルだ。
なんだろう、今年は特に「さくら」に気持ちを持っていかれてる。
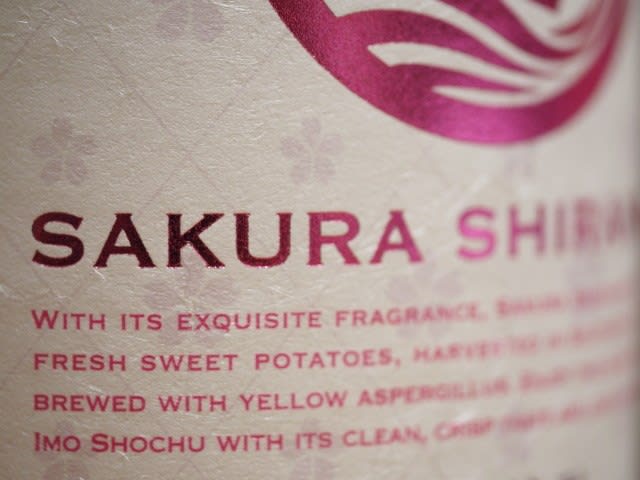
晩酌用の焼酎が切れたので、スーパーのお酒コーナーを覗いたら、いつもと違う商品が置いてあった。
「さくら白波」だって。
ぷふ。
もちろん手に取って、なに押しか確認しようと裏返したら、裏面にラベルはなく、白いすりガラスがつるんとしていた。

表のラベルには最低限の情報、商品名、原材料なんかしか書かれていない。
ああ、英語でなんか書いてあるな。
これが商品説明なのかな。
でも英語がダメな私には、ラベルデザインの一部でしかない。

芋焼酎か、どうしよう。
焼酎は最近泡盛なんかの米がお好みである。
こまごま説明してくれていると論理的に味を想像するが、なにも説明がないと雰囲気で味を想像するしかない。
芋で表すさくらな味かあ。

たまには芋もいいか、と買ってしまった。
情報量が少ない方がいいこともある。
さて、帰って飲んでみると、春らしい柔らかな風味。
ふんわり軽い飲み口。

もちろん商品名が先入観としてあるから、そのイメージが少なからず影響してるんだろう。
まあ、美味しく飲めるならなんでもいい。
暖かくなって来たし、庭付きの家に住んでるなら表に出て、朧なお月さんを盃に写して飲みたいところだ。













 不良社会人のする行為だからと、したこと無いとは決して言わないが、避けてきた方だ。
不良社会人のする行為だからと、したこと無いとは決して言わないが、避けてきた方だ。
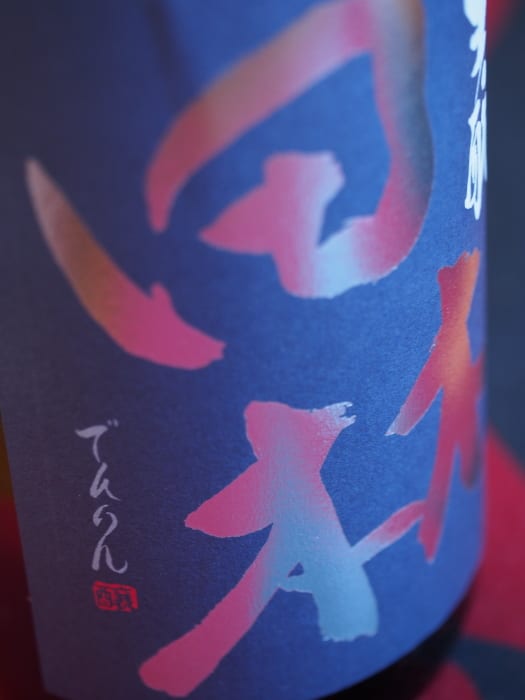
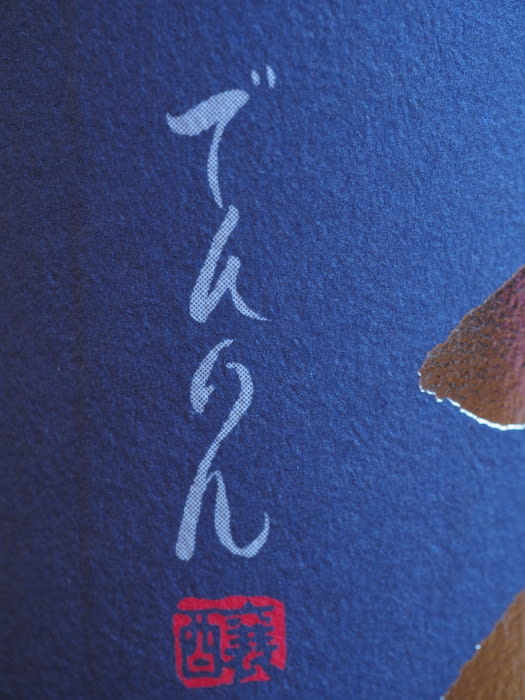
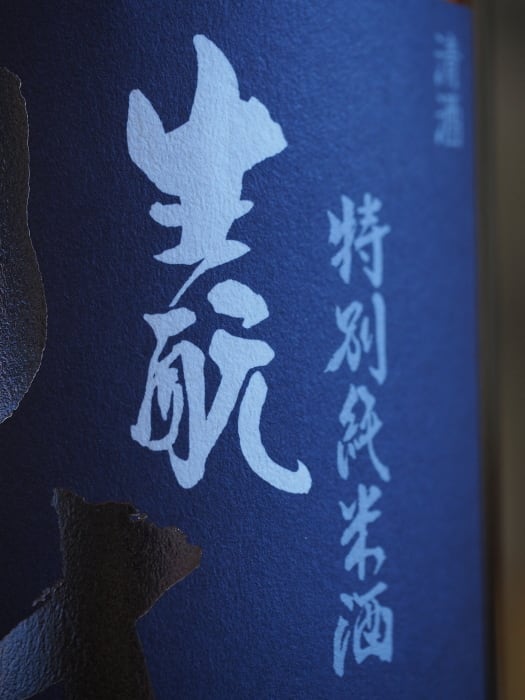













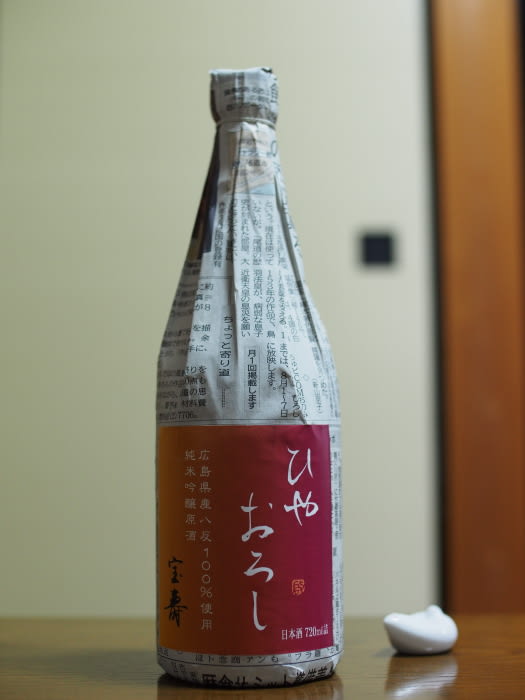




















 )ようやく開封。
)ようやく開封。 ワクワク。
ワクワク。