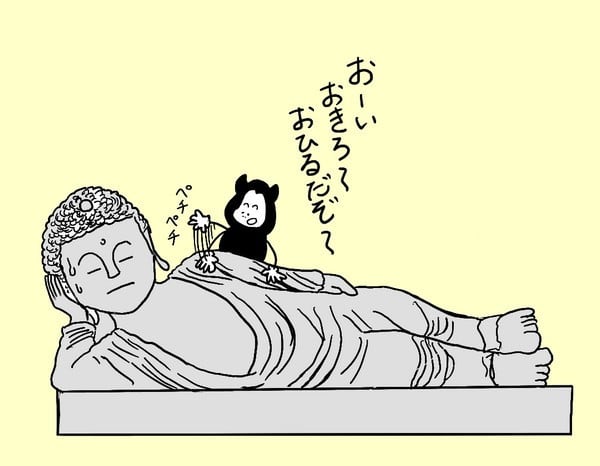九州の川が氾濫している。
懐かしい川の名前がでてくるたびに、テレビの映像に見入ってしまう。
山の木々が流され、橋が流され、車が流され、家が流されている。
その土地で何十年も生きつづけてきた人が、こんな災害ははじめてだと嘆いている。
川の姿もまわりの風景も、もはや自然の、いつもの風景ではない。
川も風景も、泥だらけ傷だらけになっている。
地図に記された幾筋もの川が、浮き上がった静脈のようにみえる。
その中の1本の川こそは、その川の水を飲み、その川の水を浴び、その川の魚と戯れて遊んだ、ぼくの血脈のような川、である。
川は、少年の日のぼくの風景、ぼくの心の故郷そのものとして、記憶の野を流れつづけている。だから今、どんなに暴れていても、川は生き物のように懐かしい。
たぶん、川はいま病んでいる。
その川の名前は、玉来川(たまらいがわ)。
とくに美しい川でもなく、大きな川でもない。
阿蘇の外輪山に降った雨水を元とする、小さな流れが源流である。そこから高原を東へとなだらかに下りながら、途中でいくつかの川を吸収したのち、玉来という古い街道に沿うように流れ込んでくる。そのあたりの川を玉来川と呼ぶ。
古代の大阿蘇の溶岩流の流れをたどるように、川は流れているようでもあった。しばしば噴火性の白い軽石が川面に浮いて流れていた。川底の石も、軽い石と重い石があった。軽い石は簡単に割れる花崗岩だった。
玉来(たまらい)という地名は珍しいかもしれない。
民俗学者の柳田國男も「豊後竹田町の西一里に玉来という町がある。湯桶訓(ゆとうよみ)の珍しい地名であるから、その後注意しているがいまだ同例を見ない。」(『地名の話』)と述べている。
同地名の語源について、狩りのために人が集まった場所「狩溜ライ」だと推理している。集まることをタマリと言い、阿蘇の地方では「リ」を「ライ」という風があったので「タマリ」が「タマライ」となったものだという。
いつの時代か、阿蘇の広大な裾野であった玉来のあたりでは、狩人が集まって盛んに狩猟が行われていたのだろうか。
また、地元の伝承を記録した『竹田奇聞』という古い書物には、700年ほど前の志賀氏が統治していた時代の話が載っている。
地元の豪族・入田丹後の守の城下町として賑わっていた頃のある夜、2個の隕石が後藤某の庭に落ちてきた。天から玉が降ったというので界隈の評判となり、「何かの吉兆祥瑞」ということで、その玉を裏の川で洗った。それから町名を「玉洗」と名付け、後に「玉来」となったという。
吉兆祥瑞の玉を洗った川で、芋の子のようになって小さな体を洗って遊んだ子供時代。その水の匂いと冷たさは、ぼくの体の芯から抜けることはない。
子供の頃も、玉来川が氾濫することはあった。
四軒家というは川のそばにあったので、洪水になると家が水に浸かっていた。だが、その辺りは川幅が広くなっていて家が流されることはなかった。
中学校も川のそばにあった。台風の時など校庭が増水した川に吸収されて、校舎だけが浮島のように孤立していた。水が引いたあとは生徒全員が駆りだされて、荒れたグランドの整備をさせられたものだった。
のちに、父の店も大きな水害に遭っている。
その時はJRの鉄橋も流され、橋のそばの民家も流されて死者が出た。
家の裏の石垣の上に避難していた父は、雨戸や家具が軽々と濁流に浮いて流されていくのを見ていたのだが、大事にしていた釣竿が浮いて流れるのを見つけると、それだけは必死で掬いとったという。
店の商品はぜんぶ流されてしまったのに、釣竿だけが手元に残った。そのときの父の行動は、何がそうさせたのだろうか。もしかすると商売よりも釣りの方が、父にとっては生きがいだったのかもしれない。
年のせいもあったが、そのあと父の商売は長くは続かなかった。
川はときには生き物のように暴れることがある。だが、いまも記憶の中の川は、変わらずに静かに流れつづけている。