
今日は期限が迫った資料作りで里山歩きをしました。
里山では土佐ミズキが春を迎える準備を始めていました。
厚い冬用の殻を脱ぎ緑をした芽を見せようとしています。
さて、テーマは日本一の砂留めについて述べますので見てください。
私が住んでいるこの町は3月から福山市に編入します。ここに堂々川と言う流域約4k㎡の小さな川がありますが暴れ川で1673年には長梅雨に台風と集中豪雨が重なり備後国分寺を初めとした多くの建物が流失し、63名の尊い命の犠牲もありました。
なぜこの川が暴れ川かといいますと広島県の花崗岩は長石と雲母類そして石英で構成されているので自然の風、水には弱く石が風化されて真砂と言う土になります。この土が土石流を起こす要素を含んでいます。またこの土は下流に堆積すればお米が出来なくなるし、海では海苔が不作になる。また塩田にも被害が出るので福山藩は1738年頃から砂留めを作り産業を守る事をはじめました。この時の砂留めが現在に引継がれ今日数えたら江戸時代の古いもの11基を含めて16群23基あり最大のものは高さ13.3メートル幅55.8メートルもあります。3世紀に渡り築き保守し、増築して現在に至るまさに日本一を継続している砂留めなのです。以下に砂留めの一部を下流から添付します。








一番砂留め、2番砂留めと続き6番砂留めが一番大きくここは現在砂留めに砂が満杯のなり公園になっています。
里山では土佐ミズキが春を迎える準備を始めていました。
厚い冬用の殻を脱ぎ緑をした芽を見せようとしています。
さて、テーマは日本一の砂留めについて述べますので見てください。
私が住んでいるこの町は3月から福山市に編入します。ここに堂々川と言う流域約4k㎡の小さな川がありますが暴れ川で1673年には長梅雨に台風と集中豪雨が重なり備後国分寺を初めとした多くの建物が流失し、63名の尊い命の犠牲もありました。
なぜこの川が暴れ川かといいますと広島県の花崗岩は長石と雲母類そして石英で構成されているので自然の風、水には弱く石が風化されて真砂と言う土になります。この土が土石流を起こす要素を含んでいます。またこの土は下流に堆積すればお米が出来なくなるし、海では海苔が不作になる。また塩田にも被害が出るので福山藩は1738年頃から砂留めを作り産業を守る事をはじめました。この時の砂留めが現在に引継がれ今日数えたら江戸時代の古いもの11基を含めて16群23基あり最大のものは高さ13.3メートル幅55.8メートルもあります。3世紀に渡り築き保守し、増築して現在に至るまさに日本一を継続している砂留めなのです。以下に砂留めの一部を下流から添付します。








一番砂留め、2番砂留めと続き6番砂留めが一番大きくここは現在砂留めに砂が満杯のなり公園になっています。











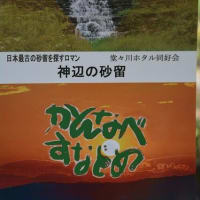
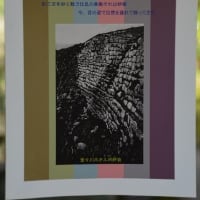




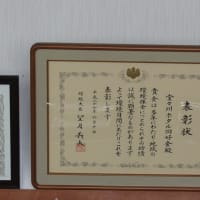


里山といっても猪は出るし、ウサギの糞はいたるところで見ます。夏になればマムシもでるようです。
上流にはゴルフ場も特養施設もごみ焼却場もあります。
ラベンダーKさん
「自然と歴史と薬草と」が現在のライフワークです。
このテーマは近々ホタル勉強会をしますが先生から4年生だと砂留めとはどんなものと質問が出るかもといわれ急いで取材したもののまとめなのです。
めだか、川エビ、アメンボ、カワニナ、シジミ、ヤゴ
沢蟹と結構豊富なようです。また水晶の小さいのが取れていましたが今はどうかな?です。
横浜のおーちゃんさん
塩の生産販売が財政の主要部分のようですから力の入れようも大変なものだったのでしょう。
すでに満杯になっているところが8箇所ありそこには公園が3箇所あります。昭和の20年代はそこで草競馬をしていたとも聞いています。
好きこそ物の上手なり。好きでなければやってられませんね。しかしいつの世にも人がよくなれば腹の立つ人はいるみたいです。
tkhsさん
どのくらい埋ったのですか?
朱子学の菅茶山先生(頼山陽の先生)が川の中に烏岩あり、その高さ2丈その上に砂が3丈ありと江戸時代の文書に載せています。
生まれも育ちも広島県ですが途中、博多で少し、東京で数年、岡山でもすこし、最近では横浜で10ヶ月生活しました。堂々川の氾濫は時間雨量が5㎜も降ればおこります。年に1~2回あります。
今でもこの川の流域では砂留めを作っています。平成
12年完成のネームがある砂留めもあります。砂留めの間隔は短いものは50m長くても200mぐらいです。
気楽さん
計算ありがとうございます。
考えてみれば上流で砂を止めてしまえば美しい海岸線や砂浜はもう出来なくなりますね。例えば巌流島の砂浜など。
いつもは水の少ない優しい川ですが少し強い雨が降ると砂が流れます。真さ土は築山を築くときは最高ですが水が混ざると悪い事をします。
yoshiさん
砂留めは砂防ダムのことです。確か富士山も江戸時代に大爆発をしてからその後は静かですよね。堂々川も江戸時代以降は人が亡くなるような洪水はありませんが小さな池は決壊した事があります。
災害から守るために昔から今に受け継がれているのですねぇ。
里山登りお疲れさまでした。
福島県は山と温泉が沢山あります。
里山も沢山あり、やがて行き着くところは里山。
里山とは言え侮れない。
永年の努力に頭が下がります。
満杯になると、何か処置をするのでしょうか。
海外に住む友人は、外から見ていて、日本ほど危ない国はないと常々言っています。
13m以上の砂留めが必要なほどの暴れ川も普段はいろいろな生物を育む皆に愛されるやさしい川なのだと思います。
・砂留めやホタル守る一里塚 〔縄〕
ご苦労多きと思いますが
『夏を彩るパラダイス・俺がやらネバ誰がやる』
頑張ってください。
日本一の砂留め拝見させていただきました。
堂々川は、現代は氾濫は収まったのでしょうか?今だにむかしの面影を残しているようですね。
最初の被害は 333年前
工事の始まり 268年前?100年の計とは
正に この事ですね!!
流石 自然を尋ねる人さんの 心が 理解できました.....写真楽しみましたョ.
又 遊びに 来ます.
富士山も大沢崩れという場所があり、頂上近くから崩れて、それを防ぐため砂防ダムがあります。
こうやって見ると、小さい川なのに。
昔の人はいろいろな知恵を働かせたのですね。
土佐水木、うちにもあります。
そういえば蕾が少し大きくなってきました。
去年は咲き始めたら、み~んなヒヨドリに食べられてしまいました。
厄介者が 今 残り
有名?になっている。
丸いだけでは 面白くない。
とんがった部分が またこれ 個性でしょうか。