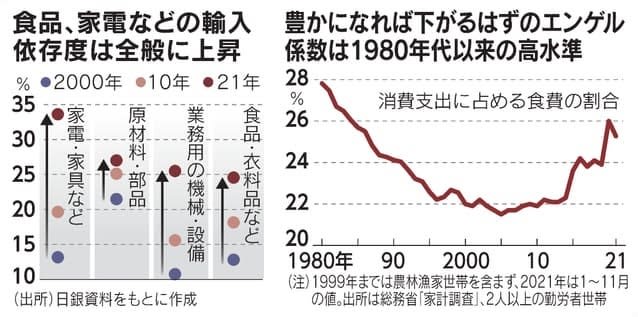目を背けず、現実を見つめよう(2)―円安の奥に何が―
前回の、“目沿背けず、現実を見つめよう(1)”では、円安の実態をさまざまな角度から検討し、
その原因についても一部、ふれました。
たとえば、“ビッグマック指数”で比較すると、日本はアジア諸国と比べても安い方で、それは働き
手の賃金水準、家賃、その国の生活水準(所得水準)によって決まります。
さらに最近、テレビの情報番組で、さらに驚くべき円安の進行事情のニュースが流れてきました。
一つは、最近日本と韓国との旅行が一部解禁されたことにより、韓国からの訪日希望者が激増し
ているとのことでした。
日本にある韓国の旅行代理店によると、とりわけゴルファーの希望が殺到しているようです。と
いうのも、今、ソウル近郊のゴルフ場でゴルフを楽しむと、1日で4万円近くかかるからです。
ところが、日本では7500円からプレーできるので、交通費や旅費を含めても日本に来てゴル
フをした方がずっと安いのだそうです。
もうひとつは、今年はうなぎの値段が高騰するとのニュースです。中国ではもともとうなぎは高
級食材だったのですが、最近は特に人気が上昇し、国内消費が増加したのです。
農水省によれば、昨年(2021年)のうなぎの国内供給量は、62,926トン。うち輸入42,290ト
ン、国内養殖20,573トン、国内天然63トン(0.1%)です(注1)。
つまり、総供量の3分の2以上が輸入うなぎで、ほとんどが中国と台湾産です。これら両国でも
ウナギの養殖は盛んで、以前は日本向けに輸出していました。
しかし現在は、日本に売るよりも中国や台湾の国内に出荷した方が高値で売れるのだそうです。
このため、日本でのうなぎが品薄になり、国産であれ輸入物であれ、うなぎの価格は高騰してし
まうのです。
これらの事例は、一方で、“円安”の影響を反映していますが、別の面から見て韓国や中国・台湾
からみて日本は“安い国”になっていることがわかります。
かつて、日本人が開発途上国に行くと、全てが安く感じられましたが、それと同じことが、今や
外国化から見て日本の全てが安く感じられるようです。
この背景には、日本人の収入水準がこの30年間、ほとんど増えていないという現実があります。
ちなみに、最近米アップル社が従業員の最低時給を22ドルに引き上げた。1ドル135円換算
で2970円です。ヨーロッパでも、ドイツ政府は最低賃金9.8ユーロを、今年10月から12
ユーロ(約1700円)に引き上げる予定です。
これに比べて日本の動きはいかにも鈍いままです。全国の加重平均最低賃金額は930円。地方
では800円台の県もあります。
今月に公表された政府の「骨太の方針」でも「できる限り早期に1000円を目指す」だけで、具
体的な賃上げ時期は示されませんでした。
日本の最低賃金1000円という“目標値”でさえも、ドル換算で7.5ドルほど。先進国から見たら
かなり低い水準です。
古賀茂明氏は、このような状況になったのは自民党政権は財界の要請で1996年の「労働者派遣法」
の大幅改定によって、非正規雇用をそれまでの13業種から26業種へ拡大し、さらに2004年には
ついに、”聖域“だった製造業にまで拡大したからだ、と指摘しています(注2)。
実際、契約社員や年期付き雇用や臨時雇用、アルバイト契約など、低賃金で解雇し易い非正規雇用
を増やしてきました。
おそらく、自民党のスポンサーである財界の要請を受けて、こうした”労働形態の多様化“という、耳
障りの良い言葉で、実質的な低賃金が固定化されてしまいました。
日本の多くの企業は、一時的には低賃金のメリットで、コストを安く抑えることができて、大いに喜
んだかも知れません。しかし、これは非常に近視眼的な姿勢です。
したがって、回りまわって、国内市場を狭め、日本経済全体の沈滞をもたらしているのです。
つまり長期的には国民の多くの所得が低いままだと、国内の購買力が減少し、消費は伸びません。労
働者の低賃金→低い購買力→製品価格の低迷→企業利益の減少→労働者の低賃金、という「負のスパ
イラル」が完成してしまっています。
下の図(注3)は、OECD加盟35カ国(比較的豊かな国)のうち、日本はどのあたりに位置して
いるかを示したものです。

日本のGDPは確かにアメリカ、中国に次いで世界第三位ですが、労働者の平均賃金でみると、OE
CD加盟国35カ国中22番目。これが、偽らざる日本の実像です。
この図が意味するところは、国全体のGDPではなく、個々の日本人の賃金が世界の水準と比べてと
ても低いことです。
同じアジアの韓国には5年前に抜かれてしまっています。実数でいうと、2020年の年収で日本は韓国
より3445ドル少ない。これを2022年7月の1ドル=135円で換算すると、46万5000円も
少ない計算です。
政府による、低賃金政策と法人税の引き下げがあまりにも簡単に実施されてしまったので、企業はそ
れによる利益に甘んじてしまい、もっと本質的な生産性の向上のための技術革新や新規事業の開拓な
どに投資する意欲を失ってしまったかのようです。
その一方で、得た利益はひたすら「社内留保金」として貯め込んでしまい、働く人たちに配分するわ
けでもなく、かといってリスクを負って新たな事業に投資するわけでもありません。
もっとも、これは大手企業の場合であり、雇用全体の6割以上を占める中小企業では社内留保金を貯
め込む余裕などなく、多くの場合、大企業の下請け的立場で、生き残るためにさらなる人件費の削減に
追い込まれ、したがって低賃金が定着するというサイクルに陥っているというのが実情です。
安倍政権の下で、企業に地位上げをを要請しましたが、一向に賃金は上がりませんでした。岸田首相
も労働者の賃金を上げるよう企業に要請していますが、賃金を払うのは企業であり、政府が操作でき
るものではありません。
日本の企業の中でも、一部の輸出企業は円安によって巨額の為替差益が入るので、それに満足し、円
安政策を歓迎しています。
日本の平均賃金が低いのは、政府の政策やリスクを負いたくない企業の体質の他にもいくつかの理由
があります。それについては、次回にもう少し掘り下げて検討します。
(注1)農水省のホームページ https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0106/15.html
(注2)古賀繁明氏のコラム 『週刊プレイボーイ』デジタル版(2022年7月1日)
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2022/07/01/116679/
(注2)DIAMOND ONLINE (2021 年8月2日 5:20)
前回の、“目沿背けず、現実を見つめよう(1)”では、円安の実態をさまざまな角度から検討し、
その原因についても一部、ふれました。
たとえば、“ビッグマック指数”で比較すると、日本はアジア諸国と比べても安い方で、それは働き
手の賃金水準、家賃、その国の生活水準(所得水準)によって決まります。
さらに最近、テレビの情報番組で、さらに驚くべき円安の進行事情のニュースが流れてきました。
一つは、最近日本と韓国との旅行が一部解禁されたことにより、韓国からの訪日希望者が激増し
ているとのことでした。
日本にある韓国の旅行代理店によると、とりわけゴルファーの希望が殺到しているようです。と
いうのも、今、ソウル近郊のゴルフ場でゴルフを楽しむと、1日で4万円近くかかるからです。
ところが、日本では7500円からプレーできるので、交通費や旅費を含めても日本に来てゴル
フをした方がずっと安いのだそうです。
もうひとつは、今年はうなぎの値段が高騰するとのニュースです。中国ではもともとうなぎは高
級食材だったのですが、最近は特に人気が上昇し、国内消費が増加したのです。
農水省によれば、昨年(2021年)のうなぎの国内供給量は、62,926トン。うち輸入42,290ト
ン、国内養殖20,573トン、国内天然63トン(0.1%)です(注1)。
つまり、総供量の3分の2以上が輸入うなぎで、ほとんどが中国と台湾産です。これら両国でも
ウナギの養殖は盛んで、以前は日本向けに輸出していました。
しかし現在は、日本に売るよりも中国や台湾の国内に出荷した方が高値で売れるのだそうです。
このため、日本でのうなぎが品薄になり、国産であれ輸入物であれ、うなぎの価格は高騰してし
まうのです。
これらの事例は、一方で、“円安”の影響を反映していますが、別の面から見て韓国や中国・台湾
からみて日本は“安い国”になっていることがわかります。
かつて、日本人が開発途上国に行くと、全てが安く感じられましたが、それと同じことが、今や
外国化から見て日本の全てが安く感じられるようです。
この背景には、日本人の収入水準がこの30年間、ほとんど増えていないという現実があります。
ちなみに、最近米アップル社が従業員の最低時給を22ドルに引き上げた。1ドル135円換算
で2970円です。ヨーロッパでも、ドイツ政府は最低賃金9.8ユーロを、今年10月から12
ユーロ(約1700円)に引き上げる予定です。
これに比べて日本の動きはいかにも鈍いままです。全国の加重平均最低賃金額は930円。地方
では800円台の県もあります。
今月に公表された政府の「骨太の方針」でも「できる限り早期に1000円を目指す」だけで、具
体的な賃上げ時期は示されませんでした。
日本の最低賃金1000円という“目標値”でさえも、ドル換算で7.5ドルほど。先進国から見たら
かなり低い水準です。
古賀茂明氏は、このような状況になったのは自民党政権は財界の要請で1996年の「労働者派遣法」
の大幅改定によって、非正規雇用をそれまでの13業種から26業種へ拡大し、さらに2004年には
ついに、”聖域“だった製造業にまで拡大したからだ、と指摘しています(注2)。
実際、契約社員や年期付き雇用や臨時雇用、アルバイト契約など、低賃金で解雇し易い非正規雇用
を増やしてきました。
おそらく、自民党のスポンサーである財界の要請を受けて、こうした”労働形態の多様化“という、耳
障りの良い言葉で、実質的な低賃金が固定化されてしまいました。
日本の多くの企業は、一時的には低賃金のメリットで、コストを安く抑えることができて、大いに喜
んだかも知れません。しかし、これは非常に近視眼的な姿勢です。
したがって、回りまわって、国内市場を狭め、日本経済全体の沈滞をもたらしているのです。
つまり長期的には国民の多くの所得が低いままだと、国内の購買力が減少し、消費は伸びません。労
働者の低賃金→低い購買力→製品価格の低迷→企業利益の減少→労働者の低賃金、という「負のスパ
イラル」が完成してしまっています。
下の図(注3)は、OECD加盟35カ国(比較的豊かな国)のうち、日本はどのあたりに位置して
いるかを示したものです。

日本のGDPは確かにアメリカ、中国に次いで世界第三位ですが、労働者の平均賃金でみると、OE
CD加盟国35カ国中22番目。これが、偽らざる日本の実像です。
この図が意味するところは、国全体のGDPではなく、個々の日本人の賃金が世界の水準と比べてと
ても低いことです。
同じアジアの韓国には5年前に抜かれてしまっています。実数でいうと、2020年の年収で日本は韓国
より3445ドル少ない。これを2022年7月の1ドル=135円で換算すると、46万5000円も
少ない計算です。
政府による、低賃金政策と法人税の引き下げがあまりにも簡単に実施されてしまったので、企業はそ
れによる利益に甘んじてしまい、もっと本質的な生産性の向上のための技術革新や新規事業の開拓な
どに投資する意欲を失ってしまったかのようです。
その一方で、得た利益はひたすら「社内留保金」として貯め込んでしまい、働く人たちに配分するわ
けでもなく、かといってリスクを負って新たな事業に投資するわけでもありません。
もっとも、これは大手企業の場合であり、雇用全体の6割以上を占める中小企業では社内留保金を貯
め込む余裕などなく、多くの場合、大企業の下請け的立場で、生き残るためにさらなる人件費の削減に
追い込まれ、したがって低賃金が定着するというサイクルに陥っているというのが実情です。
安倍政権の下で、企業に地位上げをを要請しましたが、一向に賃金は上がりませんでした。岸田首相
も労働者の賃金を上げるよう企業に要請していますが、賃金を払うのは企業であり、政府が操作でき
るものではありません。
日本の企業の中でも、一部の輸出企業は円安によって巨額の為替差益が入るので、それに満足し、円
安政策を歓迎しています。
日本の平均賃金が低いのは、政府の政策やリスクを負いたくない企業の体質の他にもいくつかの理由
があります。それについては、次回にもう少し掘り下げて検討します。
(注1)農水省のホームページ https://www.maff.go.jp/j/heya/kodomo_sodan/0106/15.html
(注2)古賀繁明氏のコラム 『週刊プレイボーイ』デジタル版(2022年7月1日)
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2022/07/01/116679/
(注2)DIAMOND ONLINE (2021 年8月2日 5:20)