翌朝(8/19)は4時に一斉に電灯がともった。広々とした寝床だったので、ゆっくりと寝ることができた。着換えを済ませたが、パンツを忘れてしまい、パンツだけは3日間同じ物をはく羽目になる。他の着替えは問題ない上、前日着ていた服は大雨で汗も流され、しかも乾燥室で乾かしたので、3日目に着ることも可能だ。
ちなみにこの小屋では水が不足しているので洗顔は禁止である。歯磨きでは歯磨き粉を使えない。しかし、給水用の流しでは、そうしたルールを守らずに洗顔や歯磨き粉を使った歯磨きをしている人がいて興ざめだった。
ところで、夜の間に困った事態になってしまった。携帯の充電が切れてしまったのである。充電はしっかりしてきたつもりだったのだが、夜の間に電話が3件も入り、それで充電が減ってしまったらしい。幸いパソコンの横には携帯の有料充電器が設置されているので、短い時間ではあったが充電をする。
外へ出てみると、前日とは打って変わって雲一つ無い空である。いや、雲はあるのだが、上空ではなく山の下の方に広がっている。そう、山は雲海の上にあったのである。
東の空の彼方は明るくなり始めている。日の出まではあと1時間ほどある。小屋の玄関は既に多くの人でにぎわっている。彼らは皆槍ヶ岳の山頂でご来光を見ようとする人達である。山の方を見ると、既にヘッドランプの明かりが点々と見える。
俺はさすがにそこまでしようとは思わないし、何よりヘッドランプがない。それでも前日登った時は一面ガスの中で、周囲の景色を眺めることはできなかったので、朝食を早めに食べ、他の人が朝食を食べている間の人の少ない時間に改めて登頂しようと考えた。
さすがに寒いので、小屋の中に入ったり出たりしているうちに、東の空はどんどん明るくなってきた。朝食は先着順なので早めに並び、食べ始める頃にちょうど日の出となり、慌てて朝食をかき込んで、外へ出て写真を撮した。
それにしても素晴らしい日の出である。一面の雲海の彼方から日が登る。左手には槍ヶ岳の山頂部分が大きく聳えている。右手には、高さは随分低いが、常念岳が美しい山容ですっくと聳えている。小屋のある場所とおぼしきところでは、カメラのフラッシュがたかれるのが見える。遠く北穂高小屋でフラッシュが光るのが見えたほどである。
荷造りをした後に荷物を持って小屋を出、ベンチに荷物をデポしておき、カメラだけ持って改めて山頂へと向かった。山頂方面からは、日の出を見た人達が次々と下山してくる。山頂への登山道のうち、始めの部分と山頂下のところだけは同じルートを通るが、それ以外の所は別のルートを通っているので、登っている分にはあまり混雑を気にしなくてもよさそうだ。登山道そのものは昨日一度登っているので容易に登れる。途中で高校生とおぼしき20人ほどの一行とすれ違った。きっとこの近辺でテント泊をした、どこかの高校の山岳部の面々だろう。
朝が早いだけに素手には岩が冷たい。ちなみに今回の登山では俺は手袋を使わなかった。手袋そのものが嫌いということもあるが、それ以上に手袋をはめると手のひらの感覚が鈍るような気がするのである。ただでさえ今回のルートでは岩やはしご、鎖に手をかけて上り下りしなくてはならない。そんな中で手の感覚が鈍るのは危険にもつながる。確かに手をすりむいたりするリスクは伴うが、俺はそれ以上に感覚が鈍ることから生じるリスクの方を避けたいと思ったのである。これは去年の剱岳でも同じであった。
山頂へ着くまでは登るのに夢中で、周囲の光景など気にならなかった。最後のはしごを登って山頂に着くと、四方に素晴らしい光景が広がった。西に笠ヶ岳(槍ヶ岳の鋭い影が映っている)、北西に黒部五郎岳・薬師岳・鷲羽岳・黒岳、北に立山、北東に白馬岳・鹿島槍ヶ岳、東に常念岳、南に穂高連峰とこれから通るルートが一望される。遠く南西の空には積乱雲が見え、今後の天気が心配されたが、大キレットはむしろガスがかかるくらいの方が怖さも半減していいのではないかと思った。
下りの方が時間がかかったのは前日と同じである。6時過ぎに小屋まで下山し、いよいよ穂高岳山荘までの3,000メートルを超える稜線歩きが始まる。途中には大キレットという北アルプスの一般コースで1,2を争う難所を通過することになっている。しかし大キレットの始まりである南岳までは、アップダウンもさほどない気持ちの良い稜線歩きである。大喰岳、中岳と眺めの良いピークを通過する。特に南岳の手前のツバメ岩からの槍ヶ岳の眺めは素晴らしかった。前日槍ヶ岳の姿をまともに見られなかっただけに、その感動も大きかった。
南岳の直前でライチョウの親子に遭遇した。昨年の剱岳では遭遇しなかったので、特にヒナはとてもかわいかった。
南岳には8時前に着いたのだが、実は中岳の山頂で槍ヶ岳の写真を撮したところで携帯の電源が切れてしまい、この後の写真撮影はデジカメのみとなった。携帯は時計の役割もあって、この後は時間がわからずに困ってしまったので、大休止をするたびに、そばにいた人に時間を聞いた。山に時計は必需品なので、聞かれた人はさぞかし変に思ったことだろう。
南岳からはいよいよ大キレット越えが始まる。


















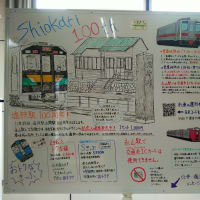

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます