
《0 ↑ 『秋田市立土崎図書館』》(平成25年11月28日撮影)
ところで、宮澤賢治は昭和3年8月10日に、我が身を削るようなそれまでの献身的な活動により(気候不順による稲作の不良を心痛し、風雨の中を徹宵東奔西走し)遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、帰宅して父母のもとに病臥したと一般には言われている。
一方同じ頃、岩手県では同年秋10月の「陸軍特別大演習」を前にして凄まじい「アカ狩り」が行われ、例えば、盛岡中学の英語教師平井直衛は昭和3年8月にその「アカ狩り」によって盛岡中学を首になったが、直衛の弟荒木田家寿が言うところによれば、その理由はせいぜい例の『種蒔く人』を初めて盛岡に持ち込んだ程度の理由であろうことが窺える、ということだったとのことである。
よく知られているように、賢治は当時労農党を物心両面でかなり援助していたから、その頃の賢治も同様官憲等からかなりマークされていたと考えられる。ましてその「大演習」の初日は花巻で行われたためであろう、賢治周縁の人達の中にも盛岡刑務所入れられたり、所払いにされて函館に奔ったりしている人がいたのだからなおさらにである。したがって、賢治の羅須地人協会からの撤退に、このときの「アカ狩り」が無関係だったとは私にはどうしても思えない…。
そこでまずは、「種蒔く人」の運動発祥の地が秋田土崎であり、そこの出身の小牧近江、金子洋文、今野賢三の同級生3人が大正10年2月に発刊したのが土崎版『種蒔く人』だったということと、秋田市立土崎図書館の2階には「種蒔く人」の資料展示室があるということ知ったので、今回の秋田行となった次第だったのである。
なお、金田一京助(長男、盛岡中学明治43 34年卒)、次郎吉(次男)、安三(三男)、平井直衛(四男、同明治45年卒)、金田一他人(五男、同大正3年卒)、六郎(六男)、荒木田家寿(七男、同大正9年卒)は皆実の兄弟(男は7人兄弟、女は四姉妹)であり、金田一他人と賢治は盛中の同級生である。この他人は抜群に優秀な生徒であったと伝わっている。
《1 図書館前の「種蒔く人」のレリーフ》(平成25年11月28日撮影)

《2 〃 説明版》(平成25年11月28日撮影)

《3 同図書館》(平成25年11月28日撮影)

さて、同じ頃羅須地人協会から撤退して実家に戻った賢治は、この「種蒔く人」の運動についてはどの辺まで知っていたのだろうか。
《4 なお、同図書館は「JR土崎駅」のすぐ近くにある》(平成25年11月28日撮影)

<「JR土崎駅」構内設置の周辺地図より抜粋>
続きの
 ”「種蒔く人」とその運動(#1)”へ移る。
”「種蒔く人」とその運動(#1)”へ移る。
次の
 ”「アカ狩り」と口実”へ移る。
”「アカ狩り」と口実”へ移る。
前の
 ”『啄木とロシア』より”に戻る。
”『啄木とロシア』より”に戻る。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

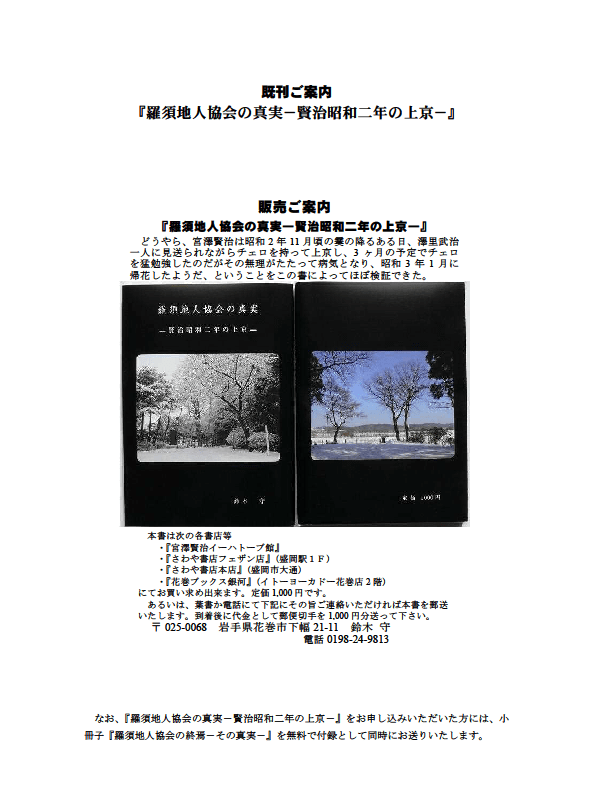
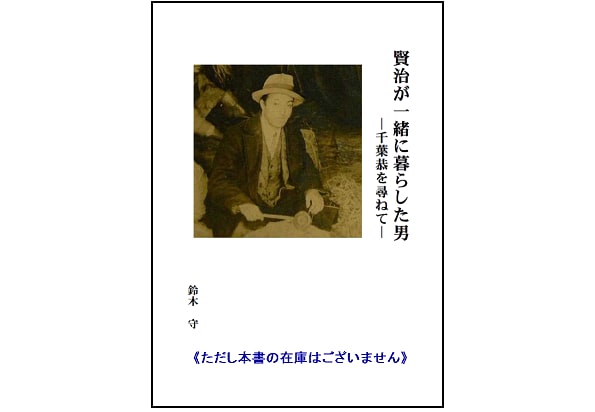
《創られた賢治から愛すべき賢治に》
この11月28日、秋田の土崎まで行って来た。というのは、あの「種蒔く人」運動発祥の地が秋田の土崎だったからだ。そこの出身の小牧近江等が大正10年2月に発刊したのが土崎版『種蒔く人』だったということを知り、先ずはこの目でその地を見てみたいと思ったのであった。ところで、宮澤賢治は昭和3年8月10日に、我が身を削るようなそれまでの献身的な活動により(気候不順による稲作の不良を心痛し、風雨の中を徹宵東奔西走し)遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、帰宅して父母のもとに病臥したと一般には言われている。
一方同じ頃、岩手県では同年秋10月の「陸軍特別大演習」を前にして凄まじい「アカ狩り」が行われ、例えば、盛岡中学の英語教師平井直衛は昭和3年8月にその「アカ狩り」によって盛岡中学を首になったが、直衛の弟荒木田家寿が言うところによれば、その理由はせいぜい例の『種蒔く人』を初めて盛岡に持ち込んだ程度の理由であろうことが窺える、ということだったとのことである。
よく知られているように、賢治は当時労農党を物心両面でかなり援助していたから、その頃の賢治も同様官憲等からかなりマークされていたと考えられる。ましてその「大演習」の初日は花巻で行われたためであろう、賢治周縁の人達の中にも盛岡刑務所入れられたり、所払いにされて函館に奔ったりしている人がいたのだからなおさらにである。したがって、賢治の羅須地人協会からの撤退に、このときの「アカ狩り」が無関係だったとは私にはどうしても思えない…。
そこでまずは、「種蒔く人」の運動発祥の地が秋田土崎であり、そこの出身の小牧近江、金子洋文、今野賢三の同級生3人が大正10年2月に発刊したのが土崎版『種蒔く人』だったということと、秋田市立土崎図書館の2階には「種蒔く人」の資料展示室があるということ知ったので、今回の秋田行となった次第だったのである。
なお、金田一京助(長男、盛岡中学明治
《1 図書館前の「種蒔く人」のレリーフ》(平成25年11月28日撮影)

《2 〃 説明版》(平成25年11月28日撮影)

《3 同図書館》(平成25年11月28日撮影)

さて、同じ頃羅須地人協会から撤退して実家に戻った賢治は、この「種蒔く人」の運動についてはどの辺まで知っていたのだろうか。
《4 なお、同図書館は「JR土崎駅」のすぐ近くにある》(平成25年11月28日撮影)

<「JR土崎駅」構内設置の周辺地図より抜粋>
続きの
 ”「種蒔く人」とその運動(#1)”へ移る。
”「種蒔く人」とその運動(#1)”へ移る。次の
 ”「アカ狩り」と口実”へ移る。
”「アカ狩り」と口実”へ移る。前の
 ”『啄木とロシア』より”に戻る。
”『啄木とロシア』より”に戻る。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。

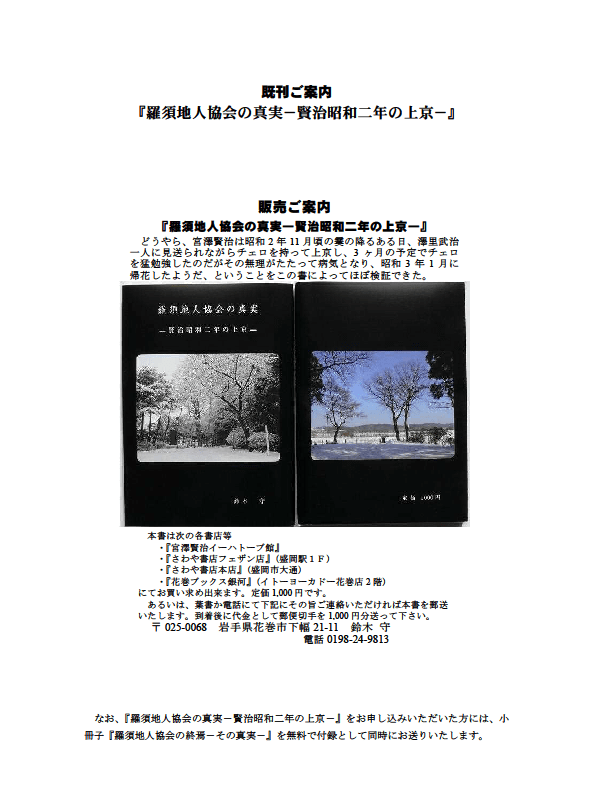
『賢治が一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』
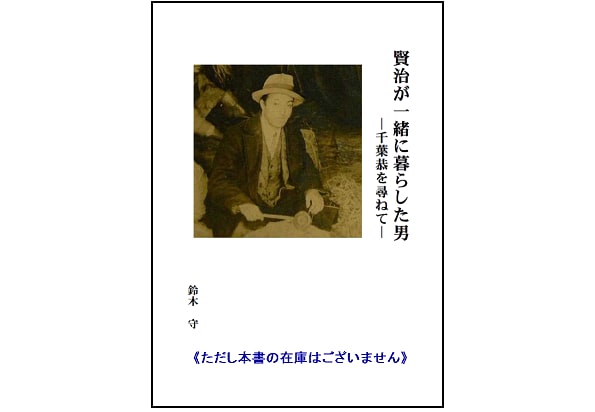




















先日はどうも。小生何時になく興奮して語り過ぎてしまいました。他者との語らいにあれほど気が入ったのは十何年びりなのかな、と。興味関心を共にする他者との語らいは時間を忘れさせてしまいます。
『種を蒔く人』という名は、先ずもって、フランスバルビゾン派の画家、J・F・ミレー(漱石が愛した『オフィ―リア』などで知られる英、ラファエル前派のJ・E・ミレイとは別)の作品として有名です。V・ゴッホが何枚かの模写を描いている筈です。メタファーとしては、「育苗する人」でも「収穫する人」でもない、といことですよね。賢治の自己観はどのあたりに。大正デモクラットは〈種〉だったんでしょうか、それとも〈芽〉?いずれにせよ、自前の息吹は踏み潰されてた、のだけれど、根は残って、と。武者小路実篤や高村光太郎、谷川徹三などなど、……。小生の父はその辺から感化を受けたようです。
『種を播く人』は岩波書店のシンボルマークですが、昭和2年の文庫創刊時くらいかと思っていたんですが、昭和8年からなんですね。ともかくも、小生は、賢治の「藤村操との同期にして漱石山房の人」なる岩波茂雄への関心は見過ごせないと考えてきました。『雨二モマケズ』のすぐ後に、『厳頭の感』を思わせる詞が。
金田一京助の盛中卒業はM43ではなくM34。直衛の入学はM40ですから、長岡拡が未だ在任中で、『岩手公園』にあるようなタピング一家を招いた英語授業を受けた可能性がある最後の盛中生ですね。賢治は長岡が去ったあとの入学生。長岡輝子さんはそのことを強調していました。直衛の他に、M40卒で後に盛中で賢治に英語を教えた内田秋皎やその親友の小野清一郎(島地大等の内弟子・刑法学者)は長岡の深い薫陶を受けた人ですね。金田一他人(たびと)の一高進学後はどうなったか調べがついてますか。
因みに、〈百姓〉という語、本来は〈ひゃくせい〉と読んで「無姓の庶民」の意だったんですね。『論語』『老子』『書経』などでの〈百姓〉はその意。『書経』の「百姓昭明、万邦協和。」から二字を採った名が何にもちられたか、賢治が深く考えこんだんではなかろうか、などと……。「本統の」という形容、〈本統の幸福〉とも。賢治の語用(プラグマ)法、そう〈単簡〉には取り扱えないのでは、と。
今晩は。
先日は大変お世話になりました。
そうでしたね、「金田一京助の盛中卒業はM43ではなくM34」、ありがとうございました。考えてみれば、「M43」であれば「平井直衛(四男、同明治45年卒)」と勘定が合わなくなってしまうのはすぐ判るはずでしたが、粗忽でした。
それから、お伝えしたいこともありますのでこれ以外のことにつきましては後程お電話いたします。