以下は前の記事からの続きです。
≪ナレーション≫
2011年、博士は理系の研究所を閉じました。ミクロの世界での生命の研究を止め、文系の教授になったのです。少年時代に心を躍らせた生命、機械とは異なる生命の本質を探究し、理系も文系も分け隔てなく伝えようとしています。博士のキーワードは動的平衡です。
≪福岡先生の話≫
シェーンハイマーのコンセプトは、日本語では動的平衡というふうに呼んだらいいと思うんですが、動的というのは常に動いているということであり、平衡というのはバランスという意味です。絶え間ない流れの中でいつも合成と分解がバランスをとっているというのが我々の身体の一番大切な特性です。そして常に動的平衡が成り立っているから、私たちの身体は何かがなくても、他のものがピンチヒッターになってやってきたり、平衡を作り替えることが出来る。それはGP2がなくてもですね、ナイなりにそれを補えるような仕組みで生物は新しいバランスを作り直していくわけなんです。
註:2016年にノーベル賞を受賞した大隅良典さんの「オートファジー(Autophagy)」を思い出してください。例えば外からのたんぱく質の補給が足らなくなったとき、細胞が自らの細胞質成分を食べて分解し、アミノ酸を得るとのこと。「自ら(Auto)」を「食べる(Phagy)」という意味とのこと。
≪ナレーション≫
生物学者や大隅義典教授を始め、21世紀に入ると生命が分解される仕組みがわかってきました。
分解、即ち自己自身を壊す仕組みです。でもどうして生命は自分を壊す必要があるのか?
(これについての話は、話が長くなるので省略させてもらいました)
さらに、人間が生命を機械と捉えると怖いことが起きる、と博士は警告します。生命が連鎖する地球環境から人間がリベンジされた例があるそうです。狂牛病です。狂牛病とは牛の脳がスポンジ状になり、牛が異常行動を起こす病気です。1986年にイギリスで発生しました。原因は牛の餌でした。
≪福岡先生の話≫
牛の餌っていったい何ですか。牛は草食動物で牧場の草を長閑に食べているとみんな思うんですが、狂牛病に罹った牛のほとんどはミルクを出す乳牛でした。乳牛はミルクを搾り取られるから沢山の栄養を食べさせないといけない。しかしミルクより高い餌を与えていたんではミルクは安く作れませんから、出来るだけ安くて栄養価のあるものを食べさせていました。それは草ではなく、肉骨粉と呼ばれる飼料だったんです。肉骨粉というのは、実は他の家畜の死体、つまり草食動物である牛を肉食動物に人工的に変えていた。その方が経済効率がいいからです。
で、狂牛病というのは、羊のスクレイピー病という病気がその餌の中に入り込んで、それを食べた牛がたくさん病気(狂牛病)になったということがわかったんです。で、そうこうしていると、今度はですね、その牛を食べた人が狂牛病になってしまう・・・、ヤコブ病っていう名前がついていますけれども、いずれも人間が勝手な都合で生物の動的平衡を切断し、組み替えているせいでこういうことが起きてしまったわけです。
≪ナレーション≫
「生命は機械ではない」博士がいくら訴えても、なかなかどうして機械論的生命観は私たちにしっかり浸み込んでいるようです。こちらの絵は小さな子供が書いた人間です。
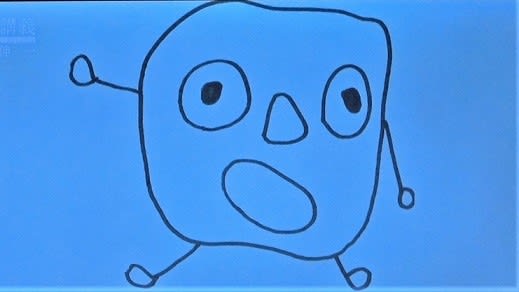
≪福岡先生の話≫
驚くべきことはたった4歳の子供でも、もう機械論的な生命観に染まってしまっているということなんです。つまり人間はパーツ(部品)から出来ているという風に、目、耳、鼻、口、手足から人間は出来ているというような・・・。でもこの考え方が間違っているのは次のような思考実験をしてみれば明らかです。
天才外科医がやって来て、AさんからBさんに鼻を移植しようと考えたとしましょう。Aさんからどういうように鼻を切り取れば、鼻という機能を取り外してBさんに移植できるか・・・。鼻というのは、実は鼻の穴の奥の天井には嗅覚上皮細胞というのがあって、そこで匂い物質を感知して、その信号をズ~と脳の奥に運んでいって・・・、だから、嗅覚っていう機能を鼻と考えると、結局身体全体を持ってこないと鼻という機能は取り出せないわけです。
≪ナレーション≫
食べ物が身体を造るのに、牛を肉食に替えたせいで牛の動的平衡がくずれました。バランスを失った牛を今度は人間が食べ、人間もバランスを崩しました。
≪福岡先生の話≫
つまり、動的平衡は一つの生命の中だけで起こっているのではなく、地球全体の生態系の中でも動的平衡は成り立っているのです。
≪ナレーション≫
さらにです。機械的生命観はいよいよ人間の生命そのものを揺るがしています。脳死の問題です。
博士の人生は今この生命哲学の問題との格闘です。
今回は以上です。
福岡教授の話は最後に「脳死問題」を取り上げられました。次回はその話ですが、お楽しみに。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
後記:「地球全体が動的バランスの上で成り立っている」という話は、お釈迦様の「山川草木国土悉皆成仏、有情非常同時成道」の言葉を思い出させるし、また詩人の「地球は生きている」という言葉を思い出させますが、いわゆる科学者からのこのような言葉を聞くと、いっそう訴えて来るものがある気がしました。
狂牛病の話も以前から宗教の世界で教えられていましたが、生物学教授からも聴けて心強く思ったことでした。

























