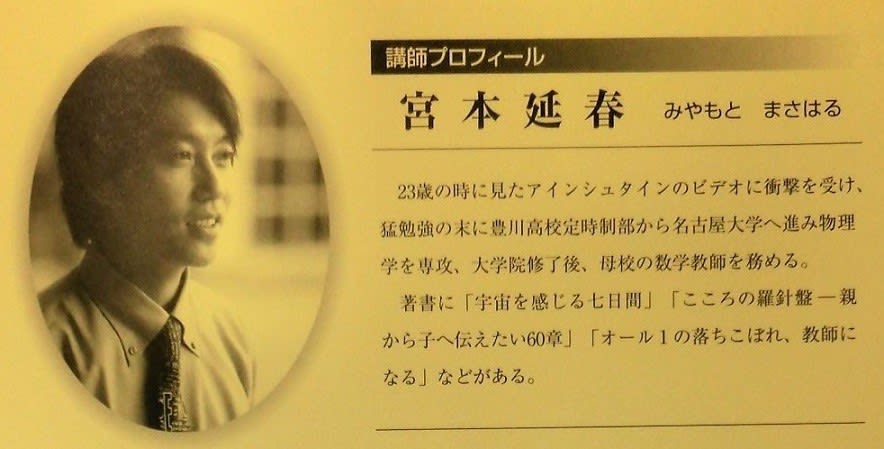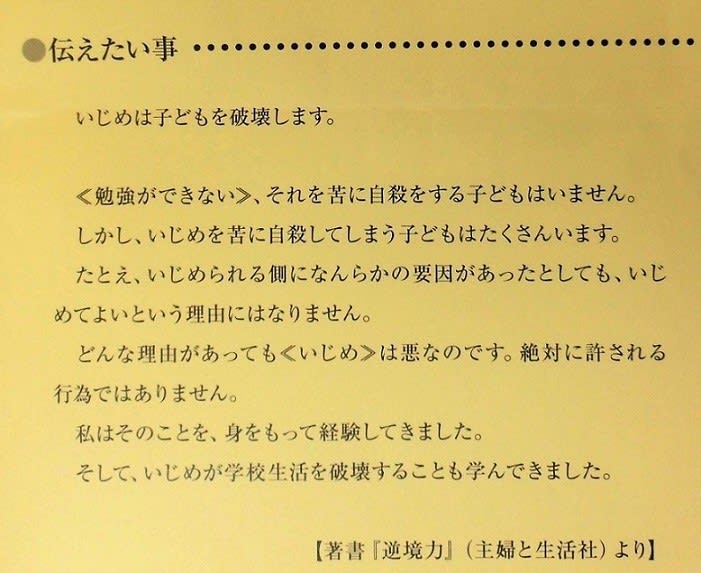以下は2年前の生長の家の月刊誌に紹介されている話ですが、先日初めて読んで大変感銘したので紹介させてもらいます。少し長いですが、最後まで読んでいただければ幸いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
花子(仮名)さんは10代の頃、両親の仲が悪く、暗く冷たい雰囲気の家庭から逃れたくて、中学1年の頃から不良仲間と付き合い始めたという。そして家出や非行を繰り返し、髪を染め、眼付もきつかったという。 (49歳になられる現在のお顔からは想像できないが)
中学を卒業した花子さんは、ブティックに就職し、8歳年上の男性と同棲するようになり、17歳のとき女の子を出産した。その、誕生したわが子の顔を見たとき、愛おしさで涙がこぼれ、この子には自分のような寂しい思いをさせたくないという思いでいっぱいになったという。
花子さんは出産を機に入籍し、19歳の時には次女を授かったが、その頃のご主人は転職を繰り返し、経済的に余裕がなかったので、花子さんは飲食店に働きに出るようになった。また、ご主人は家事に協力的でなく、子どもを邪見に扱ったりもするので、一緒にいたくないとの思いがつのり、ついに離婚したいとご主人に告げた。しかし、ご主人の方は「絶対に分かれない」と言い、もし分かれるなら子供は自分が引き取るとまでいうので、やむなく離婚は思いとどまった。
子供が成長して学校に通うようになると、花子さんは街で不良グループを見かけたり、子供の帰宅が遅かったりすると、わが子が、誰かに脅かされたり、悪い方に道を踏み外してはいないかと、不良に走ったかつての自分と重ね合わせて、心配になったという。そして、テレビ番組は悪い影響を与えると考え、10年間ほどテレビを置かず、代わりにクラッシック音楽を聞かせたり、絵本を読み聞かせたり、夜は決まった時間に家中の電気を消し就寝したとのこと。
しかし、長女も、次女もアレルギー体質で喘息やアトピー性皮膚炎を時々発症するので、体質改善について勉強し始め、自然食に興味を持つようになり、料理教室を開いている人と知り合いになり、その人から生長の家を紹介され、母親教室に通うようになった。それからやがて3人目の女の子が生まれた。
そんなある日、花子さんはご主人に言った。
「私は何も欲しいものはない。家族みんなの幸せがわたしの幸せ」と。
すると、ご主人は
「俺は幸せじゃない。お前は、一にも二にも三にも子供のことで、俺のことは何も考えとらん」と訴えた。
それから平成11年には4番目の子となる長男を授かったが、その年、ご主人の浮気が発覚し、生長の家の講師に相談した。
その講師は、
「大根の種子を蒔けば大根が生えるでしょう。環境は自分の心の影ですから、自分で蒔いた種が生えるんですよ。あなたはどんな種を蒔きましたか?」と言われたという。それで、これからはご主人に「はい」の心になり、ご主人を立てるよう心掛けることにした。
ところが一方のご主人は、浮気相手とは別れたが、今度はパチンコで数百万円も借金していたことが判明した。それが中古住宅を購入したばかりの頃で、家のローンとご主人の借金の支払いとで家計はひっ迫し、そこへもって五人目の二男を授かり、実家からは「育てられるのか」と心配されたという。
それから10年が過ぎたが、その間にもご主人は花子さんに内緒で借金を重ねていて、相変わらずその返済に追われていたが、「自分が蒔い種が生える」と教えられて以来、その言葉を思い出し、自分を責め、自分がどう変わればいいのか、何もわからなくなっていたとのこと。
花子さんは言う。
「平成24年、夜逃げをするしかないと思えるぐらい、家計はどん底の状態にありました。三女は高3、長男は中1、二男はまだ小学5年生で、返済のつらさから逃げ出すため、飲食店のパートで懸命に働き、親からも援助を受けてきました。それでも限界でした」と。
そして、再びご主人と別れようと思ったが、立ち直って欲しいという思いもあり、最後のお願いだからと、生長の家の本部練成会の参加を勧めた。今まで何回勧めても良い返事は帰ってこなかったが、この時初めて素直に応じてくれたという。
そして、ご主人はこの練成会参加中の1週間、毎日電話をかけてきて、楽しそうに練成会のことを報告してくれたとのこと。その練成会を終えて帰宅したご主人は、見違えるように顔が輝き、自信にあふれていたそうで、その時、奥さんは、「私はこの人のこんなところが好きだったんだ」と惚れ直したそうだ。
そして、それまで父の営む運送会社で働いていたご主人は、心機一転して独立し、みずから運送業を始めた。借金の返済は今もつづいているが、昼夜を分かたず働いている主人を見ながら、私も頑張ろうと勇気づけられているとのこと。
5人の子供のうち、上の3人は独立し、長女は4人の子の母になっているとのこと。
長男は中2の時、不登校になったことがあり、花子さんは「自分の何がいけなかったのか」と悩んだそうだが、友達にその悩みを話すと、「子供は神の子で、必ず良くなるから、親は心配しなくて大丈夫よ」と言われて驚いたとのこと。花子さんは、それまで家族に問題が起きるたび、「自分が蒔いた種」と自分を責めてきたが、人間本来の善なることを信じ、そのままで素晴らしい神の子と観ることのほうが大切だと教えられ、「長男はそのままで素晴らしい神の子なんだ」と思い直したとき、肩の荷が下り、「必ず良くなる!」と信じつつ過ごしているうちに、みずから高校に進学したいと言いだし、建築士になる夢を描いてがんばっているそうだ。
このような話の後、花子さんは言う。
「10代の頃から両親に迷惑をかけ続けてきた私でしたが、父母への感謝を説く生長の家に触れてからは、両親に過去の過ちを何度か謝ってきました。両親は『今は一生懸命に生きているんだから、自分を恥じることはない』と温かく話してくれ、今ではこの両親に生まれて来られたことを感謝しています」と語っている。
この素晴らしい花子さんは、ご主人が独立したころから生長の家の教化部でパートで働くようになり、平成28年から正職員として採用されたとのことです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、『神との対話』では、人生で過ちを繰り返してきたという著者のニール・ドナルド・ウォルシュに対して神はこう言っています。とても好きなところなので紹介させてもらいます。
〇いいかね。あなたには価値がある。誰にでも価値があるように。
価値がないというのは、人類に浴びせられた最悪の非難だ。
あなたは過去をもとに自分の価値を決めるが、わたしは未来をもとにあなたの価値を決める。
未来、未来、つねに未来だ!人生、生命は未来にあるのであって、過去にはない。
未来にこそ真実があるのであって、過去にはない。
これまでしてきたことは、これからすることに比べれば重要ではない。
これまで犯してきた過ちは、これから創造するものに比べれば何の意味もない。
あなたの過ちを赦そう。間違った意見も、見当違いの理解も、有害な行動も、自分勝手な決定も赦そう。
すべてを赦そう。他の人は赦してくれなくても、わたしは赦す。
他の人は罪悪感から解放してくれなくても、わたしは解放する。
過去を忘れて前進し、新しい何かになることを誰も認めてくれなくても、わたしは認める。
あなたは過去のあなたではなく、いつも、いつまでも新しいあなただと知っているから。
罪人は一瞬にして聖人になる。1秒で。1息で。ほんとうのところ、「罪人」などいない。
誰も罪を犯すことなどできない。ましてわたしに対してはあり得ない。
だから、あなたを「赦す」というのだよ。あなたにわかる言葉を使っているのだ。
ほんとうはあなたを赦すのではない。これからも赦さなければならないことなど何もない。
だが、あなたを解放することはできる。だから、いま解放しよう。今。再び。
おおぜいの他の教えを通じて、過去に何度も解放してきたように。
最後まで読んでいただき有難うございました。