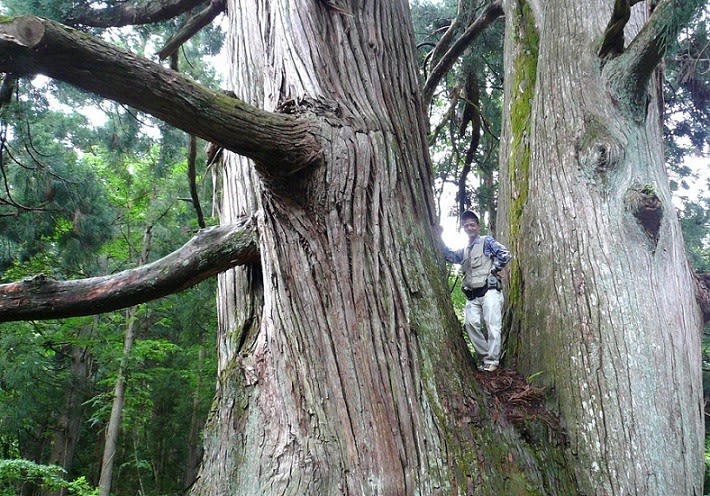NHK「歴史秘話ヒストリア」、副題「日本人ペリーと闘う 165年前の日米初交渉」を見ました。
日本が鎖国から転じて開港した件について、今まで武力を背景にしたペリーの恫喝に屈して開港した、というのが一般的な理解と思うが、この番組では、日本側もこの日の来るのを予期し、そのためのできるかぎりの準備もし、残された日米交渉の記録をたどりつつ、幕府も武力衝突とならない程度によく交渉し、健闘していることを紹介していました。
これは日本人にとってうれしい話でしたが、もう一つそれとは別の嬉しい話がありました。
それは、ペリー艦隊に水や食料を寄付した浦賀在住の一人の漁師がいたというのでした。
大きな黒船を目の前に見て、ただ驚くいているばかりの日本人を想像していましたが、なんと一人の漁師が水と食料を寄付したというのですから、実に素晴らしいと思いました。そして、船で使っていた鉄の大鍋がペリーから御礼としてその漁師にプレゼントされたとのこと。その大鍋がテレビで紹介されていました。
多くの外国人が日本見聞記の中で、「日本人は人懐っこく、いつもにこにこしている」という様な意味合いのことを書いているらしいが、ここでも、その敵意をもたない人懐っこい一面が現れているように思う。
また、横浜で幕府側と交渉していた当時、ペリー自らが農家(名主)に遊びに出かけたらしく、その時、名主の妻や妹からお菓子や酒のもてなしを受けたようで、その時の日本女性の印象についてペリーはこう記しているとのこと。
○若い娘は、姿良く美しく、その振舞いは活発である。また女性は周りから大切に扱われ、本人も自覚し、品位を保っている・・・・と。
ときどき、日本の国柄の一つとして、「男尊女卑」「封建的遺物」ということが言われますが、わたしはそういう一面があることは認めますが、必ずしもそうではないと思っていて、このペリー提督の見聞記もそのことを証明している気がします。「男尊女卑」は明治から云われるようになったと聞いていますが、私が尊敬する勝海舟も、山岡鉄舟も「男尊女卑」という見方に対して、本の中で「それは正しい見方ではない」と反論していたのを思い出します。それは言わば、人々の注目を浴びやすい野球のピッチャーと、それを陰で支えるキャッチャーの様なもので、それを男尊女卑とみるかどうかは、人それぞれの解釈ではないかと思います。
ところで、番組の中のこれらのエピソードを「へえ~!」という気持ちで見ていて、思い出したことがありました。
それは今から17年前、私が53歳の時、自宅を火事で焼き、火災保険は入ってなくて銀行のローンで、すぐ新築しました。それから3年後、わたしは以前から、「船の仕事を辞めたい」と思っていましたが、そのせいか、ある面白くないことがあって、本当にやめたくなりました。しかし、生長の家の教えでは、「嫌なことや辛いことがあっても、その嫌なこと辛いことはあなたを磨くために起きて来るのだから、そこから逃げてはいけない。あなたがその事を卒業しない限りは、たとえ逃げても、環境は心の影だからまた同様なことが起きてくると」いう様に教えられています。
そんなわけで、逃げてはいけないと思っても、自分が辞めたいと思っているせいか、心の奥から「お前は会社をやめたいと思っているくせに、経済的に心配だから辞めることもできず、このまま会社にしがみついていくつもりか。それでは男として情けないだろう」という囁きがきこえてくるのでした。
それで、辞めるべきか、辞めざるべきか、ずいぶん悩みましたが、最後は「迷っていても仕方がない、何とかなるはずだ」と、思い切って辞める決意をし、家内にそのことを話しました。家内は突然の話に心配そうでしたが、反対もせず、「お父さんがそうしたいなら・・・」と承諾してくれました。
この様に、家内も了解してくれたことが、自分にとってどんなに救いだったか。もし、「辛いだろうけど、何とか頑張って」などといわれていたら、ずいぶん苦しい立場になっただろうと思います。そして今更ながら、その時のことを有難く思うのです。
そして、このあとはこちらが就活もしないのに、祈りがきかれ、驚いたことに或る会社から「是非わが社に来て欲しい」という電話をいただき、そこに再就職しました。
その会社は横浜にある日本一の客船桟橋をホームポートにする会社で、近くに「山下公園」、「港の見える丘公園」があり、辞めるには惜しくもありましたが、3年勤めた後、60歳になったのを機に、その会社も退職しました。この時も、家内としてはまだ働いて欲しかったはずですが、何も言わず、「いいよ」と言ってくれたので、本当に助かりました。
それからもう一つ、現役を退いた後、女性と接する機会も多くなり、家内から「女の人を敵に回すと怖いよ」と度々脅かされ、いや、教えられ、できるだけ女性を敵に回さないよう心掛けている次第です。(笑)
ま、それはともかく、言いたかったのは、男尊女卑というよりも、男は女に支えられているということでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。