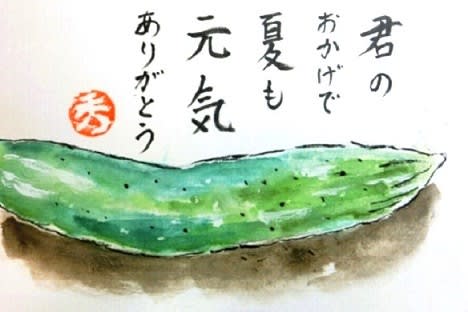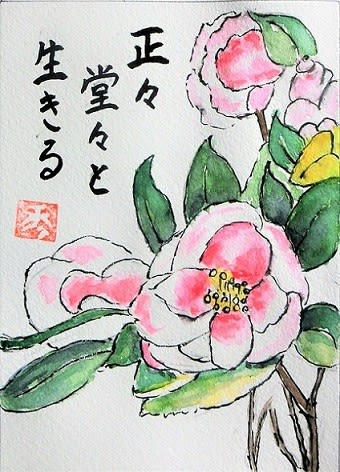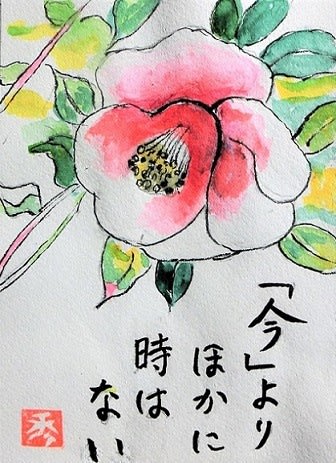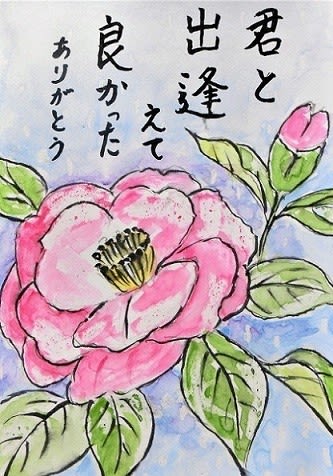昨日、テレビの番組欄を見ていて、BSⅠの「スピリチュアル・ジャパン」という放送があるのを見つけたので、録画して見ました。昨日は節分にちなんだ「鬼」をテーマにしたものと、「雪」をテーマにした、それぞれ30分の2回の放送でした。
その内容は、日本にいる若い外国人男女の二人が、外国人の立場から日本人は「鬼」を、あるいは「雪」をどのようにとらえているかを現地取材しながら日本人のスピリチュアルな面を探求していくという、そんな番組で興味あるものでした。
「鬼」については東北地方の取材で、恐ろしく忌み嫌うべきものというイメージではなく、親しみをもって捉えられていることや、さらにはその家の守護をしてくれる守り神として祭られている地域もあり、守り神というそんなとらえ方まであることが紹介されていました。(外国にも鬼がいるそうだが、怖いものとしてとらえられているらしい)
そして、何故豆なのかと質問した時、あるお寺の坊さんが「豆(マメ)」は「魔滅(マメツ)」の意であると答えていて、「あ、なるほど~!」と思った事でした。
そして道行く人に「あなたにとっての鬼とはどんなものですか?」というような質問を数人にしていたが、全員が「鬼は外にいるのではなく、自分の内に住む魔」という意味で答えていました。
このように誰でも自分の内に魔(鬼)がいると思うのですが、この魔とどう向き合っていくか、ある意味では、対人関係以上に難しいかもしれませんね。親鸞聖人のような人でさえ「煩悩具足の凡夫」とか、「心は蛇蝎の如く」と嘆いていられるし、西洋ではあのパウロも同じように嘆いているとのこと。
しかし、こんなふうに嘆いている親鸞やパウロが何故民衆に説教などしたのだろうか。
この人たちは、その内に住む魔を嘆いてばかりいたのではなく、「魔」のさらなる奥には「聖なるもの」があることをはっきりと見抜いていたのではないだろうか。
親鸞上人は「善人なおもて往生す。増して悪人をや」と説いているし、
イエス・キリストも「幸福なるかな、悲しむ者。その人は慰められん」と教えている。
もう一つのテーマ「雪」の方も、その取材地は雪国、即ち東北でしたが、こちらは「かまくら」が紹介されていました。沢山の小さい「かまくら」にはロウソクが灯され、とても幻想的でしたし、大きな「かまくら」では子供たちがその「かまくら」の主(あるじ)となり、訪れる客たちに「中に入ったんせ」と声をかけ、餅を焼き、甘酒や焼いた餅をふるまったりしていて、まるでおとぎ話を見るようでした。
子供の頃、正月に遊ぶカルタには「かまくら」の絵があり、「かまくら」の中に入ってみたいと憧れたものでしたが、そんな取材をしながら、雪国の人たちは、雪を恐れるのではなく、雪と調和した生活を営み、雪を神聖なものとしてとらえられていることが紹介されていました。
こんな番組を見ていたら、「雪の結晶」に関する好きな文章を読みたくなり、抜き書きしていたものから検索したところ、次の4つが掛かってきたので掲載します。
○雪のひとひら以上に完璧なものを見たことがあるだろうか?その精妙さ、デザイン、対称性、一つ一つが雪の結晶としてあるべき姿を保ちながら、同時に個性的でもある。まさに神秘的ではないか。あなたがたは、この自然の驚くべき奇跡に驚異の念をいだくだろう。雪の結晶についてこれだけのことができるわたしなら、宇宙についてどれほどのことができると、あるいはできたと思うか?
○いいかな、わたしはすべての花であり、虹であり、空の星であり、すべての星をめぐるすべての惑星上のすべてだ。わたしは風のささやきであり、太陽の温かさであり、それぞれが信じられないほど個性的で、しかもこの上なく完璧な雪の結晶のひとつひとつだ。
○なぜ、同じ雪の結晶が2つないのか?それは、不可能だからだ。「創造」は「コピー」ではないし、2つとして同じ雪の結晶はないし、同じ人間はいないし、同じ考えはないし、同じ関係もないし、同じものが2つ存在することは絶対にない。宇宙は――そしてその中のすべては――単数でしか存在しないし、同じものは他にはないのだ。
以上はニール・ドナルド・ウオルシュ著『神との対話』1~3巻より
○あなたは雪の結晶だ。生命を表現するために完璧な、この世に二つとない個性をもって、神の世界から舞い降りてきた。地上に着くと、あなたと同じように息をのむほど美しい個性をもつほかの者たちと一緒になって、より大きなスケールで美しい景色をつくりだす。やがてあなたは形を変え、一つに溶けあい、小川をさらさらと流れていく。そして、天へと昇っていき、消えてしまう。(あなたはそこにいるが、ただもう目には見えないのだ)あなたはこうして、来たところへ帰り、再びサイクルが始まる。雪の結晶の旅は、魂の旅の完璧なたとえだ。 ニール・ドナルド・ウオルシュ著『10代のための「神との対話」』より