「新人賞「辣油の花」、准賞「けふの用」は、ともに俳句的表現を獲得しているものの、そのぶん既視感が多くみられ、言葉がまだ言葉としてのみふわんと浮いている頼りなさがある。この「俳句的既視感」はたとえば<水槽に簡単な陸うららけし>(「辣油の花」)のように「簡単な」と印象を付与して「うららけし」と気候の季語で雰囲気をまとめたり、<階段の裏錆びきつて鳳仙花><くろぐろと濡れて朝の焚火跡>(「けふの用」)のように錆びや跡に着目したりする、発想の定型化にある。こういう句は誰かがもう作っている。それを型の継承として是とする考え方もあろうが、それは俳句の平凡化と表裏一体でもある。
(中略)
俳句は型を身につければいくらでも書けてしまうからこそ、なぜ今わたしがそれを詠むのか、作者の哲学が欲しい。質量や体温をもって世界と切り結ぶ言葉を求めたい。
以上は、『石田波郷俳句大会 第13回作品集』(2021年12月)の「新人賞 選者選評」における神野紗希の評である。読んでわかる通り、今年度の石田波郷新人賞の根木波輝「辣油の花」、準賞の佐々木啄実「けふの用」に対し、手厳しい評価を下している。たとえ受賞作であったとしても、そこに「作者の哲学」があるかどうか。賞の持つ評価以上に、この選評は俳句そのものを考える際に重要な示唆に富んでいる。
そうして今年度の各種賞の受賞作・候補作を読み返したとき、最も「作者の哲学」を感じたのは、角川俳句賞の候補作品となった牛島火宅「殯」だった。「殯」は獄中や刑場をテーマに詠まれた特異な作品であり、選考座談会でも受賞・次席の是非を巡る議論が白熱していた。以下、引用はすべて『俳句11月号』(角川文化振興財団、2021年10月)による。
主文死刑以下は野分の被告かな 牛島火宅
一と日生きのびて一夜の銀河濃し 同
「秋と逝く」のみ書き遺す自裁あり 同
死囚徒の自死をうべなふ鉦叩 同
澄む眼ゆゑ頭巾でおほふ処刑まへ 同
出獄の刑屍にかざす秋日傘 同
秋風や浄めて備ふ絞刑具 同
死を強ひる罰ある獄の聖誕祭 同
たましひを神に嘔吐す聖夜ミサ 同
作品に主に登場するのは死刑囚と刑務官。「一と日」などの句は死刑囚の日常を、「澄む眼ゆゑ」などの句は刑務官の日常を詠んでいるように思う。死刑囚は社会的に見れば善悪の悪の立場に立つ。しかし、永山則夫など、獄中で罪を心から悔いる者もいる。そして、刑務官はその死刑囚たちと長い時間を過ごすことになる。だからこそ、社会的に死刑囚が持つイメージと真逆のイメージを見ることもあるのだろう。「澄む眼」をした死刑囚や、罪を犯した己の「たましひ」を「神に嘔吐す」るように激しく打ち明ける死刑囚。そこには一人の人間としての死刑囚があるばかりだ。そのうえで己の世界・生を振り返るとき、そこにはまた別の視点が生まれてくる。作者の世界が色濃く反映されており、「殯」の読後には、映画を一本観たあとのような充足感が残った。
しかし、「言葉があまりにも大袈裟で、比喩が多くて、鳥とか虫を擬人化している。そういう言葉の遣い方が僕は積極的に採らないという理由です」という仁平勝の言や、「あまりにも由々しい言葉が多出しているのがとても気になりました。この方がこう詠むということ自体は尊いことだと思うのですが、それを角川俳句賞として推す立場で読むとき、こんな由々しい言葉を多用していいのかと疑問を持ちます」といった正木ゆう子の言のように、句の表現は確かにオーバーなものが多い。それは確かにこの作品の持つ傷と言える。しかし、死刑囚と刑務官との日常の連続における感情は、表現を抑えて詠んだ場合には失われてしまう気もしてならない。それこそ、「質量や体温をもって世界と切り結ぶ言葉」が崩れてしまう気もしなくはないのだ。
「近年、角川俳句賞の作品は作者性が薄まって透明に近くなっていく印象があります。そのなかで、この作品は強烈に作者性というものを押し出してくる。歴代の受賞作品の中でも非常にユニークなものではないか」と小澤實は述べている。最終的に受賞にも次席にも至ることこそなかったものの、この作品がまた別の世界を切り開くのではないかということを密かに願いつつ、私も作句に励みたい。











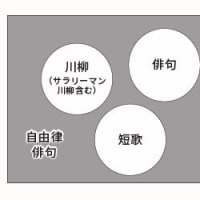


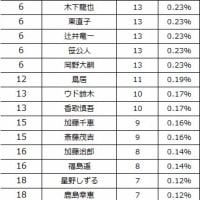
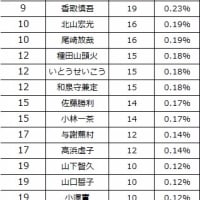
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます