引き続き、酒卷英一郞氏の三行作品を読み進めたい。読みの方針は、前々回、および前回記事と同様である。「出会い損ねる」という、詩との出会い方を、受け入れつつ、しかし抗ってみること。
なお、酒卷氏の作品において、表記は一貫して正書法が用いられているが、文字コードやフォントの都合上、表示しえないものは、それぞれ新字体に改めた。
胡麻和えは汝に
黑胡麻汚しは
そちへかな
『LOTUS』第6号(2006年)「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXII」より。この人を食ったような、とぼけたような「作風」を眼前にするとき、「ああ、酒卷作品を読んでいるなあ」という「実感」に襲われる。もちろん「実感」などというものは、「実感」という印象を伴った知覚のひとつに過ぎないのだから、騙されてはならないだろう。
コンスタティヴな「句意」は見たままだが、ひとまずパラフレーズするなら「胡麻和えはあなたに。黒胡麻汚しはそちらのあなたに」となるだろうか(《汝》の自称としての用法は、古代においてあったようだが、ここではそこまで穿った読み方をする必要はないと思う)。本作を読むさい、重要なポイントと考えられるのは、本作の背後に(下に、でも、上に、でもよいのだが)いかに間テクスト的な・テクスト参照的な重層性(深さ、とか、重み、とか呼んでもよいかもしれない)があろうとも、なによりもまず「強い句意」が、ある明瞭さの印象を伴って、読みの領域に勃勃と立ち上がる点だ。これを無視することはできない。《汝》と《そち》、《胡麻和え》と《胡麻汚し》はそれぞれ同義であり、つまり文字面を変えつつ、二度、同じことを述べていることになる(だから「人を食ったような、とぼけたような」と述べたのだ)。対称(二人称)を二度使うことは、語り手の眼前に二人の人物がいると仮定すれば、不自然な点はまったくない。
パフォーマティヴな句意はどうか。面白いのは、一行目と、二・三行目の印象が、まるで異なる、という点だろう。この印象の違いは、並べて配置する、アレンジメントの効果である。「胡麻和えは汝に」という文も「黒胡麻汚しはそちへ」という文も、それぞれ単独では、本作の与えてくる印象を備えることがない。このアレンジメントにおいて、《和え》・《汚し》の対称的な語が、まずはこの違いをもたらしている。二行目の《黑胡麻》は、反照して、一行目の《胡麻》を白胡麻としてイメージさせることだろう。
近年、「黒」を悪しきものの象徴として用いることに対し、ポリティカル・コレクトネスの観点から異議が唱えられているが(「ブラック企業」等の言い回し)、我々の知覚の構造によるものか、知覚の構造を維持しようとする保守的慣行によるものか、《汚し》の語の効果もあいまって、二つの行為は、「青眼を向けられる者への行為」と「白眼視される者への行為」という正反対の印象を備えることになってしまう。句意の、コンスタティヴ/パフォーマティヴの差異の、乖離。ここにおいて、本作は、明らかに散種のテクスチャを湛えており、詩がある。注意すべきは、詩は、コンスタティヴな句意から、あるいはパフォーマティヴな句意から発生しているのではなく、あくまでも「違い」から発生している、という点である。
なみおみの
なんぢきやりこの
からしうす
『LOTUS』第7号(2006年)「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXIII」より。ひらがなに開かれた作品も、酒卷作品に多く見られる特徴のひとつである。かなに開かれた作品は、仮に視覚を用いて読むのであれば、視点の引っかかりを失っており、外形・輪郭からじっくりと、形状を知覚し、最終的に一字一句について知覚する、というプロセスを経させるものといえるだろう。このとき紛れ込むのが、いわば「表記的マラプロピズム(誤用語法)」ないし「表記的タイポグリセミア」である。タイポグリセミアは文章の表記について生じる認知上の現象であるから、「表記的」というのもおかしな言い方ではあるが。タイポグリセミアとは、たとえば「こんちには みさなん おんげき ですか」という文(単語の文字の順番が、「正しい」ものとは異なっている)を目にしたとき、誤記(typo)があっても文意を推測できてしまう(場合によっては誤りに気づかない)現象である(文例は久保田・藤川・鈴木、2023、「タイポグリセミアを用いたMulti-model CAPTCHAの提案と評価」『産業応用工学会論文誌』vol.11, no.1より)。しかしながら、本作を読む体験において生じているのは、マラプロピズムでもタイポグリセミアでもなく、かつどちらでもある、という奇妙な事態であるように思われる。
本作の、一行目《なみおみの》を、まず私は「おなもみの」と空目してしまった。おそらく酒卷氏であれば旧仮名遣いで「をなもみの」と書くだろうと推測できるにもかかわらず、である。俳句作品を読むという文脈に拘束されており、なおかつ《なみおみ》という語に親しみがないからだ。次いで、三行目《からしうす》を私は「からすうり」と空目してしまった。理由は同前。そうなると、二行目は何に空目させようとしているのだろうと、奇妙な詮索への、奇妙な誘惑にもかられる。「なんじゃもんじゃ」だろうか。いや、「空目させようとしている」というのは勝手な決めつけであって、こうした誘惑は倒錯的なものだが。空目、つまり別の語に見間違える、という事態は、マラプロピズムの機序に似ているが、アナグラム的に文字を入れ替えることで空目する、という事態は、タイポグリセミアの機序に似ている。
ひとまず、本作のコンスタティヴな「句意」をパラフレーズしておこう。「水死したあなたは、三色斑(calico)の鮒(Carassius)(つまり金魚)であることよ」となるだろうか。《なみおみ》つまり「波臣」は、「はしん」と音読みで読むことが通例(?)であるようだが(人名においては宰相花波臣〔さいしょうかなみおみ〕、氏族名においては高志之利波臣〔こしのとなみのおみ〕と訓読みする例がある)、水中に君臣関係を投影して、魚類のこと、転じて水死者を意味するようだ。《きやりこ》つまり「キャリコ」は三色斑の模様のことで、とくに金魚について言う(「キャリコ 金魚」のフレーズで画像検索されたし)。《からしうす》つまり「Carassius」はフナ属の学名。
弔句とも読める。また、水死者と金魚を重ね合わせることは、エズラ・パウンドが荒木田守武の発句に見出した重置法(super-position)が採用されている、とも読める。しかし、もしそれだけなら、三行目は「きんぎよかな」であってもよかったはずだ……いや、そもそもひらがなに開かれる必要もなかったはずだ……などとも思わせる。《なみおみ》を「おなもみ」と空目したのは私の粗忽によるものに過ぎないかもしれず、「作者の意図」は《からしうす》の語によって無関係の「芥子」「臼」のイメージを立ち上げさせる点にあるのかもしれない。ポイントは、読者は必ず空目するわけではないし、必ず単語の音から無関係のイメージを立ち上げるわけではない、という点だ。ここに、酒卷氏の「賭け」を見出さざるをえない。
夢よりの
根深を抽くや
夢のあと
『LOTUS』第8号(2007年)「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXV」より。一読して、永田耕衣の《夢の世に葱を作りて寂しさよ》、および芭蕉の《夏草や兵どもが夢の跡》との間テクスト関係・テクスト参照関係に気づく。《根深》は長葱のことだろう。《あと》を「後」と読めば(まずは、そう読める)「夢から育ってきた長葱を、夢から覚めたいま、抽いてみる」となるだろうか。この第一の印象、第一の読み自体、奇想と言えて、面白みがある。耕衣句の《夢の世》が、「夢のように儚い此の世」とも、じっさいに語り手が睡眠中に見ている「夢の中」とも読めるのに対して、この読みにおいては「夢とうつつ」が区別され、かつ、《根深》がその区別を越境している。否、《抽く》という行為が越境しているのかもしれない。詩嚢としての《夢》から、詩のエッセンスを抽出しようとしている、と読めば、詩人の営みを詠んでいるとも読める。いまの世はもはや(耕衣の時代と違って)《夢のあと》である、と読むなら、現代・現在の俳句への批評にもなるだろう。
俳句批評のラインでの読みを促すのは、芭蕉句を想定するからでもある。つまり《あと》を「跡」と読む可能性、である。芭蕉句の《兵どもが夢》は、藤原三代、もしくは義経主従の《兵ども》が功名の《夢》を見た、と読む説と、語り手の《夢》のなかに義経たちが現れた、と読む説とがあるらしいのだが、いずれにしても《夏草》の土地が、《跡》であろう。本作に反照させれば、文学の夢、文学に対して抱かれていた《夢》が、いまとなっては《あと》(跡形)である(あるいは「跡形」もないのだろうか)、とも読める。とはいえ、「諦念」「嘆き」と読んでしまうことには、違和感が残る。本作で語り手は《抽く》行為をしているからだ。抽いた結果、どうであったかは、語られないにしても。
私なりの、少々つっこんだ読みを試みるなら、《夢》とは(山本健吉が耕衣句に対して読んだように)「夢のように儚い此の世」であり、《夢のあと》とは死後である、とも読めるかもしれない。違うかもしれない。書かれてあることからは、いずれとも判断はできない。このとき、ここにあるのが「夢とうつつ」の区別であるのか、「生前と死後」の区別であるのか、不定となる。この不定性において、私は本作を読みたい。
なはおびを
しぼればこたふ
あきのこゑ
『LOTUS』第9号(2007年)「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXVI」より。再び、ひらがなに開かれた作品。「縄帯を絞れば応ふ秋の声」と、「開かれ」を元に戻してみるなら、まずはコンスタティヴな「句意」が分かる。現代では縄帯は、洒落た、気軽な帯として用いられている。井原西鶴は『諸艶大鑑(好色二代男)』において、吝嗇そうな登場人物を《油屋の手代らしい、二十四五位の男が上がつて來たが、見ると柿染の布地の着物に繩帶を締め、縹色の木綿犢鼻褌が見え透いてゐるばかりか、懐の塵紙さへ汚らしくほの見えてゐる》(吉井勇現代語訳)と描いており、あまり「洒落た」感じはなかったのかもしれない。事典のたぐいには、はじめ遊女やあぶれ者が用い、のちに一般にも広まった、との記述もあり、時代によってニュアンスは異なるのだろう。ともあれ、着物の縄帯をキュッと絞ってみれば、キュッと応える、それが秋の声である――といったような、気風がいい東男のこざっぱりとした、小粋な一場面を描いた、まこと気持ちの良い作品である、ともなろう。なるほどクールジャパン。
これをかなに開くことで、そうは読めなくなってしまう点が面白い。「まこと気持ちの良い」句意をもたせるだけならば、かなに開く必要はないのだから。もちろん三行表記の効果もあるだろう。縄帯は、かつては村八分の制裁に用いられるなど、残酷な含意が籠った物件である(茜頭巾なども同様に用いられた)。目に見えるスティグマとして、マークとして用いられたのだ。これを前提とすれば、本作品がほのめかしている事態(昨今の流行語でいえば「匂わせ」)も、言わずもがな、となる。ギュッとやれば、ギャッと応える。虐待の場面か、殺害の場面か、一度のことなのか、反復性のあることなのか、それは書かれていない。けれども、共同体の悪性を、つまびらかに描いている作品であろうと思う。本作が傑出しているのは「開かれを元に戻し」たときの句意(コンスタティヴな句意)と、かなに開かれ、三行表記された際のほのめかし(パフォーマティヴな句意)とが、異なる、関連のない意味になるのではなく、表裏一体の、単一の現象を二つの角度から描いたものとして分岐するからである。この「単一の現象」を、ナショナリズムだとかエスノセントリズムだとか呼ぶことも可能ではあるにしても、人類が目下のりあげている暗礁は、文明の起源、「人間」がその名を負うことになった起源に関わっていることのように思われる。アドルノが『プリズメン』第一論文において提示したかの有名なテーゼは、「文化批判」からすでに「文明批判」へと一歩逸脱している(踏み込んでいる)と読むことも可能なのだ。
(つづく)











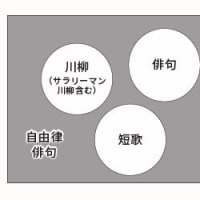


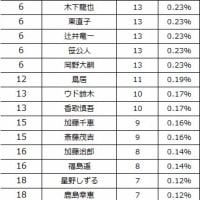
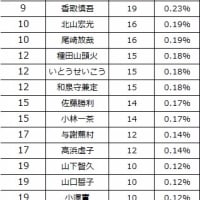
「なみおみ」句の、まず初めにくるべき「コンスタティヴな句意」としては、
「魚類であるあなた(金魚)は、三色斑の鮒だよ」
というものかもしれませんね。気になったので、付記まで。