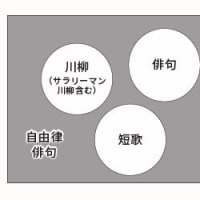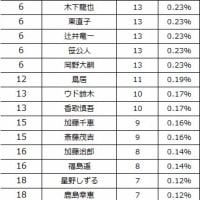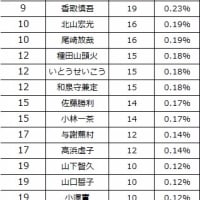この「出会い損ねる詩」と題された多行俳句時評は全四回の依頼で、今回が最終回である。第一回から、酒卷英一郞作品を読んできた。今回もそうだ。初回は『LOTUS』創刊号掲載の連作「阿哆喇句祠亞」シリーズの14作目から始まった。今回は同じく「阿哆喇句祠亞」シリーズの27作目から30作目まで、かいつまんで読む。なんとも中途半端なところから始まり、中途半端なところで終わってしまう。この中途半端な感触、宙吊りの感触、もっと読むことができればよいのにと思いながらも象の一部を撫でて終わってしまうもどかしさこそ、「詩と出会い損ねる」という、この一連の稿で私が提示しようとした、「詩に向き合う態度」そのものであるから、もしもこの感触が読者に伝わっているなら、ひとまず私の試みは這々の体ながらも成功したと言えるのではないか。
出会い損ねると言いながらも、謎解きをして、一定の読解を提示してきたではないか、それで終りではないにしても、詩を読むとは、それで十分ではないか――とご批判を受けるかもしれない。しかしまあ、この連載で取り上げた作品は、恣意的なピックアップの結果であるし、「何か言うことができそう」と思ったものを拾い上げたというだけである。いまでも半分以上の酒卷俳句は、私には手も足も出ない。そうしたことも、多くの読者にはすでにバレバレであろうけれども……。
いま、私の脳裏には、数名の俳人の名が思い浮かんでいる。まず、大岡頌司。大岡の作品は、安井浩司の作品に似ている。もちろんこれは倒錯した感じ方であって、安井の作品が大岡頌司の作品に似ていると述べた方が適切な場合もあろうし、あるいはたんに一定の言語領域を共有した二人の俳人がいた、と述べる方が適切なのだろう。次に、木村リュウジ。酒卷氏に私淑していた木村リュウジの作品は、大岡作品と酒卷作品に似ている。このことは当人も認めていたところである。ところが不思議なことに、酒卷作品は、大岡作品にも木村作品にも似ていない。安井浩司の影響が、影が、見出されないと言えば嘘になるが、同じ語彙を用いていても酒卷作品においては異なるテクスチャ――酒卷語、としかいいようのない独特の肌理――を湛えることになる。あえて挙げれば、私にはむしろ加藤郁乎の作品に向き合うときの感触が、酒卷作品において少なからず蘇ってくるように感じられるのだ。見た目のうえではまるで異なるにしても。これは、つねに書き換えられるべき、私の個人的な脳内地図の記述に過ぎないから、読者諸賢の役に立つものではないかもしれない。
ダラダラと私情を述べてしまった。最終回をさっそくはじめよう。なお、酒卷氏の作品において、表記は一貫して正書法が用いられているが、文字コードやフォントの都合上、表示しえないものは、それぞれ新字体に改めた。
入らずんば
ここが鼠穴か
言の葉の
『LOTUS』第10号(2008年)「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXⅦ」より。謎めいていると同時におかしみがある。《入らずんば》ということは、入らないのであろうか、それとも「虎子を得ず」の慣用句に従い、入るべきだと考えているのだろうか。しかし虎穴ではない。《鼠穴》である。入ってみたところで、得られるのはせいぜい「鼠子」であって虎子ではないだろう。それでも誘引力の強い《穴》である。この段階では、三通りの含意があるかもしれない。(1)豊潤な《言の葉》の内側へ入ってみたところで、我々にはせいぜい鼠子しか得られない(「我々にはせいぜい鼠」に力点)。(2)魅力的に見える《言の葉》の内側にはたかだか鼠子がいるだけである(「言語にはたかだか鼠」に力点)。(3)入らないことによって《穴》は在り続け、魅力的にも、あるいはつまらないものにも見えるアンビバレントなものであり続ける。
少し深読みしよう。《鼠穴》の元ネタは落語の演目「鼠穴(ねずみあな)」ではないか。あらすじはWikipediaの同項目の通りだが、本作にとってのポイントは二つ。(1)蔵の鼠穴を塞ぐのを怠ったために火がつき、主人公は全財産を失ってしまう。(2)このことは、あまりに鼠穴を気にしていたために見た夢であったこと。この深読みにおいてもまた、感触はアンビバレントなものとなる。《鼠穴》は塞がれるべきなのか――《言の葉》を守るために。はたまた、一挙に転覆するためのチャンスが訪れているのか。私はとうぜんながら後者、言語破壊を志すものであるのだが、きっと言語とは、暗殺しようと背後から近づくと、いつのまにか私の背後に回っている、自分の影のようなものに違いない。そしてまた、その穴は、気にしすぎるがゆえに自らを苦しめるものであり、夢のなかにしか現れないものでもある。穴に入ってしまえば、穴は消えるのだろう。それは《言の葉》と抜き差しならない関係を保とうとする詩人――言語をメディウムとする場合の詩人――にとっては、不可能なことだとも言える。
余談を付け加えておこう。本連作の一つ前の句は《元朝も/はやも寢濃しの/寢棲みなる》、一つ後の句は《鼠鳴きの/不寢權現の/夜の物》となっている。前者は「寝濃い(寝坊)」と「寝越し(寝だめ)」の地口、「寝住む(ずっと一緒に暮らす)」と「鼠」の地口、と読める。後者は「鼠鳴(鼠が鳴く)」と花柳界用語としての「鼠啼(客を呼ぶなど、多義的)」の地口、「根津」の地名の由来の諸説(「不寝権現(寝ずに神々の番をする神)」「鼠」など)に含まれる地口、「夜の物」の多義性(「夜着、夜具」と「鼠」)、と読める。いわば「鼠三昧」である。酒卷作品とツェラン――などと口走ることは、我田引水に過ぎるかもしれない。先に「酒卷語」と述べた。「酒卷語」に湛えられる感触=「鼠啼」の感触と、ツェランの「チューチュー語り(Mauscheln)」に湛えられている感触とが、同じものであるはずはないにせよ、分有されるなにがしかが、そこにあるように感じられるのも事実である。
ツェランが「チューチュー語り」と述べたのは、かの散文作品「山中での対話」(一九六〇年)における、ツェラン自身とアドルノとの、架空の、実現しなかった出会いと対話についてである。よく知られるように、ツェランとアドルノは、共通の知人ペーター・ソンディを介して、一九五九年、スイスのシルス・マリアで面会する予定になっていた。一般には、ツェランの急用によってこの初めての出会いは延期されたのであるが、ヨアヒム・ゼングや細見和之のツェラン論においては、むしろツェランがあえて回避したとされる――七月、ツェランはアドルノ夫妻より一週間はやくシルス・マリアを離れ、八月に「山中での対話」を書き上げる。まさにそのために、実際の面会を回避した、というわけだ。
二人のユダヤ人は翌一九六〇年一月に初めて出会うのであるが、以降の二人のやり取り(『アドルノ/ツェラン往復書簡1960-1968』ヨアヒム・ゼング編、細見和之訳)から察せられるように、ツェランの求める「ユダヤ人であること」の呼びかけに対して、アドルノは十分に応答できないという、「すれ違い」に終始している。裏切られた、とツェランが感じていたかどうかは分からないが、やり取りは決してツェランを元気づけるものではなかったと思われる。付言するなら、ツェランはシオニズムにもアンビバレントな反応を示しており、生涯イスラエルを訪問したのは一度きりだった。ツェランの言う(求めた)「チューチュー語り(Mauscheln)」とは何か。《ドイツ語のMauschelnは、Mausネズミ(二十日鼠)から来た言葉で、Mauschelといえば侮蔑的に「ユダヤ人」を指す名詞であり、動詞のmauschelnは「イディッシュ訛りで話すこと」を指している。もちろん、侮蔑的な響きがそこにはある。チューチュー鳴いているネズミのようにわけのわからない言葉を話している連中、ということだ。そういうイディッシュ訛りでのアドルノと自分の対話こそがあの作品〔「山中での対話」〕なのだ、とツェランは自ら語っていた》(細見和之「アドルノとツェラン――両者の往復書簡を手がかりとして」前掲『往復書簡』訳書所収)。
ツェランが「ユダヤ人であること」を他者に求め、裏切られ、傷ついたように、酒卷氏は作品を通じて読者になにがしかの共有を求めている、とは言えない。少なくとも私の目にはそう見えない――これもまた、たんに私が「読めていない」からに過ぎないかもしれないが。酒卷作品とツェラン、という我田引水的な結びつけは、投瓶通信的なもの、という一つの共通項においてしか成り立たないかもしれない。しかしながら、その圧縮された言葉、極端な「訛り」、隔世遺伝的な語り(鼠啼)は、私の指先において、似たテクスチャを与えてくるのは、たしかなのである。
寂寞の
三つ四つから
初烏
『LOTUS』第11号(2008年)所収の連作「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXⅧ」から。一読、きわめてシンプルに書かれている。《三つ四つ》とは時刻かもしれないが(そしてそれを含意しつつ)、おそらく『枕草子』の冒頭を元ネタとしているのであろう。『枕草子』の諸本間には異同がきわめて多いが、現代よく読まれているいわゆる「三巻本」を底本とした、岩波文庫版から引用しておく。《秋は夕暮。夕日のさして山のはいとちかうなりたるに、からすのねどころへ行くとて、みつよつ、ふたつみつなどとびいそぐさへあはれなり》。夕暮れに、塒へ帰るために烏が「三つ四つ、二つ三つ」とどんどん少なくなってゆく、という。清少納言が「あはれ(寂しい・哀しい)」と述べた景を、《寂寞》という俳言に丸め込んだ点が、掲句の新しみかもしれない。
ここで、おや、と思わせるのは、一つには新年季語を用いながらも正月らしくない(めでたい感じがない)ということもあるが、ここでの《初烏》は夕暮れの景なのだろうか、という謎である。《三つ四つ》を時刻かもしれないと述べたけれども、一日を十二等分する十二支式の表現法だと、「三つ」は存在しない(九つから四つまで)。「丑三つ時」というように、一つの刻を四等分するときの《三つ》かもしれないけれど、このときは、「どの三つ」なのか分からない。つまり時刻と読んでも、時間帯を知るには役に立たないわけである。『枕草子』元ネタ説からするならば、夕暮れなのだが、夕方まで《初烏》が登場しなかったというのも考えにくい。この謎に答えはないのだが、朝の景だとするなら、《寂寞》のなかから少しずつ《初烏》が現れ、しだいに「やかましい!」と怒鳴りたくなるほど賑やかになる、と読めるし、暮れの景だとするなら、《寂寞》が《初烏》と共に増殖してゆく、なんともめでたくない、正月らしからぬ事態となるであろう。
また余談になるのだが、現代ではきわめて有名な『枕草子』も、刊行されて三百年は文学史の外へ追いやられていたことを思うと、趣深い。三百年後の兼好法師が『徒然草』において(『源氏物語』と並列させて)言及したことにより、『枕草子』が初めて拾い上げられることになるわけだけれど、この『徒然草』自体が、広く読まれるようになるにはさらに三百年以上経過した江戸時代になってからであったこともまた、趣深い。兼好法師は歌人として著名だったから、『徒然草』はまず歌人のあいだで知られるようになる。しかしこれも、没後七十年経過してのことだった。江戸時代の歌人・俳人であった北村季吟が『徒然草文段抄』を記し、その七年後『枕草子春曙抄』を記した。『枕草子』も『徒然草』も広く読まれるようになったのは、それ以後のことである。島内裕子によるちくま学芸文庫版『枕草子』は『春曙抄』を底本とした、現在では珍しいものだが、島内によれば《昭和二十年代頃までは、「枕草子を読む」とは、基本的に、北村季吟の『春曙抄』を読むことであった》のである。島内は同書「はじめに」において蕪村の「春風のつまかへしたり春曙抄」を引用している。《春風が女性の着物の褄(つま)をふわりと優しく吹き返した、と詠み掛けて、実は『春曙抄』の冊子の端(つま)を春風がそっと吹き返した》というわけである。と、余談を続けてみて、おそらく、ここでの酒卷作品も、季吟を経由させた『枕草子』への参照を行っているのではないか、と思われてくる。
木が觸れて
鳥不止の
木に觸はる
『LOTUS』第12号(2008年)所収の連作「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXⅪ」(「XXⅨ」の誤植だろうか)から。一読して、一行目は「気が触れて」、三行目は「気に障る」と掛けられていることが分かる。《鳥不止》(とりとまらず)は多義的である。コトバンクの「精選版日本語大辞典」を引くと、五つの植物の「異名」とされている。これらのうちのどれかに決定する必要もないのだが、漢方薬においては「メギ科のメギ」とされているから(酒卷作品には漢方薬の名称が頻出する)、ここでは目木のことと読んでも差し支えないのではないか。目によいから目木。枝の鋭い棘が、いかにも「気が触れて」「気に障る」という質感を湛えているから、なおさらだ。
本作の面白さは、《木》と「気」を2×2のグリッドに配置したときに現れる、四つの系列の読み、すなわち「木‐木」「木‐気」「気‐木」「気‐気」の読みが、渾然としてくる点にある。書かれてある文字面は「木‐木」のみを示しているのだが、素直にそう読めるようには書かれていない――その読みを拒絶するわけではないにせよ。かといって、どのように読むべきなのか、この四つの系列のどれを選択すると腑に落ちる結果になるのか、これもまた結論づけることはできない。あえて言えば「気が触れて(頭がおかしくなったから)目木の木に触った(棘に触れると痛い、ということにも考えが及ばずに)」というストーリーは筋が通っているかもしれない。筋は通っているけれども、そのようにのみ読む読者は、いそうにない。決定不能な、それぞれに排他的な四つの意味の系列が、同時に到来する、その感触に、詩が宿っている。
鹿茸が蟲
今朝の冬
『LOTUS』第13号(2009年)所収の連作「阿哆喇句祠亞 αταραξία XXX」から。《鹿茸》(ろくじょう)とはシカの袋角。滋養強壮の生薬とされる。『日本書紀』「巻第二十二」の推古天皇の段に《十九年の夏五月の五日に、菟田野に薬猟す》(岩波文庫版『日本書紀(四)』)とあり、「薬猟」の注釈によれば《鹿の若角(袋角)をとる猟。鹿茸といい、かげ乾しにして補精強壮剤にした。後世変じて薬草を採ることとなる》とある。気になるのは《腦喰む》と《蟲》であるが、これは『徒然草』が元ネタである。第一四九段を全文引用する。《鹿茸を鼻に当てて嗅ぐべからず。小さき虫ありて、鼻より入りて、脳を食むと言へり》(角川ソフィア文庫版)。事実ではないだろうが、かつてそのような言い伝えがあったのだろうか。
それにしても『徒然草』という書物も謎に満ちた代物で、日本三大随筆の一つといえども、一段丸々このような「べからずのメモ書き」のようなものを、随筆と呼んでよいものか、悩ましいところがある。むろん「随筆」というジャンルによる分類は近世~近代によるものであって、当時、ジャンル意識はなかった。兼好法師という人物についても謎が多く、家系図をはじめ、多くの人物像が没後捏造されたものである(詳しくは小川剛生『兼好法師』を参照――これもまた余談であるけれども)。かの語義未詳の「しろうるり」が登場するのは六十段で、人の容姿の形容として言われるのだが、《さる物を我も知らず》というのだから、ほとんど落語の構想メモのように思われてくる。そう言えば、大岡頌司にも木村リュウジにも「しろうるり」を詠んだ作品があった。酒卷作品にあったかどうか……覚えていない。
本作には謎といえるほどの謎はない。あえて挙げれば「薬狩り」も「袋角」も夏の季語であるのに、三行目で一挙に立冬に移行するのは何故か、という点だろうか。しかしこれも、鹿・茸・虫、と秋の季語を二行目に配置し、改行によって季節を移行させる、という超絶技巧に気づくことができれば、それでよいのではないだろうか。
(了)