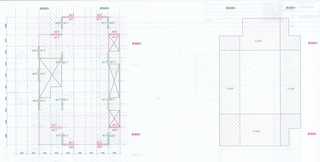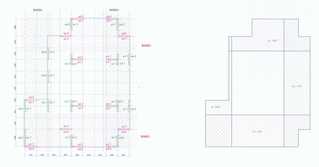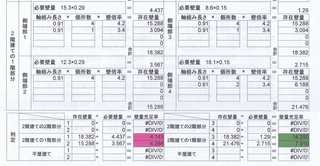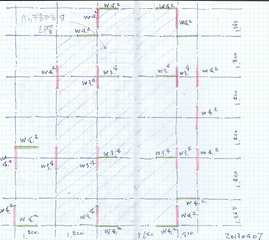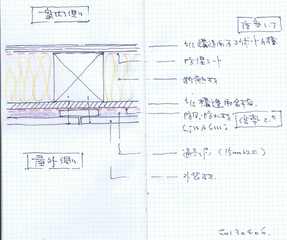吹抜け部分を削除して、
壁量充足率を算出してみる。
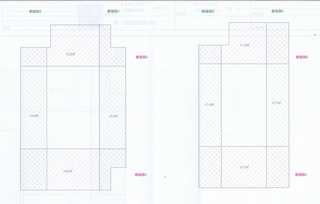
20130428-1
左側が吹抜けがある状態の四分割。
右側は吹抜けを除いて四分割した。
当然の事だが・・・側端部3,4の幅が狭くなった。
加えて、外壁に在ったX方向の耐力壁が、2箇所カウントできなくなった。
これで充足率は、かなり下がるはず!

20130428-2
判定欄を見ると、2階の側端部1,2の充足率が1/3程度になった。
充足率が1以上あるので、基準法的にはOKだが、配慮したほうがよい。
壁量充足率を算出してみる。
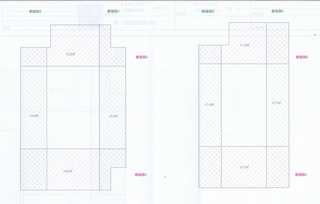
20130428-1
左側が吹抜けがある状態の四分割。
右側は吹抜けを除いて四分割した。
当然の事だが・・・側端部3,4の幅が狭くなった。
加えて、外壁に在ったX方向の耐力壁が、2箇所カウントできなくなった。
これで充足率は、かなり下がるはず!

20130428-2
判定欄を見ると、2階の側端部1,2の充足率が1/3程度になった。
充足率が1以上あるので、基準法的にはOKだが、配慮したほうがよい。