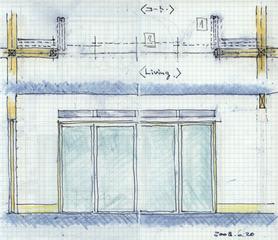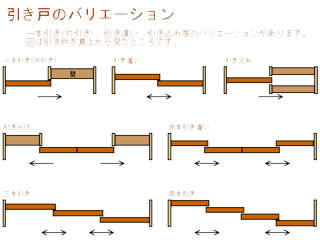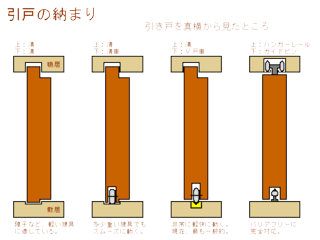メンテナンスは・・・何事にも必要。
住宅のメンテナンスは、
費用もかかって大変だが、
管理者責任と思って・・・?
軽い汚れなら、消しゴムでこすったり、
水洗いで良さそうだ。
カビが生えたり、濃いめの汚れがついたら、
塩素系漂白剤を水で薄めて、
布で拭き取る。
この時・・・酸性洗剤は使わないこと!
漆喰の原材である水酸化カルシュウムは
アルカリ性だから。
漆喰の上から塗装するときは、
選択する塗料に注意!
関西ペイント「アレスシックス」
日本ペイント「ケンエース」
これらは、良さそうだ。
漆喰壁の補修は、
・軽微な表面割れなら、上から漆喰の重ね塗り。
費用は3500円〜/平米
・下部の土壁にも割れが入った時は、
既存の漆喰を撤去し、
下地作りをした上で、漆喰の上塗りを施す。
費用は5000円〜/平米
費用対効果を熟慮し・・・
住宅を可愛がろう。
住宅のメンテナンスは、
費用もかかって大変だが、
管理者責任と思って・・・?
軽い汚れなら、消しゴムでこすったり、
水洗いで良さそうだ。
カビが生えたり、濃いめの汚れがついたら、
塩素系漂白剤を水で薄めて、
布で拭き取る。
この時・・・酸性洗剤は使わないこと!
漆喰の原材である水酸化カルシュウムは
アルカリ性だから。
漆喰の上から塗装するときは、
選択する塗料に注意!
関西ペイント「アレスシックス」
日本ペイント「ケンエース」
これらは、良さそうだ。
漆喰壁の補修は、
・軽微な表面割れなら、上から漆喰の重ね塗り。
費用は3500円〜/平米
・下部の土壁にも割れが入った時は、
既存の漆喰を撤去し、
下地作りをした上で、漆喰の上塗りを施す。
費用は5000円〜/平米
費用対効果を熟慮し・・・
住宅を可愛がろう。