前回、かなりお見苦しい画像で説明をしつつ紹介したアメリカの
デブ救済番組「エクストリーム・ウェイトロス」。
片づけられなくてどうしようもなく家が「汚部屋」「汚家」になってしまったところに
周りが手を差し伸べ強制的に全てを掃除してしまう「HORDERS」などとともに
野次馬として観ているものにはなんというか実に「爽快な」?
数十分の間に他人の人生が変わっていくのをビジュアルで観ることの面白さ、
そして「他人のこと」に好奇心を持たずにはいられないアメリカ人には大人気。
まあ、日本人だってたぶんそうですけど。
この夏一度ご紹介した「HORDERS」。
去年紹介したのが「HORADING」だったので、てっきり名前が変わったのだと思い
そのようにエントリでも書いたのですが、なんと、これ別の番組だったんですね。
同じような趣向の、同じようなタイトルの番組が同時進行で二つあるとは・・・・。
わたしがこの手の「ビフォーアフターもの」で好きなのが、
とんでもなくダサい一人の女性の前に、クリントンとステイシーという二人の
「ファッション救済人」がある日突然降臨し、「なんでも5000ドル買えるカード」を与えてくれ、
あれこれアドバイスしたうえ、プロの手によるヘアとメイクを施して、
あっという間に洗練された女性に変えるという番組、
WHAT NOT TO WEAR(こんなの着てはいけないわ)
や、あるいは通りの電話ボックスのようなガラスケースにターゲットを立たせ、
道行く人に「彼女(彼のこともあり)いくつに見える?」と聞いて酷評させ、その後
こちらはファッション、ヘア、歯の漂白、時にはボトックス注射までを駆使して若返らせ、
完成後にもう一度ガラスケースの中に入って10歳若返ったことを実験する、
10 YEARS YOUNGER(10歳若返る)
などなど。
このようなファッション変身ものにおいても、たとえば今までのスタイルを全否定されたり、
ガラスケースの自分に向かって野次馬が聞こえないと思って無茶苦茶言うのを後から聞いたり、
なによりもそんな自分がネイションワイドで知られてしまうことは、恥ずかしくないのか?
と思ってしまったりするわけですが、そこはアメリカ人。
日本人とは「恥ずかしい」のポイントがずいぶん違うようなのです。
もっとも「ジェリー・スプリンガー・ショー」で、恋人の浮気相手(ときにはそれが姉妹や娘だったり)
となぐり合ったり、「モーリー」で1ダースの男性全員にDNAテストをしてどれが父親か探したり、
こんなのに比べればまだまだ常識的には許容の範囲というものかもしれませんが。
さて、というわけで前回に引き続き、今回も一人の「救われたデブ」の物語をお送りします。

本日のデブ。
名前を忘れてしまったのでキャシーさんとしましょう。
ご覧のとおり、アメリカの主婦にしてはごくごく普通の、「中デブ」くらいのレヴェルの女性です。
一家の良き妻良き母で、家族からも愛され、明るいキャシーさん、
この過酷なダイエット道場にいきなり放り込まれても、取りあえずはうまくいきそうです。
この番組はビジュアルとして「激しいトレーニングをしている」というのが分かりやすいように、
シチュエーションを毎回変えています。
今回はなぜかいきなり国道沿いの砂浜。
クルマがブンブン通り、おそらく車の中からは「何やってんだあれ」
とみられることは必至の状況ですが、そんなことはいいのです。
砂浜を選択したのは、より運動負荷を与えるため、そして「海」です。
ゴムベルトで胴を抑えられ、前に進もうとするキャシーですが、後ろで押さえている
この番組専門の「デブ救済トレーナー」クリスが、がっちり押さえて離しません。
「ぐぬぬぬ・・・前に進まんっ!ぜいぜいぜいぜい」
「ふははは、貴様に脚力がないせいだ。わたしはこれこの通りびくともせぬわ!」
続いて番組お約束、スパーリング。
なぜか人は何かを無心に殴るときに心の中のわだかまりを吐き出すようです。
(この番組によると)
もし、黙ってバンバンミットを殴って「気持ちいい~~!」とすっきりしてしまうような人だったら
ディレクターはどのように指導して「トラウマ吐き出しの場」に持って行っているのか、
むしろこの制作陣に感心してしまうくらい、皆同じ行動をとります。
ミットを殴りながら、ディレクターの誘導により(多分)、キャシーさんは次第に
心の中に何かが溜まっていたことに気づき(笑)それを吐き出し始めます。
幼き日のキャシーさんとハンサムだった父親。
彼女の心に過るのはかつての幸せな日々。
そして、今は亡き父親の死が、彼女の心にトラウマを与え、
彼女はここまで太ってしまった・・・・・・・・・わけないだろっ!(笑)
全く・・・・。
太っている原因をこういう無理やりな原因になんでもしてしまうのは、
いくらドラマが必要と言っても大概にした方がいいと思うの。
ともかくも、ダイエットを成功させるには、特にキャシーさんのように毎日の楽に流され、
「ちょっとぐらいはいいわよね」みたいな気持ちで何も運動せずに食べてしまうような人の場合、
こういった「荒療治」が必要だ、ということのようです。
この人はほかのアメリカ人にありがちな家庭の問題をあまり持っていないので、
むしろ番組製作者はそんな面を引き出すのに苦労したのではないかと思われました。
ただ、先日アメリカの友人と話したところ、アメリカという国は見かけはともかく、
コミュニティに入ると、実に問題が多い国なのだそうです。
たとえば彼女にはうちの息子と同じ年代の娘がいるのですが、彼女のクラスメートは
たいていが親が離婚したり再婚したりしていて、そっちがふつうの状態。
わたしもサンフランシスコの幼稚園に息子を通わせていたとき、
親が離婚して今は父親と別居している男の子のこんなシーンを見ました。
その幼稚園は共同経営型の、親が週に一回幼稚園で安全監視をしたりスナックを用意したり、
つまり労働を提供する代わりに安価であるというもので、
その日は男の子の「本当のお父さん」が仕事に来ていました。
(まだ法的に離婚が成立していなかったのだと思われます)
男の子は母親と新しいその夫、つまりステップファーザー(継父)と一緒に住んでいますから、
幼稚園が終わったらその家に帰っていくわけですが、なんと息子を迎えに来たのが
継父だったわけです。
当然そんなことも予想されるとわかっていて継父をよこす母親も大概ですが。
すると男の子は「帰りたくない。(本当の)お父さんと一緒にいたい)」泣き出し、
どうしても継父の所に行こうとしません。
おそらく、たいしてこの子供に愛情を持っていないらしく、継父は男の子を困惑した、
しかし冷ややかな目で見ています。
まあ、こんな状況になると、継父も決して面白くないでしょうが。
そして、実の父(この人はお母さんが日本人だった)が継父に向かって
「ジェームスは帰りたくないといっているので、わたしが後で家に連れて行く」
と告げ、継父は黙って帰って行ったのでした。
たかだか3歳の子供をこんな目に合わせるこの大人たちにも呆れましたが、
この子が将来どんなトラウマを抱え、どう成長するのか、
他人事ながらわたしはこの様子を横で観ながら(彼らは人目をはばかるようなこともしない)
心を痛めていたものです。
そのほか、家のガレージで薬をやっていた新しい夫を叩きだし、
男に愛想を尽かした仲良しのお母さんが共同で住んで子育てしていたり、
明らかに子が養子(親が白人で子供が黒人)なのに親が離婚してしまったり、
「アメリカ社会って病んでるなあ」
と嘆息する噂話ばかりを聞いたものです。
日本人にも血縁に関する悩みや苦しみはもちろんありましょうが 、ここでは
たいていの人が何らかの親兄弟に関するトラウマを持っているのではないか、
とこういう番組作りを観ていても思われるのでした。
ですから、番組制作側としてもこのような被験者の「悩み苦しみ」をあげつらうのに
いわば何の工夫も努力も要らないわけです。
幸せそうに見える主婦のキャシーさんも、いろいろ辛いトレーニングをこなし、
体重が嘘のように減っていくにつれ精神も「浄化」を求めるのか、
やたら感傷的になり、トレーナーの一言に泣いたり笑ったり。
さて。以下の過程はすっとばして(写真が撮れなかったので)。
いよいよこの番組お約束、
「デブが急激にしぼんだときに余ってくる皮を手術で切る」
時がやってきました。
これは、ある程度脂肪が減って、切除しても大丈夫、というラインがあって、
まだ脂肪が詰まっている段階の皮膚を切ることは危険なため、
必ずここで医師の診察があります。
「ふむー。確かに痩せていますが・・・・・」
渋い顔の医師を心配そうに見るクリス。
「この程度では切除は無理です」
「がああああ~~~~ん」(キャシーさんがショックを受けた音)
実は診察の前、クリスの「手取り足取り」はしばしお休みで、キャシーの自助努力に任されており、
少しの期間、キャシーはトレーナーの目の届かないところで、
・・・・・・・・・少し安心して羽目を外したようです。
「いや、ここ余ってますよ。切れませんか?」
「切れませんな」
って医師はともかく、トレーナーまでキャシーのおなかをまるで肉屋の品定めのように・・・(T_T)
クリス「どおっすんだよお!手術できなくなるくらいリバウンドしてんじゃねーよ!」
「反省してます」

陰になり日向になってキャシーを支えてきた家族も暗い顔。
しかし、このスマートな娘さん、母親のこの騒ぎを他山の石としないと、
あなたは20年後に同じようなことになってしまうよ。
というか、キャシーさんも昔はこんなスマートな女性だったんですね(T_T)
「馬鹿!馬鹿!わたしの馬鹿!」
八つ当たりするキャシーさん。
そして心を入れ替え(何回入れ替えてるんだ)再びダイエットに励んだ結果、

番組の尺の関係上、いきなり再診察と手術はすっ飛ばして(笑)
場面は「ビフォーアフターお披露目」の会場に。
端折ってんじゃねー。
息子、夫、前からおばあちゃんと娘。
彼女の場合、この家族が大きな支えとなったのが成功の原因でした。
全くひやひやさせらたぜ!
と自分の苦労を交え、観客にキャシーの変身成功を告げるクリス。
内心イライラしていたと思うんですけどね。
必ず会場に到着する元デブは、黒塗りのリムジンから降り立つ足だけが映されます。
そして確認するように何度もフラッシュバックされるかつての姿。
グロ画像注意。ってもう見ちゃいましたね。
いくら変身前でも、これは、全国的に放映されるにはあまりに辛い画像ではある。
おなかの部分に見えるのは、もしかして脂肪の小さな塊?
これだけ太ると、脂肪がまんべんなく全身につくのではなく、一部に固まることもあるのでしょうか。
おおおお。
確かにウェストは太いが、取りあえずやせたキャシー登場。
やりました!
これもお約束、高々と手を挙げるクリス。
どうですか?今の気持ちは。
目を輝かせて妻の晴れ姿を見ていたと思ったら、夫は
涙をあふれさせ、眼を拭うのでした。
なんと美しい愛の姿。
しかし、この際夫ももう少しダイエットしたほうがいいと思うのはわたしだけであろうか。
さて、この番組では同じようにダイエット成功させる「グループ被験者」もおり、
この場で彼女らのビフォーアフターも紹介されました。


皆喝采を受けつつ晴れやかな顔で登場しますが・・・・・
必ずしも成功する人だけとは限りません。
このひとは何があったのか全くと言っていいほどやせられず、
でも出さないわけにはいかないのでこの場に登場し、さらし者になっていました。
出してやるなよ・・・・。
そして画面には何度も映し出されるかつての姿。
いくら変身前でもこれは(略)
そして何度も言うが、脂肪のブツブツが怖い。
彼女が減らした体重は65キロ。
成人男性まるまる一人分です。

顔つきまで変わったキャシーさん。
彼女を愛する家族が、今後彼女のリバウンドに対し、どの程度厳しくできるか、
実のところ非常に 不安を感じさせますが、取りあえずは大成功です。
めったにいないだけに、彼女のように家庭環境に問題のない被験者を見ると、
番組製作者が「お約束」で欲しがるトラウマなんぞより、この人の場合むしろ
「その幸せな家庭環境こそが太る原因だったのでは・・・・」とつい考えてしまいました。


































































































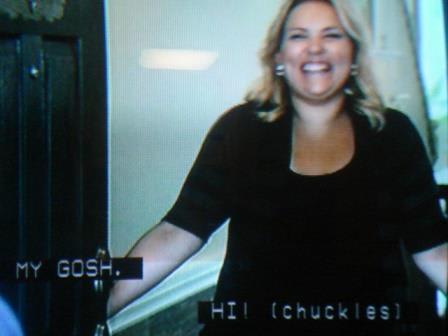
















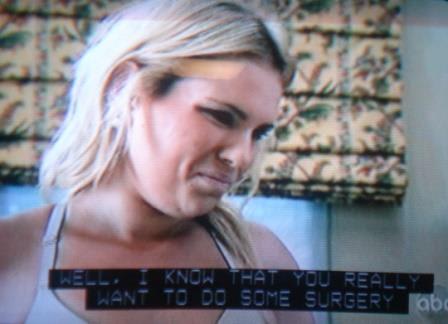

















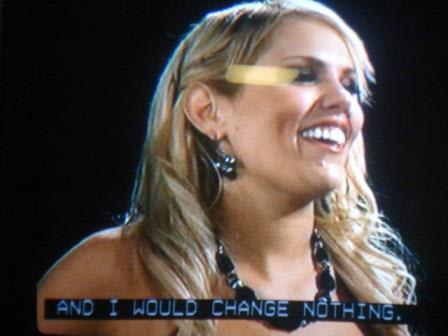


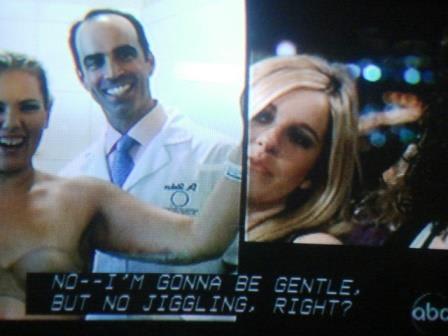




















































































































 あd
あd




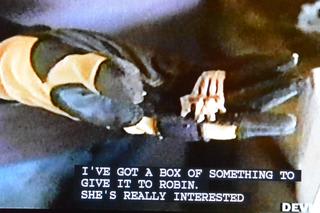
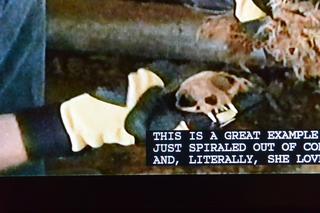












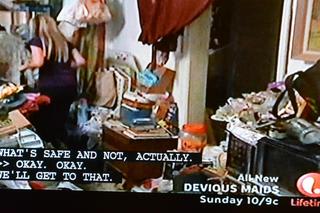
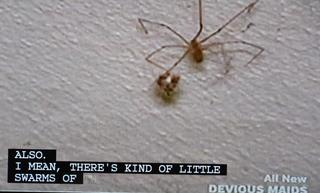












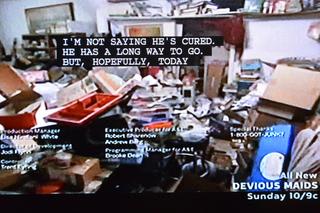






























































































 z
z z
z






























































































