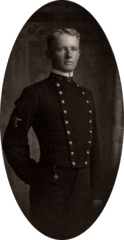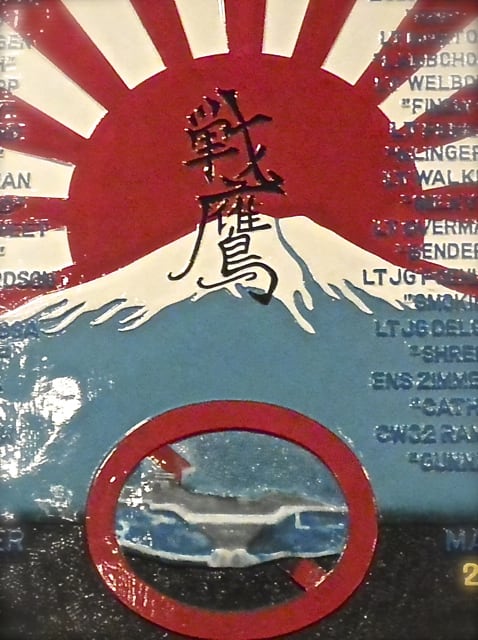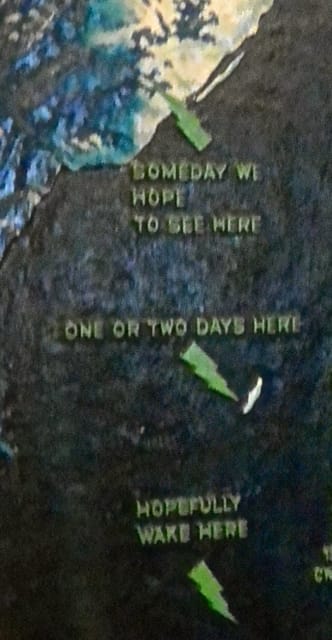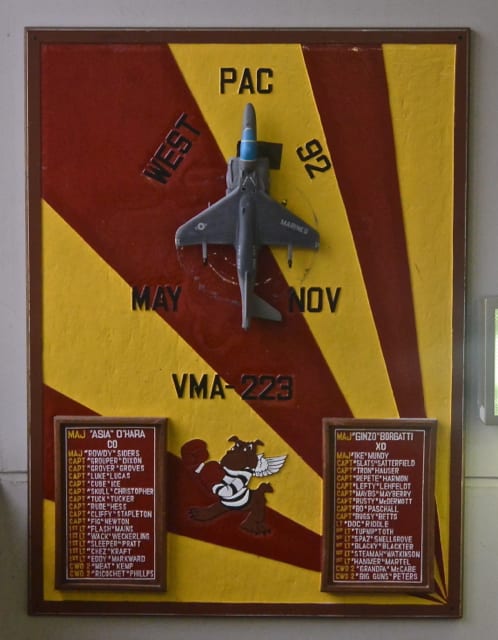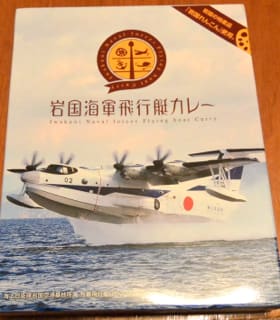アメリカでは車がないと何も出来ないため、旅行者は必ず
空港でレンタカーを借り、 そこから出発します。
それが普通なので非常にレンタカーのシステムも合理化されており、
空港バスでレンタカーセンターに行けば、あらかじめインターネットで
予約しておいたレンタカー会社のカウンターに行き、
クレジットカードと免許証を見せ、あとは車の停まっているロットに行き、
駐車場を出るときにもう一度契約書を照合するだけでおしまい。
さらにわたしがここ何年か利用しているハーツゴールデンクラブは、
前もって全て予約しておいた車がすでにロットに用意されているので、
専用駐車場に行けば大きな電光掲示板で自分の名前を見つけ、
名前の横にあるナンバーが表わすロットに行くだけでOK。
つまり、全く人と会話せず車をゲットすることが出来るのです。
しかし(笑)
システムこそとことん合理的ではあるが、一旦何か問題が起こった場合、
あなたがそれを訴える相手は、アメリカ人のレンタカー会社社員です。
これがいかに恐ろしいことか、あなたはご存知でしょうか。
愛想だけはいいが労働意欲と能力に異常なくらいのバラツキのある
アメリカ労働現場で、いざとなったときに相手がとんでもない愚か者か、
やる気がない奴か、あるいはその両方であるパーセントはほぼ2分の1くらい。
2回に1回は相手の対応にムカつき、間違いに呆れ、要領の悪さに辟易し、
まあつまり日本人であれば滞在中一度は
「アメリカ人ってもしかしたらばか?」
という呪詛の言葉を飲み込む羽目になるのです。
さて、という話をマクラにしたからには、そういう話なのですが、
今回、わたしはアメリカ滞在中にレンタカーを返品交換した数で
今までの最高回数を記録してしまいました。
この10年、一度借りたらそのまま1ヶ月乗って返してきたものなのに、
今回はまず、最初に予約していたプリウスに3日乗ったところで
1、GPS(カーナビ)が付いていないため交換。
プリウスにはGPSは付けられない、という謎の理由で
アップグレードするしかなくなったため、
わたしはボルボを選択しました。
後から考えるとこれが不幸の始まりだったのです。
ここまではお話ししましたよね?
ボルボはなかなかいい車だと思ったのですが、走り出してこれも3日目、
2、フロントパネルにタイヤチェックの警告ランプが付いた
ためまたもや交換する羽目になりました。
一つの滞在地で2台乗ることすら初めてだったのに、なんと3台目です。
交換のため訪れたハーツのカウンターで色々と感慨に耽っていると(笑)
アフリカ系のカウンター係員が、
「何難しい顔してるの。笑って笑って」
笑ってじゃねーよそっちの整備不良ってことじゃねーかよ。
誰のおかげでこんなに何度もハーツに来ないといけないと思ってんだよ。
と思わず心の中で不良になってしまうエリス中尉。
しかし外面のいい穏やかな日本人としては、内心はどうでも
とにかくニッコリと彼に笑ってみせ、さらにこの係員が
「いい靴履いてるね!バレリーナが履いてるやつみたいだね」
とお愛想をいうのにニコニコと相づちを打っておりましたorz
憎い。おのれの日本人のDNAが憎い。
そしてこのときにスィッチした車はキャデラック。
日本ではキャデラックはあまり見ませんね。
アメリカでもあまり見ません(笑い)
昔は歌にも贅沢の象徴としてよく歌われていた車ですが、
今のアメリカでは影の薄いレアな車です。
どうしてアメリカ人はビッグスリーの車を買わないのだろう、
パトリオットならばもう少しアメリカ企業を応援しそうなものだけど。
とわたしは当初思ったものですが、アメリカの道路を毎年コンスタントに走り、
そして時折はこういう「アメ車」に乗ってその理由が今ではわかります。
だって日本車の方が断然いいんだもん。
シートピッチや空調、オーディオシステムやタッチパネル、
そして何よりも燃費と取り回しの良さ。
メンテナンスが少なくて良く、信頼性がある。
一度日本車に乗ったことのある者は、わざわざ大金を出して
アメリカ車を買うことはないでしょう。
愛国とかなんとか以前に、日本車という選択は彼らにとって
最も合理的で適正な判断だってことに過ぎないのです。
おそらく皆さんが思っている以上にアメリカの道は日本車が席巻しています。
小型車も最近は大型車も殆どがトヨタでありニッサンでありホンダであり・・。
この車も決して悪くはないとは思いましたが、もしこれが日本車より
高いのであればわたしは躊躇なく日本車を選ぶでしょう。
わたしが今までここで乗ったクルマで燃費の点でまあまあだと思ったのは
サターンだけですが、そのサターンも日本車に対抗したものの
日本車に打ち勝つことが出来ずに失墜しましたね。
そんなある日、TOがボストンにやってきました。
夜の到着なので迎えにいったときのマスパイクで撮った写真。
向かいに見えるのはプルデンシャルタワーです。
実はこのとき、キャディラックのフロントパネルには
3、エンジンマークの警告ランプが点いていました(笑)
危急性はないものの、これが点いたら点検すべし、と
面倒くさいけど読んだマニュアルに書いてありましたし、
何かあっても嫌だし、TOが来たため空港に帰るのに
トランクが全部乗るだけの大きな車に代える必要があったので
わたしはTOと一緒にまたもや次の日ハーツレンタカーに突撃。
このときのカウンターの係員が、いわゆる
The worst salesclerk in the world
だったのです。まじで。
40台後半(前半かも)のその白人女性は、まず
「どうして交換したいの?」
とため息をつきながら実に不機嫌そうに車のところに行き、
ガソリンタンクの蓋をいきなり締めなおして
「ここが空いているとランプが点くのよ!
(自分で運転席に座ってエンジンをかけ)
ほら、ランプ消えたでしょ!」
と言い放ったそうです。
つまりこのまま乗って帰れという趣旨です。
そうです、というのはわたしはそのとき化粧室に行っていたからで、
このときにもう一度運転手であるわたしがチェックしていたら
ランプは実はまだ消えていなかった
(つまりおばちゃんの勘違い)ことに気がついたはずでした。
運転のことがわからないTOは、しかし
「わたしたちは最終日大人三人でトランクを乗せて
空港に行かないといけないので、大きな車にアップグレードしたい」
と食い下がりました。
彼女は面倒くさそうに
「でもないのよね~大きな車って。
いっそメルセデスのワゴンはどう?」
メルセデスはいわゆるアップグレード対象車です。
ブースの横にはこの写真のようなアップグレード車
(これはポルシェのオープン)が飾ってあります。
差額は一日150ドル(とおばちゃんは言ったけどこれも後から調べたら間違い)。
さすがに一日1万5000円の差額はもったいないね、と日本語で会話し、
「これしか大きな車が無いのなら元の車でいいです」
と彼女に返事すると、彼女はわざとらしく大きくため息をつき、
そんなら最初からごちゃごちゃ言うんじゃないわよ、
とばかり忌々しそうにパコパコキーボードを叩きます。
しかしここでわたしは嫌な予感がしたので、
「ちょっと待って!
わたし、本当にこのおばちゃんの言うように
警告ランプが消えてるのかどうか見て来る。
だってランプはガソリン入れる前からついてたんだもの」
とキャディラックのイグニッションを入れてみると、
・・・・
警告ランプは全く消えてないじゃないですかーやだー。
というかふざけんなよおばちゃん。
「ランプ消えてないんですけど!♯」
デスクに帰って彼女に告げるとかすかに彼女は狼狽し、
すぐさまキーボードを叩き、
「大きな車ならシェビーのSUVがあるけど・・・」
なぜどうして最初からそれを出さない。
というわけでシェビーのエキノックスに車を交換しました。
「・・・・どうしてこういう不毛な言い合いをしないと
こういう結論に最初からたどり着かないのかねえ」
「アメリカ人ですから」
そんな会話をしつつ息子を迎えにいきました。
ロータリーに並ぶ車はどれも同じような大型車ばかり。
翌日になってTOがハーツの明細を見せてほしいといいだしました。
「なんか昨日の晩寝ながら嫌な予感がしたんだ。
あのおばちゃんにちゃんと料金の切り替え作業なんて
出来るのかと思うと・・」
言われてみればそうです。
我々が車を借りていたのは28日間ですが、そのうち6日だけを
アップグレードの差額プラスで計算するなどというパソコン操作が、
あのいかにも頭の悪そうな、そのくせ舌打ちしたりため息をついたり、
とにかく客の神経を苛立たせることだけは平気でやってのける、
勤労意欲の薄いおばちゃんにできるものか?
限りなく答えはノーです。
そしてTOによると切り替えは全くできていないらしく、
料金が異常に高くチャージされていました。
「よく気がついたね」
「もっと早くあの場で気づくべきだったんだけどね。
おばちゃんがあまりに酷いので疑いが生じたようなもんだ」
確かにもっとテキパキと微笑みを欠かさないような店員ならば、
おそらく間違いを疑わなかったかもしれません。
そしてわたしたちはまたもや空港のハーツレンタカーへ。
昨日のおばちゃんがまたもや座っていたらどうしよう、
とわたしは怯えたのですが、幸運なことに今回は、
至極マトモなアフリカ系男性が対応しました。
どれくらいまともかというと、TOが要点を言っただけで
SUVの料金が全日にカバーされていることに気がついたくらいまともです。
「これが前の料金、これが改正後の料金です」
彼の計算を見てわたしたちは目を丸くしました。
その差額約2000ドル。
何がどうなったのかわかりませんが、あのおばちゃんは
わたしたちのチャージに20万円もの上乗せをしていたのです。
驚き呆れたわたしたちは言葉の通じないのをいいことに、彼の前で
「なんなのあのおばちゃん!もしかしてすごいバカ?」
「しかも態度悪かったしね」
「アメリカの労働現場っていったいどうなってるの?」
「チップの出ないところなんてこんなもんですよ」
と言いたい放題。
普通に対処しただけのその黒人店員がとても優秀に見えました。
最後にわたしが小さく両こぶしを握ってガッツポーズすると、
彼はにやっと笑って同じようなガッツポーズを返してきました。
そして、驚くことに一番最後に
「とにかくすみませんでした」
と謝ったのです。
「アメリカ人でこういうときに謝るなんて珍しいね」
日本なら普通のことでもこの国ではこれだけで評価される。
さても不思議な社会です。
さて、というわけでレンタカーに乗るのもあと5日。
心安らかにカーライフを満喫できるのか?
と思ったら好事魔多し(笑)
このシェビーのSUV、異常に燃費が悪い。
3日目にガソリンケージは半分を指し、試しに
そこから満タンにしてみると8ガロン、30リッターで
ガソリン代は30ドル。
「5~6日で給油か・・・」
「誰もこんな車借りないし、ましてや買うなんてありえないよ」
「タイヤ半転がりごとにガソリンをまき散らしている感じ?」
「しかも運転し難い。トップヘビーで安定悪いし」
「そりゃ皆大型車ほど日本車に乗るよなあ」
車に乗りながら散々アメ車の悪口が出るにつけ、
比べたくなくても日本車との比較になります。
「アメリカの車会社の人だって乗りたくないんじゃないこんなの」
「全然工夫が足りないよね」
レンタカー会社の係員の質などを見ても、日本っていい国だなあ、
と改めて思わずにはいられません。
「だが待ってほしい(笑)
こんなレベルの低い人間が殆どなのに、こんな社会をつくりあげた、
アメリカのすごい人は本当にすごいんじゃないだろうか」
「ごく一部の頭のいい人がそうでないその他大勢を科学的に
動かすことの出来るマニュアルってものを発明したからね」
アメリカの車とついでに労働現場に対する非難はとどまるところを知らず。
ついには

「エキノックスって名前もイマイチだよね。
エキノコックスみたいで」
「エキノックスって何だっけ」
「春分の日?」
「ほらー。やっぱり変な名前だ」
坊主にくけりゃ、で名前にまで文句をつけるわたしたち。
しかもここでめでたしめでたしとはなりませんでした。
事実は小説よりも奇なりとはよくぞいったものです。
明日はボストンを発つという日、TOとボストン美術館に向かう
高速の道中、このエキノコックスの警告ランプがつき、
4、左後ろのタイヤがパンクしている
らしいことが判明しました。
後は飛行機に乗るだけとはいえ、いやだからこそ何かあっては困ります。
そのまま我々は4度目の交換にまたハーツに向かいました。
選択の余地なく(笑)今度の車はジープ。
もう怒る元気も失せ、力なく我々は
「じーぷのったことなかったしよかったんじゃない~?」(棒)
「そうだねーいろいろのれておもしろいねー」(棒)
次の日、われわれはそのジープにトランクと大人3人が乗り、
無事に空港に着いてやっとのことで5台目の車を返却しました。
そしてサンフランシスコに飛行機で向かいます。
「サンフランシスコのハーツではどんな苦難が待ち受けているのだろうか」
心配しつつサンフランシスコのハーツに着いたら、驚くことにロットには予約していた
GPS付きのプリウスが
ちゃんと停まっていて(日本では普通のことでもアメリカでは略)
しかもそのプリウスには 、
大型車でないと積載不可能と思われた大小計10個の荷物と
大人三人がまるで魔法のように余裕で収まったのです。
わたしたちは絶句し、
「ボストンの最初のプリウスにGPSさえついていれば・・・・」
あるいは2台目がもし日本車であったなら、
おそらく5台も車を乗り換えることはならなかったに違いありません。
日本と日本人と日本の技術の素晴らしさをあらためて認識しました。