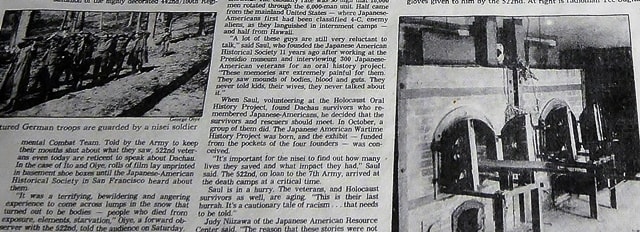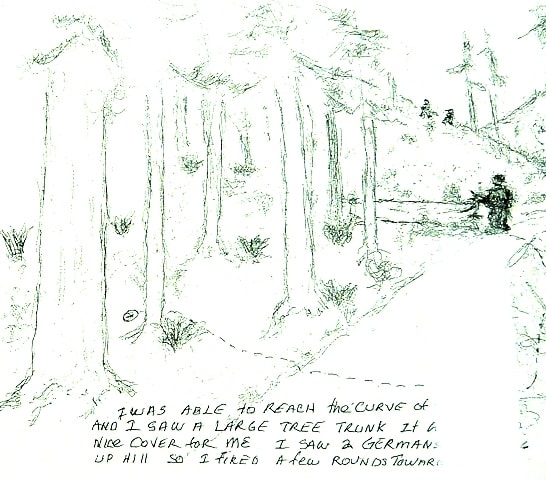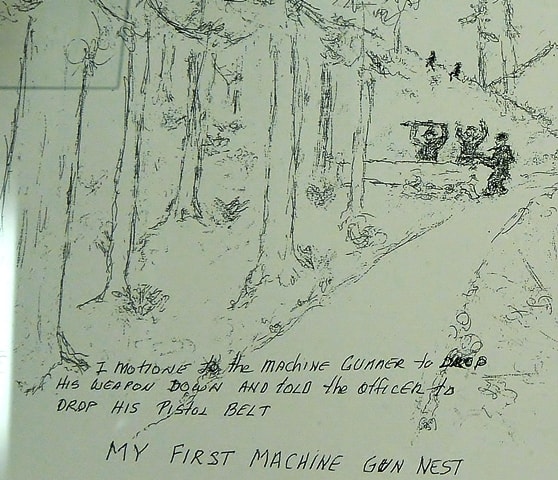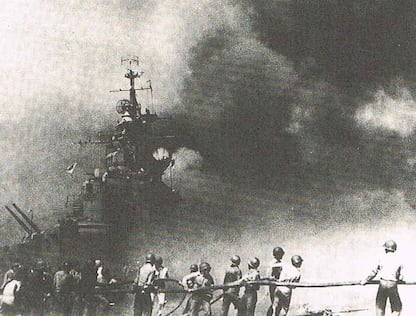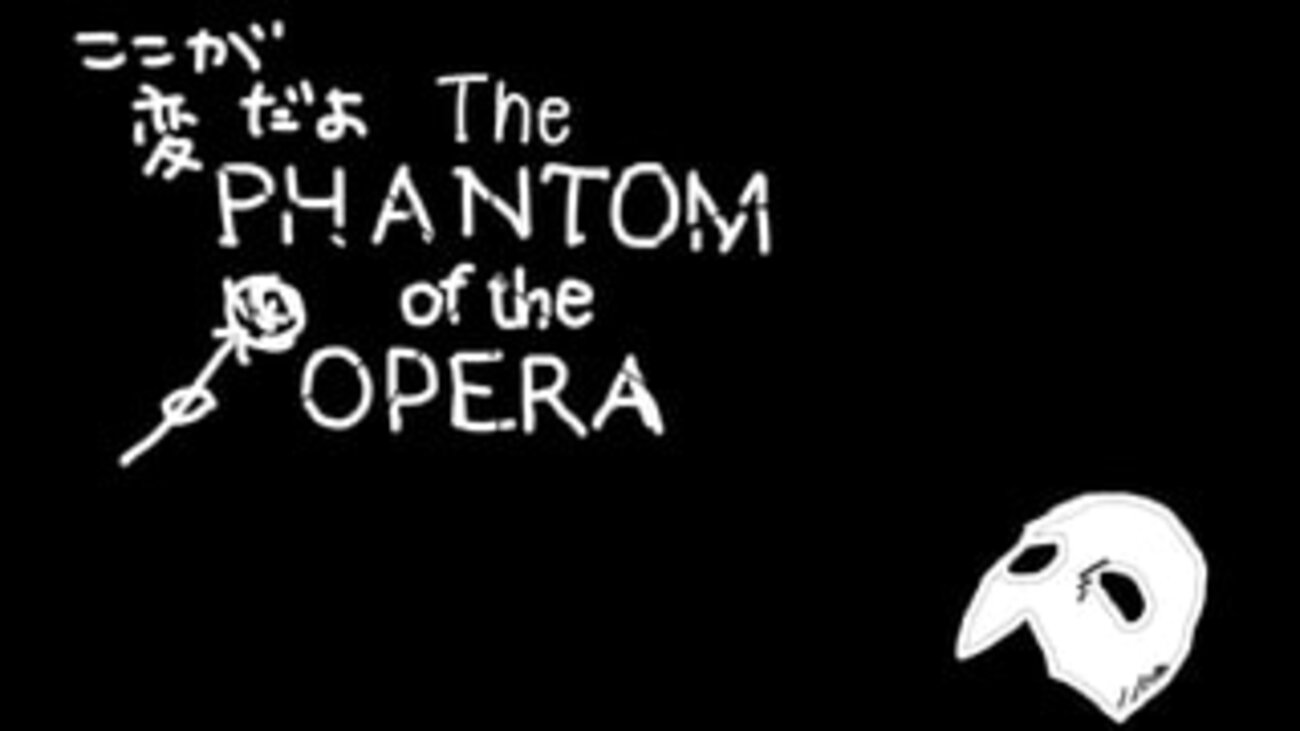1月末に多分インフルエンザにかかっているのにアメリカにわざわざ行って、
その大半を部屋で寝ていたときに見た番組を今日も紹介します。
アメリカ行きのご報告の時にもちらっと書きましたが、
三人の太った男が大自然に挑むという誰得チャレンジ番組、
「FAT GUYS IN THE WOODS」。

一週間で人生が変わる、とか字幕が付いてますが、つまりは、
日頃カロリー消費量を上回るだけ食って、その結果脂肪を溜め込んだ男たちを、
厳しい自然にサバイバルさせて根性を叩き直す(たぶん)というのが
この番組のキャッチフレーズ。
以前、夏にアメリカでやっている「ネイキッド・アンド・アフレイド」という
破天荒のチャレンジング番組をご紹介したことがあります。
ネイチャー系の、ナショジオチャンネルとか、このウェザーチャンネルなどでは、
この手の大自然に挑む系が過去たくさんありました。
白髪をおさげにした男が、頼まれもしないのに山の中で穴を掘ったり蛇を食べたり、
といったサバイバルものをすっかり見慣れてしまったアメリカ人にとっても、
この、「見ず知らずの男女が一糸まとわぬ姿でサバイバル」という企画は
一大センセーションであったようです。
昨年の夏は、この人気にあやかって柳の下のドジョウを狙ったらしい
なんとも言えない不愉快な番組を見つけました。
題名は忘れましたが、最初から一糸まとわぬ姿で男女が出会う「マッチング」番組です。
海辺のロッジが一軒与えられ、そこで三人の男、三人の女がいきなり
全てを見せ合うところから始まって、さて、誰がカップルになれるでしょうか、
という、18歳以下は視聴禁止(とはなっていないのが恐ろしい)番組。
つまり「ネイキッド」からサバイバルの部分を抜いた企画です。
一応写真は撮ったのですが、あまりに下品すぎて、ここで
写真をあげて内容を説明するのは憚られる番組でした。
全部を見たわけではありませんが、アメリカのテレビ番組は
その下品さにおいて下を見ればきりがありません。
そんななかで、この「ファットガイ」はむしろ健全すぎるくらい健全です。
普通すぎて謎です。
なぜ太った男なのか。なぜ三人なのか。
調べてみたら2014年に始まったらしいので、すでに3年目を迎えているのです。
もしかしたら夏しかアメリカにいないわたしが知らなかっただけで、
ここでは結構人気がある番組だったのかもしれません。
太古の昔、人間が狩りによって食べ物を得ていたというところから
本番組のタイトルは始まります。

食物連鎖のトップにいる人類は、今やその座に甘んじて?
肥大したお腹に悩むようになった・・・・・・・
って、そりゃあんたたちアメリカ人だけだろっていう。

「思い出すが良い。我々は打たれても立ち上がった。我々は強かったのだ。
文明に飼いならされて、すっかり牙を抜かれているものたちよ」
そして、
「カウチから降りて、ポテトチップスの脂をスェットパンツで拭き(笑)
そして大自然の声で目覚めようではないか」
と続きます。
というわけでカウチから降りてきたデブ三人。
この姿を見てわたしはたちどころに
「なぜデブなのか」だけは理解することができました。
大抵この番組は凍りつくような雪山で行われるため、
万が一のために脂肪を溜め込んで保温力のあるデブを出演させることで
番組はリスク回避というか、保険をかけているのです。(たぶん)
まず集められた三デブは、「師匠」であるナビゲーターに会うため、
ある程度の苦労をすることを余儀なくされます。
今回は、この大きな氷柱の立つような洞窟を抜けたところに、
その「師匠」がいる、と聞かされ、
立って歩くこともできない難所を越えていくのでした。
ただでさえ日頃から運動に無縁なデブたち、もうここで青息吐息です。
氷柱がまるでオブジェのように立つ洞穴の出口に人影が。
これは一体誰?
この人物が、当番組の「サバイバリスト」、クリーク・スチュアート。
クリークは、14歳の時にイーグル・スカウトになっています。
イーグルスカウトとはアメリカのボーイスカウトにおける最高位の章で、
21以上のメリットバッジ、技能賞を持っていなくてはいけません。
つまり、ボーイスカウトの中でも特別な存在です。
所持者は特別な奨学金を利用できるほか、ときには大統領晩餐会にも招待されるなど、
大変名誉とされている地位なのです。
そんな人ですから、サバイバルにかけてもプロフェッショナル。
現在、そういった自然での知恵を伝授するため、インディアナ州に
サバイバルロッジを持ち、そこで体験指南をしているそうです。
冒頭写真は番組宣伝のHPでポテトチップスに火をつけるクリーク。
ちなみに、番組中この写真のように、「サバイバル豆知識」が字幕で現れます。
たとえば「サバイバルの時にクリークはウールとレザーを着用する」とありますね。
確かに、ダウンジャケットでただでさえデブなのに1.2倍くらいに膨らんでいる
参加者に比べると、クリークは異様なくらいの薄着に見えます。
慣れているのか、他にサバイバリストならではの理由があるのでしょうか。
ところで、この斜めに着る形のスヌードというかマフラーは、
なかなかおしゃれで素敵だと思いました。
こんなの売ってたらぜひ欲しいけど、多分手編みでしょう。
お互い挨拶が終わったあとは、これからのサバイバルについて
さんざん脅かされるというか、予告を受けます。
神妙な顔でそれを聞く三デブ。
華氏34度というのは摂氏1度のことです。
昼間でこれですから、夜には確実に零下になるでしょう。
まず常緑樹の葉のついた枝を集めて仮眠所を作ったあとは、
火を起こすことを始めねばなりません。
クリークはどんな状況でも確実に火を起こす方法をいくつも知っており、
適宜デブたちにそれを指南します。
二本の立木にかけたベルトでどうにかしてどうかすると、
木と木が人力でするより早くこすり合わせられるということみたいです。
木の幹に火を起こす木を挟み、ベルトで回転させて発火させる方法かな?
「あまり強くこすり過ぎない方法がいいよ」
などとアドバイスをしているうちに、
木切れから煙が出たので、それをおが屑のようなものに移して
みんなでフーフー吹きます。
punky wood、パンクウッドともいいますが、森の朽木から採れる
(幹を蹴飛ばしたりして採る)木屑のことをこういうようです。
簡単に火がつくので、サバイバルには欠かせません。 (豆知識による)

どうもクリークは、人に呼びかける時にいちいち「MAN」をつける癖があるようです。
もっと吹いて火を起こせ、と言っております。
やったー!
ついに火を起こして焚き火をすることができました。
「You sucker」と言っていますが、サッカー=おめでたい人、と、
ふうふう吹く、の反対で「吸う」をかけているのかと思われます。
日本語に翻訳しても何が面白いの、ってことになってしまいますが。

さて、次はお待ちかね、何かをお腹にいれる時間です。
これまでカウチポテトしてきた歴代のデブたちが、この番組で食べさせられたのは
大カブトムシの幼虫
木のラーメン:トナカイモス(ハナゴケ)
フクロネズミ
ローストしたミツバチ
野兎
どんぐりの粥
皮をむいた蛇
アヒル
エルサレムアーティチョーク
ウズラ
ガマガエル
ワイルドベリー
ローズヒップベリーティー
まあ、全然オッケーなものもたくさんありますよね。
特に最初から料理されていさえすれば。
問題は自分でそれを獲って、殺した獲物の皮を剥いで、
焚き火で炙ったりするというそのプロセスにあります。
今回、カウチポテトの代わりに彼ら三デブに与えられた
自然の中の食べ物とは、なんだったのでしょうか。
後半に続く。










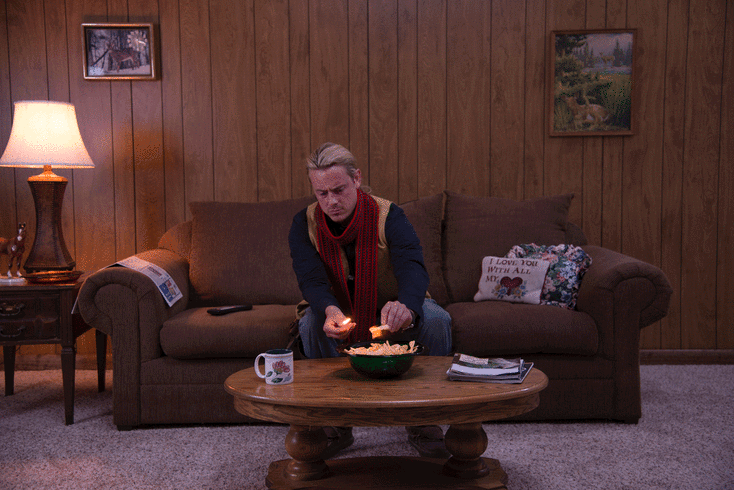




















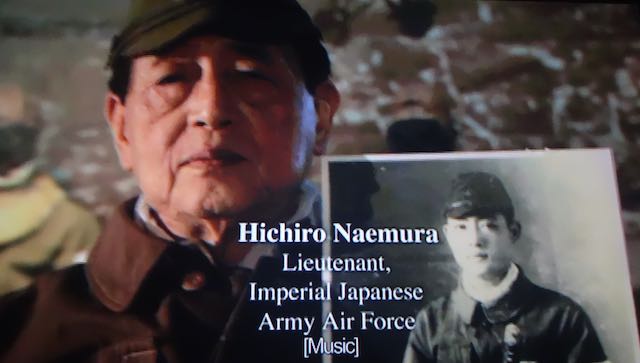



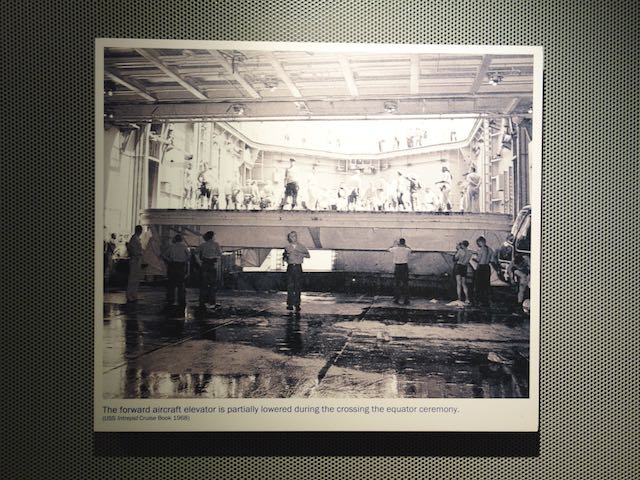

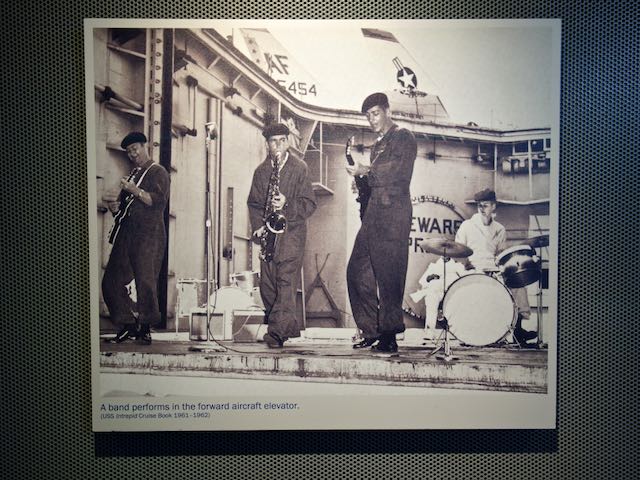






























































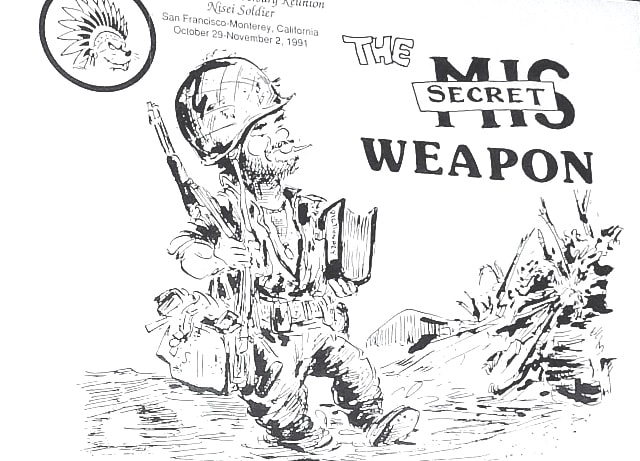
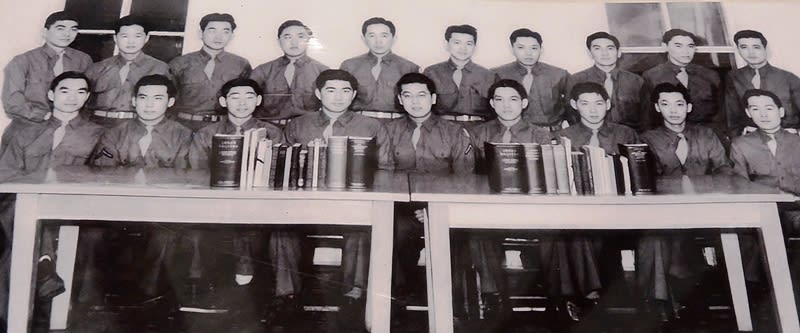












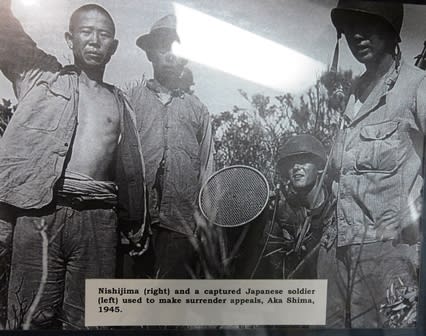










 まって時間を潰すのも、彼らが観光客だから。
まって時間を潰すのも、彼らが観光客だから。