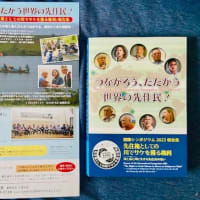日本政府のアイヌ政策推進に関して、進み具合が全体的に把握できるように工夫をしてほしいと推進会議の方にお願いしたところ、その通りですと言わんばかりにうなずかれたので待っているのですが、一向に推進会議の議事概要も遅いし、内容も不透明な記述のみなのにがっかりです。一方では国民の理解(マジョリティの理解)が必要だといいながら、努力を怠っているとしか思えません。早急の対処を望みます。作業部会議事概要は以下。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/kaisai.html

今年度のわが家のクリスマスカードの手作り飾り。(図をクリックして拡大)
近くの海岸からとってきた小石をプレゼントに見立てました。オロロン鳥もいます。
数年前に当センターに実習に来てくれた農村伝道神学校4年の佐藤真史さんの卒論を送って頂き、興味深く読ませて頂きました。
タイトルは「矢内原忠雄におけるキリスト教植民地主義」。わたしと同じく無教会主義の基督教独立学園高校を卒業後、農伝で学んだ佐藤さんは、高校時代に内村鑑三や矢内原に触れることが多くあった。しかし、姜尚中著『オリエンタリズムの彼方へ」にある矢内原批判に触れ、矢内原を「重層的」に理解しようと論文のテーマに決めたようです。
興味のある部分だけの引用となりますが紹介します。
矢内原(1893~1961)は、愛媛で生まれ、1904年に神戸中学に入学。当時の校長は札幌農学校二期生(内村や新渡戸稲造と同期)の鶴崎久米一(これも不思議な接点ですね)。後に、内村の聖書講義に出席するようになり、無教会キリスト者となります。
1913年に東京帝国大入学。吉野作造の政治学や、1909年に開講したばかりの新渡戸稲造による植民政策学に深い影響を受ける。卒業後、住友総本店に就職するも、1920年に新渡戸が国連事務次長に内定したことを受けて、その後任助教授として東京帝大に赴任。留学を経て1923年以降、植民政策学の基礎を築く。この頃の代表的著作には、『植民及植民政策』(1926年)、『帝国主義化の台湾』(1929)、『満州問題』(1934)、『南洋群島の研究』(1935)、『帝国主義下の印度』(1937)など有り。
じっくり読んで内容確認をしたいですね。
しかし、日本の中国侵略政策、満州政策を批判し、1937年12月に大学を辞職。戦後の1945年11月に復職し、大学総長になって活躍。
日本において1890年に札幌農学校にて植民学講座が始まります。「植民史」(96年から「植民論」と改名)で、最初の講義担当者は佐藤昌介(後に新渡戸稲造と佐藤が交互に担当 過去blog参照 http://pub.ne.jp/ORORON/?entry_id=3879188)。
次いで1909年に東京帝国大学に「殖民政策学講座」が開講。その時の初代担当教授が新渡戸。彼の後を次いで、2代目の担当教授が矢内原。
矢内原が著書『植民及植民政策』の最初に新渡戸に対し、『特別の謝意』を捧げていることを佐藤さんが紹介してくれています。
「・・・(新渡戸)先生より、私は深き師恩を受けた。人格尊重の観念及び之に基づく植民政策論は、最も私を感銘せしめたる先生の教の一であった」
「野蛮」の対極に「進歩した文明」を位置づけ、「文明の伝播」として植民思想を推し進めて行った新渡戸を継いで、矢内原は「植民地人に愛の福音を告ぐべき」と「異邦伝道」を結びつけたようです。
矢内原の植民地当時政策は、
①従属主義(被植民者への利益を考慮せず、完全従属を強いる)
②同化主義(植民地の本国化)
③自主主義(被植民地の歴史的特殊性を認め、自治を認めるが独立を認めず協同一大帝国を維持)
の三つに分けられ、矢内原は③を提唱。
これにもキリスト教の「愛」からの発想があり、①②は「植民者の利益中心主義」であって、③こそが「虐げらるるものの解放、沈めるものの向上、而して自主独立なるものの平和的結合」という「希望」につながると考えていたようです。
論文は矢内原が「文明の伝播」思想に基づき、どのようにアイヌ民族への差別意識を内在化させていたかを検証。そこには松浦武四郎(『知床日誌』他)や長谷川修(『レラ・チセへの道』P.248ff)にあるようなアイヌ民族への共感はなく、むしろ「『野蛮』として一方的に規定するものだった」ことを論じています。
最終章は割愛しますが、矢内原のもう一面、「キリスト教植民地主義を内面化しながらもポストコロニアル神学に繋がる視座」について論証しつつ、日本基督教団批判を浮き彫りにしています。
勉強になりました。より詳細に参考文献も確認しつつ深め、歴史の反省と共に宣教の課題を確認したいと思いました。

暑寒別岳の朝焼け 青
留萌も寒い日が続きます、昨日朝に引き続き今朝もマイナス8度を下回りました。
それでも午後には元気に遊びに来るこども達に元気をもらっています。
みなさん、ご自愛下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/kaisai.html

今年度のわが家のクリスマスカードの手作り飾り。(図をクリックして拡大)
近くの海岸からとってきた小石をプレゼントに見立てました。オロロン鳥もいます。
数年前に当センターに実習に来てくれた農村伝道神学校4年の佐藤真史さんの卒論を送って頂き、興味深く読ませて頂きました。
タイトルは「矢内原忠雄におけるキリスト教植民地主義」。わたしと同じく無教会主義の基督教独立学園高校を卒業後、農伝で学んだ佐藤さんは、高校時代に内村鑑三や矢内原に触れることが多くあった。しかし、姜尚中著『オリエンタリズムの彼方へ」にある矢内原批判に触れ、矢内原を「重層的」に理解しようと論文のテーマに決めたようです。
興味のある部分だけの引用となりますが紹介します。
矢内原(1893~1961)は、愛媛で生まれ、1904年に神戸中学に入学。当時の校長は札幌農学校二期生(内村や新渡戸稲造と同期)の鶴崎久米一(これも不思議な接点ですね)。後に、内村の聖書講義に出席するようになり、無教会キリスト者となります。
1913年に東京帝国大入学。吉野作造の政治学や、1909年に開講したばかりの新渡戸稲造による植民政策学に深い影響を受ける。卒業後、住友総本店に就職するも、1920年に新渡戸が国連事務次長に内定したことを受けて、その後任助教授として東京帝大に赴任。留学を経て1923年以降、植民政策学の基礎を築く。この頃の代表的著作には、『植民及植民政策』(1926年)、『帝国主義化の台湾』(1929)、『満州問題』(1934)、『南洋群島の研究』(1935)、『帝国主義下の印度』(1937)など有り。
じっくり読んで内容確認をしたいですね。
しかし、日本の中国侵略政策、満州政策を批判し、1937年12月に大学を辞職。戦後の1945年11月に復職し、大学総長になって活躍。
日本において1890年に札幌農学校にて植民学講座が始まります。「植民史」(96年から「植民論」と改名)で、最初の講義担当者は佐藤昌介(後に新渡戸稲造と佐藤が交互に担当 過去blog参照 http://pub.ne.jp/ORORON/?entry_id=3879188)。
次いで1909年に東京帝国大学に「殖民政策学講座」が開講。その時の初代担当教授が新渡戸。彼の後を次いで、2代目の担当教授が矢内原。
矢内原が著書『植民及植民政策』の最初に新渡戸に対し、『特別の謝意』を捧げていることを佐藤さんが紹介してくれています。
「・・・(新渡戸)先生より、私は深き師恩を受けた。人格尊重の観念及び之に基づく植民政策論は、最も私を感銘せしめたる先生の教の一であった」
「野蛮」の対極に「進歩した文明」を位置づけ、「文明の伝播」として植民思想を推し進めて行った新渡戸を継いで、矢内原は「植民地人に愛の福音を告ぐべき」と「異邦伝道」を結びつけたようです。
矢内原の植民地当時政策は、
①従属主義(被植民者への利益を考慮せず、完全従属を強いる)
②同化主義(植民地の本国化)
③自主主義(被植民地の歴史的特殊性を認め、自治を認めるが独立を認めず協同一大帝国を維持)
の三つに分けられ、矢内原は③を提唱。
これにもキリスト教の「愛」からの発想があり、①②は「植民者の利益中心主義」であって、③こそが「虐げらるるものの解放、沈めるものの向上、而して自主独立なるものの平和的結合」という「希望」につながると考えていたようです。
論文は矢内原が「文明の伝播」思想に基づき、どのようにアイヌ民族への差別意識を内在化させていたかを検証。そこには松浦武四郎(『知床日誌』他)や長谷川修(『レラ・チセへの道』P.248ff)にあるようなアイヌ民族への共感はなく、むしろ「『野蛮』として一方的に規定するものだった」ことを論じています。
最終章は割愛しますが、矢内原のもう一面、「キリスト教植民地主義を内面化しながらもポストコロニアル神学に繋がる視座」について論証しつつ、日本基督教団批判を浮き彫りにしています。
勉強になりました。より詳細に参考文献も確認しつつ深め、歴史の反省と共に宣教の課題を確認したいと思いました。

暑寒別岳の朝焼け 青
留萌も寒い日が続きます、昨日朝に引き続き今朝もマイナス8度を下回りました。
それでも午後には元気に遊びに来るこども達に元気をもらっています。
みなさん、ご自愛下さい。