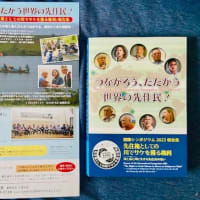世界先住民族サミットinあいち2010 に前半参加してきました。
2年前の二風谷・札幌での先住民族サミットで事務局長だった佐々木さんと飛行機で一緒になり、前回を懐かしみながら会場へ。
当日、配布された「プログラム&発表要旨」の冊子はいい資料になります。事前にフォーラム発題者の発表内容をA42枚程度にまとめて書いてもらっていたものが掲載されています。当日の発表時間はひとり10~15分程度でしたから、事前に文書化されたものをより短くしなければならず、発表者もご苦労されたことでしょう。

一日目の萱野さんのトーク
フォーラム セッション1「生物多様性と先住民族の現状と生物多様性」では、5名の方の基調トーク。
興味深く聞いたのは稲村哲也さん(愛知県立大・多文化共生研究所)の話。アンデスの先住民族の生活から、先住民族が古代の知恵を継承し、生物多様性の保全や持続的利用を実践してきたか、そしてそのことが現代を生きるわたしたちにとってもいかに重要かを話されました。
そのひとつに、チャクと呼ばれる「殺さない狩猟」の説明がありました。古代インカ帝国ではビクーニャなど野生動物を追い込んで捕獲し、殺さずに毛だけを刈り取って再び逃がすという猟法を行っていたとか。インカ崩壊後、チャクのシステムは一時なくなりはしたものの1993年に復活。幻滅した野生動物も徐々に増加しているようです。
もうひとつ、アンデスというと多様な作物の原産地で、ジャガイモ、サツマイモ、かぼちゃ、トマト、唐辛子、ピーナッツなど、それぞれ標高に応じて多くの品種が育っているようです。古代から何種類もの品種を育てることで、その年の気候変動で収穫が少ない品種があっても他の品種でまかなえるというリスクを軽減させる方法を考えていたというのです。また、毒があるために害虫や寒さに強いイモも栽培し、上手に毒抜きをしながら食用としている、と。稲村さんは最後に以下の言葉を述べます。
「アンデスの人々は、自然を固く画一的な方法で管理しようとするのではなく、ゆるやかに管理して持続的に多様に利用してきました。『生物多様性の危機』が叫ばれている現在、そこから私たちが学ぶべきことは極めて大きいといえます」(「発題要旨」より)。
続いて海外から招待された先住民族の皆さんの紹介がありました。
グアテマラ・マヤ民族のロサりーナさん、アラスカ州クリンギット民族のボブ・サムさん、アオテアロア・マオリ民族のS.ケントさん、E.ウォーカーさん、そして、台湾アミ民族のシン・オラムさんは前回に引き続いての参加。
加えて、今回は米・プエブロ民族のロン・ルッキングエルクさん、米・ナバホ民族のクリシー・カストロさん、東ティモール・ロウ民族のエゴ・レモスさん、ネパール・セルパ民族のパサン・シェルパさんが新たに参加。
皆さんのお話もよき学びとなりました。
2日目は、会場が変わり、モロコロパーク(地球市民交流センター)での開催。
フォーラム中、わたしは外でアイヌ民芸品販売ボランティア。時々、フォーラム内容を聞きに中に入りましたが、午後3時には帰路に着きました。
全体の報告はディバンさんが11月中旬発行予定の機関紙ノヤ最新号にて書いてくださいますのでお待ち下さい。他にも感じたことや学んだこと、出会いなど順に書いていきます。
今回はCOP10関連で環境問題が意識されているからか、先住民族の権利回復というよりも、持続可能な環境利用を知恵として持っている先住民族から学ぼうというような内容が多かったように感じます。もちろん、環境破壊が進むことで、一番最初に生命の危機があるのは先住民族ですから、環境問題は先住民族の権利としっかりとつながっていることですが。

二日目の会場。司会をしているのは三重TV「おはようテンTEN」「ズームインサタデー」などで活躍している宮村その美アナ。三重に甥っ子たちがいるので、会ったことを自慢しようかと・・・・
今回は、台湾原住民族からシン・オラムさんとお連れ合い、そして、ディバンさんが参加したので、
アミ民族、タイアル民族、ブヌン民族の三民族がわたしたちの関係から参加。
2年前の二風谷・札幌での先住民族サミットで事務局長だった佐々木さんと飛行機で一緒になり、前回を懐かしみながら会場へ。
当日、配布された「プログラム&発表要旨」の冊子はいい資料になります。事前にフォーラム発題者の発表内容をA42枚程度にまとめて書いてもらっていたものが掲載されています。当日の発表時間はひとり10~15分程度でしたから、事前に文書化されたものをより短くしなければならず、発表者もご苦労されたことでしょう。

一日目の萱野さんのトーク
フォーラム セッション1「生物多様性と先住民族の現状と生物多様性」では、5名の方の基調トーク。
興味深く聞いたのは稲村哲也さん(愛知県立大・多文化共生研究所)の話。アンデスの先住民族の生活から、先住民族が古代の知恵を継承し、生物多様性の保全や持続的利用を実践してきたか、そしてそのことが現代を生きるわたしたちにとってもいかに重要かを話されました。
そのひとつに、チャクと呼ばれる「殺さない狩猟」の説明がありました。古代インカ帝国ではビクーニャなど野生動物を追い込んで捕獲し、殺さずに毛だけを刈り取って再び逃がすという猟法を行っていたとか。インカ崩壊後、チャクのシステムは一時なくなりはしたものの1993年に復活。幻滅した野生動物も徐々に増加しているようです。
もうひとつ、アンデスというと多様な作物の原産地で、ジャガイモ、サツマイモ、かぼちゃ、トマト、唐辛子、ピーナッツなど、それぞれ標高に応じて多くの品種が育っているようです。古代から何種類もの品種を育てることで、その年の気候変動で収穫が少ない品種があっても他の品種でまかなえるというリスクを軽減させる方法を考えていたというのです。また、毒があるために害虫や寒さに強いイモも栽培し、上手に毒抜きをしながら食用としている、と。稲村さんは最後に以下の言葉を述べます。
「アンデスの人々は、自然を固く画一的な方法で管理しようとするのではなく、ゆるやかに管理して持続的に多様に利用してきました。『生物多様性の危機』が叫ばれている現在、そこから私たちが学ぶべきことは極めて大きいといえます」(「発題要旨」より)。
続いて海外から招待された先住民族の皆さんの紹介がありました。
グアテマラ・マヤ民族のロサりーナさん、アラスカ州クリンギット民族のボブ・サムさん、アオテアロア・マオリ民族のS.ケントさん、E.ウォーカーさん、そして、台湾アミ民族のシン・オラムさんは前回に引き続いての参加。
加えて、今回は米・プエブロ民族のロン・ルッキングエルクさん、米・ナバホ民族のクリシー・カストロさん、東ティモール・ロウ民族のエゴ・レモスさん、ネパール・セルパ民族のパサン・シェルパさんが新たに参加。
皆さんのお話もよき学びとなりました。
2日目は、会場が変わり、モロコロパーク(地球市民交流センター)での開催。
フォーラム中、わたしは外でアイヌ民芸品販売ボランティア。時々、フォーラム内容を聞きに中に入りましたが、午後3時には帰路に着きました。
全体の報告はディバンさんが11月中旬発行予定の機関紙ノヤ最新号にて書いてくださいますのでお待ち下さい。他にも感じたことや学んだこと、出会いなど順に書いていきます。
今回はCOP10関連で環境問題が意識されているからか、先住民族の権利回復というよりも、持続可能な環境利用を知恵として持っている先住民族から学ぼうというような内容が多かったように感じます。もちろん、環境破壊が進むことで、一番最初に生命の危機があるのは先住民族ですから、環境問題は先住民族の権利としっかりとつながっていることですが。

二日目の会場。司会をしているのは三重TV「おはようテンTEN」「ズームインサタデー」などで活躍している宮村その美アナ。三重に甥っ子たちがいるので、会ったことを自慢しようかと・・・・
今回は、台湾原住民族からシン・オラムさんとお連れ合い、そして、ディバンさんが参加したので、
アミ民族、タイアル民族、ブヌン民族の三民族がわたしたちの関係から参加。