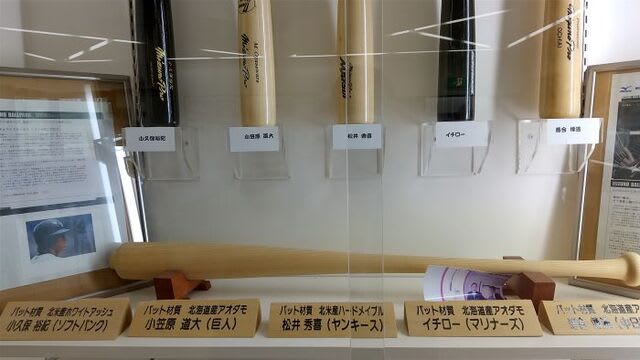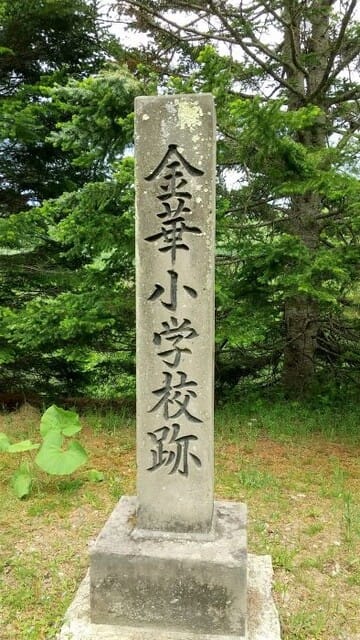3日~4日にかけて、帯広に行ってきました。
3日は7時過ぎに出発しまずは岩見沢へ、そこから帯広へ。
国道234号線を南下し栗山町角田から道道3号線へ入り夕張経由で紅葉山から樹海ロードへ、
その後はひたすら樹海ロードを東へ東へと…。
路面は雪もなくい完全露出、行きも帰りも快適なドライブとなりました。
3日は日曜日、樹海ロードは交通量も少なく、
ナント紅葉山から十勝清水まで他の車を追い越すことも追い越されることもなく走り切りました。
順調に走ったので予定より早く到着、音更の道の駅に入りしばし休憩、
その間に車内で小野伸二選手の引退試合を観戦、最後のプレーを拝見。
小野伸二選手ほどの大物の引退となると、感慨ひとしおですなぁ。
4日は帰るだけ、午前中には札幌に入っていました。
これだけ見れば普通にただ帯広に行って帰ってきただけなのですが、
年のせいか結構疲れたのは我ながらびっくり。
順調に走りすぎて時間を余してしまったせいもあるのだろう。
とありあえず無事に帰ってきました。
年内の泊りでのお出かけはあと1回(旭川)の予定。
さて、いつ行こうかな。