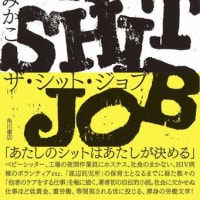帚木蓬生『エンブリオ』(集英社、2002年)
 この小説は、先に読んだ『インターセックス』の前編のような小説だった。『インターセックス』が面白かったので、図書館にこの作者のものを探しに行ったら、これがあって、ちらっと見たら、岸川院長とか加代とかが出てくるので、もしかしたら続き物かなと思い借りてみたら、案の定、そうだった。
この小説は、先に読んだ『インターセックス』の前編のような小説だった。『インターセックス』が面白かったので、図書館にこの作者のものを探しに行ったら、これがあって、ちらっと見たら、岸川院長とか加代とかが出てくるので、もしかしたら続き物かなと思い借りてみたら、案の定、そうだった。
『インターセックス』で翔子が謎解きをする連続死亡事件が『エンブリオ』で次々と起こることになっている。この小説では、岸川がサンビーチ病院で行っている生殖医療、不妊治療などが紹介され、モナコでの国際学会で男性の体内でエンブリオを成長させて、失敗はしたが、成功まであと一歩というところまでこぎつけたという発表をして大きな反響を呼び、それがアメリカの生殖医療企業であるリブロテックの会長の目に留まり、岸川と一緒にモナコに行っていた加代と、サンビーチ病院のファームの責任者である鶴が買収されてスパイをしたことから、岸川に殺されてしまうという展開である。
もちろんこの小説の興味は、そんな殺人事件のトリックとかではなく、世界の生殖医療がどんなところに来ているか、一般人の知らない間に、不妊治療という名目の元で人間の誕生がどんな風に操作されているのかを分かりやすく示しているところにある。
私なんかはときどきテレビなどである不妊治療の話なんかを見て、そんなことまでして子どもを得なくてもいいじゃないかと思っている人間だが、そんな思惑などに関係なく、事態は進んでいるのだろう。この小説にもでてくるが、ノーベル賞ものだともてはやされている例のIP細胞から実用の段階になるまでには相当の時間がかかるだろうことは素人でも分かる。それに比べたら、胎児から直接そういう臓器を成長させて使えるようにすることのほうがよほど手っ取り早いといえばそうだろう。だが、本当にそんなことをしている、あるいはしようとしている研究機関や医療機関はあるのだろうか? 不妊治療といえばなんでもできそうなアメリカならそういうこともやっているのかもしれないと思う。
この小説でも公立病院なんかはもうだめだというようなことが描かれているが、すべての病院がサンビーチ病院のようになるためにしのぎを削るというのはおかしいと思う。地方にいくつか拠点病院としてこういう先端医療をする病院があり、その他は普通に医療を丁寧に行ってくれる病院が充実しているということではだめなのだろうか?そういうことは不可能なのだろうか? 今の日本の医療崩壊は、また原因が別のところにあるように思うのだが、医者が十分に集まらないという原因の一つに、先端的な医療を行えるところを求めて、普通の病院から医者が去っていくということもあるのだとしたら、みんながみんなスペシャリストでなくてもいいから、地域医療の原点を理解して医療に当たってくれる医者はいないわけではないと思うのだが、どんなものなのだろうか?
先ごろ、子どもの脳死も認める法律が通った。本当に死んだと言えるのかどうか分からない子どもを死んだことにして、その臓器を移植するなんて、私にはとても考えられないのだが、この小説にはパーキンソン病の治療のために自分の胎児を早期に流産させてその脳を注入するなんていう、どこまで本当なのか分からないような話が登場する。自分の延命のためにわが子を犠牲にするのなら文句のいいようがないとでも言うのだろうか?
 この小説は、先に読んだ『インターセックス』の前編のような小説だった。『インターセックス』が面白かったので、図書館にこの作者のものを探しに行ったら、これがあって、ちらっと見たら、岸川院長とか加代とかが出てくるので、もしかしたら続き物かなと思い借りてみたら、案の定、そうだった。
この小説は、先に読んだ『インターセックス』の前編のような小説だった。『インターセックス』が面白かったので、図書館にこの作者のものを探しに行ったら、これがあって、ちらっと見たら、岸川院長とか加代とかが出てくるので、もしかしたら続き物かなと思い借りてみたら、案の定、そうだった。『インターセックス』で翔子が謎解きをする連続死亡事件が『エンブリオ』で次々と起こることになっている。この小説では、岸川がサンビーチ病院で行っている生殖医療、不妊治療などが紹介され、モナコでの国際学会で男性の体内でエンブリオを成長させて、失敗はしたが、成功まであと一歩というところまでこぎつけたという発表をして大きな反響を呼び、それがアメリカの生殖医療企業であるリブロテックの会長の目に留まり、岸川と一緒にモナコに行っていた加代と、サンビーチ病院のファームの責任者である鶴が買収されてスパイをしたことから、岸川に殺されてしまうという展開である。
もちろんこの小説の興味は、そんな殺人事件のトリックとかではなく、世界の生殖医療がどんなところに来ているか、一般人の知らない間に、不妊治療という名目の元で人間の誕生がどんな風に操作されているのかを分かりやすく示しているところにある。
私なんかはときどきテレビなどである不妊治療の話なんかを見て、そんなことまでして子どもを得なくてもいいじゃないかと思っている人間だが、そんな思惑などに関係なく、事態は進んでいるのだろう。この小説にもでてくるが、ノーベル賞ものだともてはやされている例のIP細胞から実用の段階になるまでには相当の時間がかかるだろうことは素人でも分かる。それに比べたら、胎児から直接そういう臓器を成長させて使えるようにすることのほうがよほど手っ取り早いといえばそうだろう。だが、本当にそんなことをしている、あるいはしようとしている研究機関や医療機関はあるのだろうか? 不妊治療といえばなんでもできそうなアメリカならそういうこともやっているのかもしれないと思う。
この小説でも公立病院なんかはもうだめだというようなことが描かれているが、すべての病院がサンビーチ病院のようになるためにしのぎを削るというのはおかしいと思う。地方にいくつか拠点病院としてこういう先端医療をする病院があり、その他は普通に医療を丁寧に行ってくれる病院が充実しているということではだめなのだろうか?そういうことは不可能なのだろうか? 今の日本の医療崩壊は、また原因が別のところにあるように思うのだが、医者が十分に集まらないという原因の一つに、先端的な医療を行えるところを求めて、普通の病院から医者が去っていくということもあるのだとしたら、みんながみんなスペシャリストでなくてもいいから、地域医療の原点を理解して医療に当たってくれる医者はいないわけではないと思うのだが、どんなものなのだろうか?
先ごろ、子どもの脳死も認める法律が通った。本当に死んだと言えるのかどうか分からない子どもを死んだことにして、その臓器を移植するなんて、私にはとても考えられないのだが、この小説にはパーキンソン病の治療のために自分の胎児を早期に流産させてその脳を注入するなんていう、どこまで本当なのか分からないような話が登場する。自分の延命のためにわが子を犠牲にするのなら文句のいいようがないとでも言うのだろうか?