ジョエル・エグロフ『日当たりのよい人たち』(ロシェ書店、2000年)
Joel Egloff, Les Ensoleilles, Editions de Rocher, 2000 (Folio 3651)
 1999年8月11日の昼の12時17分から32分にかけて起きた皆既日食を観ようと右往左往する10数人のフランス人たちの様子をブラックユーモアをきかせて書いた小説。
1999年8月11日の昼の12時17分から32分にかけて起きた皆既日食を観ようと右往左往する10数人のフランス人たちの様子をブラックユーモアをきかせて書いた小説。
ヴァカンスで海辺に来ているが、ずっと雨で、ヴァカンスどころか日食も観ることができなかったのに、親戚への絵葉書には、ヴァカンスを楽しんでいるとか、日食を観たとか書いたことで妻と言い争いになる男性。
マンションから出るたびに、家の中のあらゆる道具や電化製品の電源がきってあるか、すべての窓の戸締りができているかを確かめてからでないと出かけられない強迫観念症の男性が、日食を観るためにすべての戸締りを確認してやっとマンションの外に出たところで、自分のマンションから煙が出ていることに気づくというブラックコメディー。
どこかのビーチに日焼けをしにやってきた水着姿の若い女性が、たぶん日食中だということもしらずに無頓着に振舞っている姿。
ロジェさんと呼ばれて、海辺の小さな町のカフェで、知り合いたちに人生のアドバイスをしたり、馬券のアドバイスをしたりして尊敬を得ている退職後の男が、一人の見知らぬ男の登場でその権威が失墜してしまう様子。
12時といっても夜の12時と勘違いしてしまう男もいれば、怪我をしたら危ないからと長い間外出させてもらえなかった老婆が日食を観たくて、腰も曲がっているのに杖を突きながら公園にやっとたどりついたけど、腰が曲がっていて見上げることができなかったとか。
恋人のエステルと公園の噴水の傍で待ち合わせしていたポールはずっと前から日食を観ながらエステルにプロポーズしようと決めていた。ところが時間になってもエステルが来ない。携帯をもっていないので連絡のとりようがなく、どこかで事故に遭ったのではないかと気になって、警察や病院に電話をしてみるが埒が明かない。友人のマルシアルのところに行けば助けてくれるだろうと思い、行ってみると、マルシアルのワイシャツをきてしどけない姿をしたエステルが彼のマンションにいたという、これも笑えない話。
最後は、いつも寝起きしている公園のベンチで寝ていると回りに大勢の人がやってきて日食を観ているので、それにならってグラスなしで日食をみて目をつぶしてしまった浮浪者の話でオチがついている。
このときの皆既日食はおそらくその情報がいきわたっていたこともあって、人類史上最も多数の人が観たのではないかといわれている。
つぎにヨーロッパとくにフランスで観察できる皆既日食は2081年で、そのとき自分はどうなっているだろうと死後の自分と死後の世界に思いをはせる女性の話もある。
「ずいぶん前から予想されているこのお祭り、でも私は招待されていないこのお祭りのことを考えると、私は絶望的になる。でも私がいなくてもみんなうまくやるのだろう。それがまた私を苦しめるものなのだ。私は自分自身にしか必要とされない。地球は回り続けるだろうし、月もおなじだ。太陽は光り輝いて、同じ場所で待っていればいいのだ。すべてが予想されたとおりになるだろう。私がいなくても。」(p.142)
なんだか私がいつも思う私の死後の世界と同じことが書いてあるのでびっくりした。そんな風に自分がいなくても世界が続くと考えることは辛いものだ。
タイトルはフランス語をそのまま訳したのだけど、なんか違うような気がする。
Joel Egloff, Les Ensoleilles, Editions de Rocher, 2000 (Folio 3651)
 1999年8月11日の昼の12時17分から32分にかけて起きた皆既日食を観ようと右往左往する10数人のフランス人たちの様子をブラックユーモアをきかせて書いた小説。
1999年8月11日の昼の12時17分から32分にかけて起きた皆既日食を観ようと右往左往する10数人のフランス人たちの様子をブラックユーモアをきかせて書いた小説。ヴァカンスで海辺に来ているが、ずっと雨で、ヴァカンスどころか日食も観ることができなかったのに、親戚への絵葉書には、ヴァカンスを楽しんでいるとか、日食を観たとか書いたことで妻と言い争いになる男性。
マンションから出るたびに、家の中のあらゆる道具や電化製品の電源がきってあるか、すべての窓の戸締りができているかを確かめてからでないと出かけられない強迫観念症の男性が、日食を観るためにすべての戸締りを確認してやっとマンションの外に出たところで、自分のマンションから煙が出ていることに気づくというブラックコメディー。
どこかのビーチに日焼けをしにやってきた水着姿の若い女性が、たぶん日食中だということもしらずに無頓着に振舞っている姿。
ロジェさんと呼ばれて、海辺の小さな町のカフェで、知り合いたちに人生のアドバイスをしたり、馬券のアドバイスをしたりして尊敬を得ている退職後の男が、一人の見知らぬ男の登場でその権威が失墜してしまう様子。
12時といっても夜の12時と勘違いしてしまう男もいれば、怪我をしたら危ないからと長い間外出させてもらえなかった老婆が日食を観たくて、腰も曲がっているのに杖を突きながら公園にやっとたどりついたけど、腰が曲がっていて見上げることができなかったとか。
恋人のエステルと公園の噴水の傍で待ち合わせしていたポールはずっと前から日食を観ながらエステルにプロポーズしようと決めていた。ところが時間になってもエステルが来ない。携帯をもっていないので連絡のとりようがなく、どこかで事故に遭ったのではないかと気になって、警察や病院に電話をしてみるが埒が明かない。友人のマルシアルのところに行けば助けてくれるだろうと思い、行ってみると、マルシアルのワイシャツをきてしどけない姿をしたエステルが彼のマンションにいたという、これも笑えない話。
最後は、いつも寝起きしている公園のベンチで寝ていると回りに大勢の人がやってきて日食を観ているので、それにならってグラスなしで日食をみて目をつぶしてしまった浮浪者の話でオチがついている。
このときの皆既日食はおそらくその情報がいきわたっていたこともあって、人類史上最も多数の人が観たのではないかといわれている。
つぎにヨーロッパとくにフランスで観察できる皆既日食は2081年で、そのとき自分はどうなっているだろうと死後の自分と死後の世界に思いをはせる女性の話もある。
「ずいぶん前から予想されているこのお祭り、でも私は招待されていないこのお祭りのことを考えると、私は絶望的になる。でも私がいなくてもみんなうまくやるのだろう。それがまた私を苦しめるものなのだ。私は自分自身にしか必要とされない。地球は回り続けるだろうし、月もおなじだ。太陽は光り輝いて、同じ場所で待っていればいいのだ。すべてが予想されたとおりになるだろう。私がいなくても。」(p.142)
なんだか私がいつも思う私の死後の世界と同じことが書いてあるのでびっくりした。そんな風に自分がいなくても世界が続くと考えることは辛いものだ。
タイトルはフランス語をそのまま訳したのだけど、なんか違うような気がする。










 図書館には魔物が住んでいるので、あまり長居はしないことにしているのだが、このあいだは予約本もないし、とくにあらかじめ決めた本もなかったので、うろうろしているとこれが見つかった。こういう場合に意外と掘り出しものに出会ったりするものだ。
図書館には魔物が住んでいるので、あまり長居はしないことにしているのだが、このあいだは予約本もないし、とくにあらかじめ決めた本もなかったので、うろうろしているとこれが見つかった。こういう場合に意外と掘り出しものに出会ったりするものだ。 フランスの移民政策の一つは移民も普通のフランス人と同じようにフランス語を話しフランスの国家精神を理解するというようにして、フランス人に融合することを目指しているのだが、ついこの間までまったくフランスと無縁のモラルや生活習慣や言語のなかにいた人々にそういうものを受け容れなければ、フランス人として認めないという政策は、無理があるように思う。その無理さ加減が教育に荒廃として現れているのではないだろうか。
フランスの移民政策の一つは移民も普通のフランス人と同じようにフランス語を話しフランスの国家精神を理解するというようにして、フランス人に融合することを目指しているのだが、ついこの間までまったくフランスと無縁のモラルや生活習慣や言語のなかにいた人々にそういうものを受け容れなければ、フランス人として認めないという政策は、無理があるように思う。その無理さ加減が教育に荒廃として現れているのではないだろうか。 小説家のフィリップ・クローデルが来日したらしい。しかし今回の来日は小説家としてではなくて、現在東京のほうで上映中の映画『ずっとあなたを愛している』の監督としてということらしい。最近、いくつかの新聞でこの映画のことを中心にして、もちろん彼の小説も含めて、インタビュー記事が載っていたので、来日していることを知った。
小説家のフィリップ・クローデルが来日したらしい。しかし今回の来日は小説家としてではなくて、現在東京のほうで上映中の映画『ずっとあなたを愛している』の監督としてということらしい。最近、いくつかの新聞でこの映画のことを中心にして、もちろん彼の小説も含めて、インタビュー記事が載っていたので、来日していることを知った。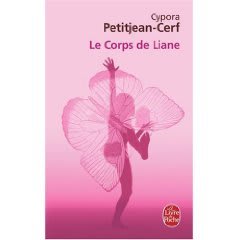 前回読んだサミラ・ベリルの自伝のすざまじく荒れた生活とはうって変わって、ほとんどたいした変化もないように見える同じ12才前後の少女とその家庭や友だちといった狭い生活圏での日常を描いた小説なのだが、なんだかクスッと笑える場面が満載で、面白かった。
前回読んだサミラ・ベリルの自伝のすざまじく荒れた生活とはうって変わって、ほとんどたいした変化もないように見える同じ12才前後の少女とその家庭や友だちといった狭い生活圏での日常を描いた小説なのだが、なんだかクスッと笑える場面が満載で、面白かった。 もうブルターニュに帰るとユゲットお祖母ちゃんが言い出したころ。その頃、ロズリンは母親が家事と育児を放棄していたので、リアーヌの家に寝泊りしていた。
もうブルターニュに帰るとユゲットお祖母ちゃんが言い出したころ。その頃、ロズリンは母親が家事と育児を放棄していたので、リアーヌの家に寝泊りしていた。 14才のときに集団による暴力、レイプ、輪姦に三度もあい、その精神的後遺症に苦しみ続け、やっと25才でこの本を書くことでそれから自分の解放することができた女性のドキュメントである。
14才のときに集団による暴力、レイプ、輪姦に三度もあい、その精神的後遺症に苦しみ続け、やっと25才でこの本を書くことでそれから自分の解放することができた女性のドキュメントである。 医者の家長(という言い方がまさにまだフランスで活きていた時代の話なので)を中心とした大人数家族の末っ子のファニーの視点から見た父ルイ・デルヴァスや母親、兄弟姉妹の旧弊な世界を描いたもの。
医者の家長(という言い方がまさにまだフランスで活きていた時代の話なので)を中心とした大人数家族の末っ子のファニーの視点から見た父ルイ・デルヴァスや母親、兄弟姉妹の旧弊な世界を描いたもの。 産院での医療過誤から誕生後数時間(実際は出産時に死亡していた)しか生きられなかったわが子フィリップの出産をめぐる数日そして出産前後の数時間のことを体験記風に綴った小説。
産院での医療過誤から誕生後数時間(実際は出産時に死亡していた)しか生きられなかったわが子フィリップの出産をめぐる数日そして出産前後の数時間のことを体験記風に綴った小説。 女優をしているエリザベトとラジオ・フランスのパーソナリティーをしているクララという二人の女性の、それぞれの夫パスカルと愛人のボリスとのかかわりをとうして、フランス人女性の不幸なありようを描いた小説。
女優をしているエリザベトとラジオ・フランスのパーソナリティーをしているクララという二人の女性の、それぞれの夫パスカルと愛人のボリスとのかかわりをとうして、フランス人女性の不幸なありようを描いた小説。 エリザベトは二人の子どもを早退させて連れ出し、ラジオ・フランスで働いているクララのところへ行き、泊めてくれるように頼む。全てを察したクララは「あなた、自分のしたことが分かっているの?」と言いつつも受け容れてくれた。
エリザベトは二人の子どもを早退させて連れ出し、ラジオ・フランスで働いているクララのところへ行き、泊めてくれるように頼む。全てを察したクララは「あなた、自分のしたことが分かっているの?」と言いつつも受け容れてくれた。 幼かった頃に母親を亡くし、その理由だけでなく、なぜかしら母親の顔も写真も姿もすべて思い出をなくしてしまった女性が、父親の死の直前にその母親が別の男を愛していたことを知らされ、その男に会いに出かけ、画家だった母親の形見の絵をもらいうけるという話を一人称で綴った物語。
幼かった頃に母親を亡くし、その理由だけでなく、なぜかしら母親の顔も写真も姿もすべて思い出をなくしてしまった女性が、父親の死の直前にその母親が別の男を愛していたことを知らされ、その男に会いに出かけ、画家だった母親の形見の絵をもらいうけるという話を一人称で綴った物語。 ペーパーバックス版の裏表紙に書かれた作品の一部だが、30歳にもなって、母親探し?って思うかもしれないが、どうやら母親が不倫をしていたことを知っていた父親が、彼女の死後に形見のもの、彼女の思い出を全て家の中から取り去ってしまったことから、母親の思い出がほとんどないという不幸な経験をしたことが、一人称でたんたんと語られていく。
ペーパーバックス版の裏表紙に書かれた作品の一部だが、30歳にもなって、母親探し?って思うかもしれないが、どうやら母親が不倫をしていたことを知っていた父親が、彼女の死後に形見のもの、彼女の思い出を全て家の中から取り去ってしまったことから、母親の思い出がほとんどないという不幸な経験をしたことが、一人称でたんたんと語られていく。 ロレーヌ地方のある山岳地帯の村幼少の頃に母親と移り住んできたブロデックが、ユダヤ人狩りにやってきたナチスの軍隊におびえた村人たちから「生贄」にされ、強制収容所送りにされてしまう。だが生き延びるために「犬」にまでなったブロデックはそこから生き延びてもどってきた。戦争も終わり村もやっと落ち着いた頃にやってきた一人の男、何をしに、どこからやってきたのかも、いったい何者なのかも分からない一人の男のために、疑心暗鬼になった村人たちは、この男がブロデックを収容所送りにして、逃げてきた三人の女性を殺したことを告発しにきたと思い込み、彼を惨殺してしまう。その顛末を報告書に書くことになったブロデックの回想の物語が、これである。
ロレーヌ地方のある山岳地帯の村幼少の頃に母親と移り住んできたブロデックが、ユダヤ人狩りにやってきたナチスの軍隊におびえた村人たちから「生贄」にされ、強制収容所送りにされてしまう。だが生き延びるために「犬」にまでなったブロデックはそこから生き延びてもどってきた。戦争も終わり村もやっと落ち着いた頃にやってきた一人の男、何をしに、どこからやってきたのかも、いったい何者なのかも分からない一人の男のために、疑心暗鬼になった村人たちは、この男がブロデックを収容所送りにして、逃げてきた三人の女性を殺したことを告発しにきたと思い込み、彼を惨殺してしまう。その顛末を報告書に書くことになったブロデックの回想の物語が、これである。