ミシェル・ウェルベック『服従』(河出書房新社、2015年)
 近未来の2022年のフランス大統領選挙の第一回投票で、移民排斥を訴えて急伸した国民戦線のマリーヌ・ル・ペン(実在の政党で実在の党首)とイスラム同胞党のモアメド・ベン・アッベス(フィクションの政党で党首)が第一と第二になり、決選投票になる。フランス人は、ファシストかイスラム主義者かという選択を迫られることになる。
近未来の2022年のフランス大統領選挙の第一回投票で、移民排斥を訴えて急伸した国民戦線のマリーヌ・ル・ペン(実在の政党で実在の党首)とイスラム同胞党のモアメド・ベン・アッベス(フィクションの政党で党首)が第一と第二になり、決選投票になる。フランス人は、ファシストかイスラム主義者かという選択を迫られることになる。
この小説ではイスラム主義者のモアメド・ベン・アッベスが大統領になり、大学はイスラム化されて、イスラム教徒でなければ教員になれない。そのため主人公のフランソワは、まだ40代なのに(定年まで働いた場合と同じだけの)高額の年金をもらって退職するが、学長になったルディジェに説得されてイスラム教徒に改宗して大学教員に戻ることになる。
実際の議論は見ていないが、たぶんいろいろ議論のあるところだろう。たとえば、このような究極の選択を前にして、社会党(現在のオランド大統領の政党)やUMP(サルコジの支持基盤政党)がファシストよりはイスラム主義者のほうがましと考えるだろうか。フランス人のイスラム感情が根強いとすれば、棄権して、どちらの政権ができても打倒のための戦いを起こすだろうか。国民戦線にせよイスラム主義者にせよ、政権を取れば、そんな簡単に引き下がるわけがない。たぶん強権的な態度にでるだろうから、内戦のようになるのではないか。しかし今の国民に、社会党にそんな根性があるのか。
こんな小説を書き始めた限りは、ウェルベックは内戦という究極の結論も念頭にあったはずだが、彼はそんな結論にはしないで、大方の国民はおとなしくイスラム主義政権に「服従」するという結論にした。早い話が、フランス式の「長いものには巻かれろ」という物語である。
私にはまったく腰砕けの展開としか思えない。ある意味、ミシェル・ウェルベックもつまらないものを書くようになったなとがっかりするばかりだ。
 近未来の2022年のフランス大統領選挙の第一回投票で、移民排斥を訴えて急伸した国民戦線のマリーヌ・ル・ペン(実在の政党で実在の党首)とイスラム同胞党のモアメド・ベン・アッベス(フィクションの政党で党首)が第一と第二になり、決選投票になる。フランス人は、ファシストかイスラム主義者かという選択を迫られることになる。
近未来の2022年のフランス大統領選挙の第一回投票で、移民排斥を訴えて急伸した国民戦線のマリーヌ・ル・ペン(実在の政党で実在の党首)とイスラム同胞党のモアメド・ベン・アッベス(フィクションの政党で党首)が第一と第二になり、決選投票になる。フランス人は、ファシストかイスラム主義者かという選択を迫られることになる。この小説ではイスラム主義者のモアメド・ベン・アッベスが大統領になり、大学はイスラム化されて、イスラム教徒でなければ教員になれない。そのため主人公のフランソワは、まだ40代なのに(定年まで働いた場合と同じだけの)高額の年金をもらって退職するが、学長になったルディジェに説得されてイスラム教徒に改宗して大学教員に戻ることになる。
実際の議論は見ていないが、たぶんいろいろ議論のあるところだろう。たとえば、このような究極の選択を前にして、社会党(現在のオランド大統領の政党)やUMP(サルコジの支持基盤政党)がファシストよりはイスラム主義者のほうがましと考えるだろうか。フランス人のイスラム感情が根強いとすれば、棄権して、どちらの政権ができても打倒のための戦いを起こすだろうか。国民戦線にせよイスラム主義者にせよ、政権を取れば、そんな簡単に引き下がるわけがない。たぶん強権的な態度にでるだろうから、内戦のようになるのではないか。しかし今の国民に、社会党にそんな根性があるのか。
こんな小説を書き始めた限りは、ウェルベックは内戦という究極の結論も念頭にあったはずだが、彼はそんな結論にはしないで、大方の国民はおとなしくイスラム主義政権に「服従」するという結論にした。早い話が、フランス式の「長いものには巻かれろ」という物語である。
私にはまったく腰砕けの展開としか思えない。ある意味、ミシェル・ウェルベックもつまらないものを書くようになったなとがっかりするばかりだ。










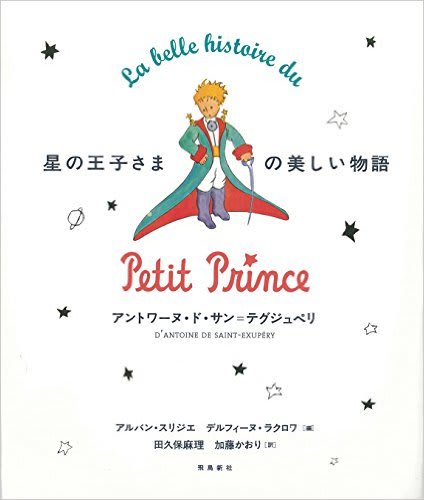 『星の王子さま』は1943年4月16日にアメリカでフランス語版と英語版が出版された。この本はそれから70週年を記念した特別版の翻訳である。『星の王子さま』全文の前後に、ゆかりの人々のコメントや論文、そして未発表のデッサンが収録されている。
『星の王子さま』は1943年4月16日にアメリカでフランス語版と英語版が出版された。この本はそれから70週年を記念した特別版の翻訳である。『星の王子さま』全文の前後に、ゆかりの人々のコメントや論文、そして未発表のデッサンが収録されている。 グルネル通り七番地という、パリの高級住宅街にある金持ちたちが住むアパルトマンの管理人をしている中年女性ルネとそこに住む金持ちの一人の娘パルマの語りによる物語。
グルネル通り七番地という、パリの高級住宅街にある金持ちたちが住むアパルトマンの管理人をしている中年女性ルネとそこに住む金持ちの一人の娘パルマの語りによる物語。 なんだかウェルベックもずいぶんと丸くなったなと思う。『戦線を拡大せよ』や『素粒子』や『プラットフォーム』の、あのタブーをタブーとも思わない、シニカルな態度はこの小説ではほとんど姿を消してしまったように見える。
なんだかウェルベックもずいぶんと丸くなったなと思う。『戦線を拡大せよ』や『素粒子』や『プラットフォーム』の、あのタブーをタブーとも思わない、シニカルな態度はこの小説ではほとんど姿を消してしまったように見える。 原文で読んだ時の感想は
原文で読んだ時の感想は 以前に(このブログを読み直したら、なんと2007年だった)読んだアメリー・ノートンの『畏れ慄いて』が翻訳で出ているので読んでみた。また後で感想を書こうと思っているが、じつは『チューブな形而上学』の翻訳が出ているのを、最近知ったので、急にアメリー・ノートンへの関心が再び湧いてきて、図書館で借りようと思ったら、これしかなかった。
以前に(このブログを読み直したら、なんと2007年だった)読んだアメリー・ノートンの『畏れ慄いて』が翻訳で出ているので読んでみた。また後で感想を書こうと思っているが、じつは『チューブな形而上学』の翻訳が出ているのを、最近知ったので、急にアメリー・ノートンへの関心が再び湧いてきて、図書館で借りようと思ったら、これしかなかった。


 あの名優ジェラール・フィリップの妻だったという女性作家の小説。だからといってどうということはないのだが、ジェラール・フィリップ云々よりも、その詩情あふれる文章が出色の作品。
あの名優ジェラール・フィリップの妻だったという女性作家の小説。だからといってどうということはないのだが、ジェラール・フィリップ云々よりも、その詩情あふれる文章が出色の作品。 15歳で高校一年生の「僕」は3年前から始めたブログを父のフィリップが何も言わずに秘かに読んでいたことを知って、激怒し、口もきかなくなる。母のとりなしで、休戦状態になったが、父がノートや写真の入った古い箱を「僕」に渡す。それらのノートには父が高校生の頃に書いたと思われる日記や小説のようなものが書かれていて、「僕」はそれを読んで、何度も捨てようと思うのだが、徐々に惹かれていく。毎夜、自分の部屋で読むのが楽しくなってくる。ついにはそこに出てくる高校生たち全員と友だちになったような錯覚さえ生まれるようになるのだった。
15歳で高校一年生の「僕」は3年前から始めたブログを父のフィリップが何も言わずに秘かに読んでいたことを知って、激怒し、口もきかなくなる。母のとりなしで、休戦状態になったが、父がノートや写真の入った古い箱を「僕」に渡す。それらのノートには父が高校生の頃に書いたと思われる日記や小説のようなものが書かれていて、「僕」はそれを読んで、何度も捨てようと思うのだが、徐々に惹かれていく。毎夜、自分の部屋で読むのが楽しくなってくる。ついにはそこに出てくる高校生たち全員と友だちになったような錯覚さえ生まれるようになるのだった。