阿部共実「空が灰色だから」4巻読了(★後半短編集に関して追記しました)。
璃瑚奈ちゃんの気持ちも実は結構分かるんですよね・・・(笑
同じような固定観念、共通観念を浴びせられ続けると「そうだよなあ」と思う一方で
「息苦しいなあ」って思ってしまうのも人間なんですよね。一つの枠しか選択出来ないような感覚。
ただ、安易に批判的な目線になるのではなく、結局「動いてないから」って批判に対する注意も盛り込まれてる
その中立的な感覚こそがこの漫画の良い部分なんじゃないかなあ、と改めて感じられた巻でした
ニヒルに気取っていても傍から観れば滑稽なだけだったり
想像の世界でいくら楽しんでも現実に還元する事は一切なかったり
誰かに教えを与える偉そうな態度を取っていても、結局はストレスの捌け口でしかない
そういう一面性を徹底的に排除した作りには本当に感心させられますね
要するに、美も醜も同時に存在させている
人間らしさを追求している
それがエンターティメントなのかと問われれば間違いなくNOですけど
表現として考えればこれだけ個性的な作品も珍しいんじゃないかと個人的には思います
つまりは、今回も水準以上に面白く楽しめたという話ですね。この漫画で描かれている人間の殆どが
一言で形容すれば滑稽なだけの人間ですけど、それは理想を排除した生々しい姿でもあって
そういう意味じゃ物凄く良くも悪くも現実感に溢れた漫画なんですけど
それもまた認めるべきなんですよね。
誰も彼もが全員きれいにまっとうに生きてる訳ないですからね。
本当は見えないところで色々やってたり考えてたりするもんなんですよ。
そういう部分を描いてるのがこの漫画です。
・・・っていうのが分かりやすいかな
なまじ読み手の日常に近いからこそ、妙な親近感が沸いて堪らない、そんな作品でもありますね。
インパクトやペーソス的には3巻のが爆発してましたが、その分4巻では徹底して「弱者」に焦点を絞って
多角度から人間の「弱さ」を描いていた印象ですね。それはコメディ話であってもね。
「想像」、という言葉がありますけど
マシンガン娘のお話は正にそんな言葉を彷彿とさせる傑作回でした
あの話で描きたかった事を個人的に解釈するならば、人の言葉や態度なんてものは
それだけを切り取れば印象に付ければ単なる一面的なものに過ぎない
でも裏では水面下ではもっと複雑な感情が蠢いてるもの
だから切れ端で判断するのは止めよう
そのまま受け取るのは止めよう
思考停止ではなく、想像を膨らまして考えてあげよう・・・ってそんなメッセージ性を感じました
同時にそれは人間は思った以上に脆弱で抱えてしまう生き物って事実でもあるんですが
かといって、直せない癖はいつまで経っても直らないものですから
半永久的に本音と建前の間で苦しむしかない
それは悲しい事ですけど
結果的にはそれを受け入れて何とか生きている彼女の姿
それは傍目から観ている以上に尊いものなんだなあ、と個人的には思いました
「上手く行かない」事が「当たり前」の我々の日常、それをナチュラルにポンポンとここまで描けている
それは安定なんて言葉で済ましては本当はいけないんだろうな、と
まあ安定してるとは思うんですが(笑
しかしまあ、それを維持してる事自体が凄い。
今回も全体的に滑稽で、でも滑稽だからこそ憎めない連中ばかり
それは自分の体験の一部一部を作品から垣間見るようで気持ち悪くも気持ち良い妙な感覚
この感覚こそがこの漫画の一番の武器なんだと確信出来た4巻目になってました。
アネゴのその後も気になってしまうのですが・・・(笑
半ばストレス解消だったとは言え、
褒められた行為じゃないにしても
それでも根底にはわずかな優しさがあったんじゃないかなあ、と思う
でも子供にそういう気持ちが理解出来る訳はないですよね。全く、救われて欲しい人物ばかりの漫画だぜ(笑
だからその後を想像したりするのも楽しい漫画になってるんじゃないかなあ、とも思いました。
第43話の「膨らんだ」に関して言えば、
理想を押し付けてそれと違ったら有無を言わさずシャットアウト
勿論間には事件もあったんでしょうが「人間」ではなく「人形」を求める残酷性が良く出ていて
でもそれは誰しもがそういう面があるんだよ・・・と本質的なオチになってたのが見事でした
決して読んでて気分の良い話ではないんですけど(笑
でも、そういう話にはそういう話なりのカタルシスがある事も知って欲しいですね。
★追記:大好きが虫はタダシくんの
短編集も購入して読みました
基本的に空灰の延長線上ですが「ドラゴンスワロウ」は連作なので回を増す毎のデレが楽しめたり
表題作はこの作者ならではの伝家の宝刀って感じで良い具合に切ない余韻を残す良作
漫才ネタに関しても「ならでは」という印象で読み応えは抜群でした
この漫画が好きなら多分普通に気に入ると思います
まあ、そもそも空灰自体がオムニバスなのでそこまで印象の違いが目立つ訳ではないんですけど(笑
作品としては良作揃いだった印象ですね。という訳で是非2冊味わって頂ければ。
















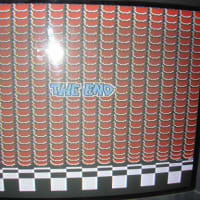

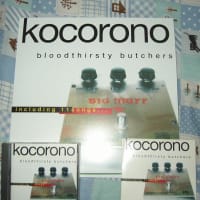

かわいらしい絵柄を灰色基軸アートチックに描かれる、笑・毒・猛毒・閉塞感・不安・恐怖・現実・恋・愛。
様々な人の心が紡ぐ様々な迷宮模様。たどり着いた先には希望か救いか絶望か未だに迷宮を歩き続けるのか・・・つまりは”人生そのもの”を特異な視点で描いたヒューマンサスペンス&ホラー&コメディ(つまりジャンル分け不可能)
確かに誰もが楽しめるエンターテイメントとは程遠いですが、少年誌でどこにでもいる人の心を突き詰めるだけでこんなにも深いドラマが生まれるという証明をした希有な傑作だと思いますよ。安易なありたきり勧善懲悪超人解決作品よりも遙かに価値があるかと(ちなみに武富健治の「鈴木先生」という作品がありましてベクトル・表現は全く違えど空灰に通じる様々な人の心が紡ぐ身近で深く壮大なドラマ。実に良質な作品ですので未見ならば是非)
私は現実と人間をちゃんと描ける作家・描けている作品というのが琴線を奏でられるタイプの人間のようで。
この作品内に登場する少年少女ときどき姉さん母さんの心の葛藤・揺らぎの生々しさ、そしてそれが作り上げる現実のドライな対応が帰結が素敵すぎて堪りませんね。
マシンガン少女も幽霊少女もアネゴも妄想姉弟もどこか可笑しく、そして愚かしく切なく愛おしい。
そして今回遂に発売された短編収「大好きが虫はタダシくんの」も大変よろしかった。最初からもうすでにこの作家さんの作風が出来ていたんだなぁとの発見と同時に長編もちゃんと描ける人であることが分かったのも大きな発見でした(でもどちらかというと短編の方が好きなのです。この人の資質は長編よりも短編が何よりも生きるタイプなのだと個人的に思います)中でも個人的に良かったのは雑誌デビュー作の「破壊症候群」(読んでいる途中「ワンパンマン」という漫画を思い出してしまった 笑。それにしても虫人間達を殴るたびに手の皮がむけて肉が見えていくいくあの生々しさときたら・・・ひぇぇ)そして表題作かつ私が阿倍共実先生という才能を知った傑作「大好きが虫はタダシくんの」これをピクシブで初めて読んだときの衝撃は忘れられません。特異な障害により(アスペルガーか自閉症か聴覚処理障害になった少女の話かと思ったのですが阿倍先生いわく『実際にある障害や病気を参考やモチーフにはしていない』とのことでした)かつて友達だった少女や他者とのコミュニーケーションがとれず離れていき凄まじい孤独の中で泣きながら帰る少女のあの切実で深いやるせない悲しさといったら・・・。
阿倍共実先生はどんな進化を遂げるか。どのような作品を書いていくのか。非常に楽しみな作家さんの一人です。でも作風を見る限り結構心を追い詰めて書いていくタイプの作家さんに見えるので、心を変に追い詰めて精神を病んでいかないようにして欲しいですね・・・。
個人的にはある程度現実感を感じさせる描写は必要だと思っているんですが
全部が全部現実的でもつまんないなー、とか思っちゃうタイプなんです
それを考えるとこの漫画の描き方は正に「ちょうどいい」
現実感と漫画感の中間を往く私好みの作品だとつくづく思います(笑
個人的にはエンターティメントとドキュメントのどっちかに表現は分けられると思っていて
この漫画は明らかにドキュメント側だと思います
近年そういう立ち位置の作品が少年誌では少なくなってきた事もあり
良い具合にカウンターとして機能してるのではないでしょうか
多分我々の日常に近い登場人物たちだと思うので
いとおしく思ってしまうのも必然かと
今回も大満足の一冊でした。
長編に関しては、意外とちゃんとしたオチが付いてたのに感心しました
ただゆるゆるやってるだけじゃなくて、地道に名前を呼べるようになってた
イコール距離が縮まってたんだな、と(笑
そういう部分が面白かったです
今は短編で名を馳せてますけど
いつかはこの方の長編も読んでみたいですね。割と読み心地的には変わらなかったので
いずれ新境地を拓く時を期待しています。
実際にある病気・・・というよりは「個性」を認めない世の中に向けての疑問や
マイノリティである事によって苦しめられている人々への
処方箋としてこの漫画は成り立っている気はします
自分が見てきた限りこの国の人々は連帯感と共通認識が大好きなご様子なので
そういう輪の中に入れない人にとっては確実に響く漫画なのではないでしょうか
こういう存在もいるんだよ、ってサインでもあるんですよね。
そこを拾い上げてくれる漫画はやはり貴重です。
>心を変に追い詰めて精神を病んでいかないようにして欲しいですね・・・。
個人的には暗い漫画ばかり描いてる訳ではないので割と自分を持ってる方なのだと思います
ネガティブではなくシビアな見方というか。
その上でハッピーなだけのお話も描ける懐の深さもあるので案外絶望だけの人ではないんじゃないかと
久米田康治に近いものを感じますね。