「ヤマギシズム社会の実態」
「解説 ヤマギシズム社会の実態(一)
「第一章 概要」
「三 機構と人情社会に」
この「機構と人情社会に」のなかの、次の一節がこれまで何回も読んできて、好きだった。
「・・無軌道では混乱し、事が運びませんから、真の人間向きの、間違いない機構・制度を確立します。
しかし、そうして立派な道路機構が出来ても、同じ道を行く人の間に、他の人を跳ねとばし、白眼で
見交す冷たい気分があれば、決して愉快な人生旅行は出来ません。また、道を尋ねられても、
自分は自分、ひとはひとと、他に関せずの個人主義も、実は社会が自分一人限りのものでなく、必ず
何かで他の人との関連があり、人間は相対的であって、吾一人行かんも程度の差こそあれ、帰結する
ところ、他との保ち合いで人生が有意義になります。
本当に人間は一人になり切れるものでなく、そこに人の情が自ずと湧いてくるものです。
道連れ話し相手があると、遠路も忘れて愉快に過ごし、汽車や船で長旅すると、未知の人ともいつか
言葉を交し親しくなり、路傍で見かけただけの間柄でも、遠い他国で相逢うと、近親感を覚え語り合う
ようになり、純な子ども達が、特に早く馴染むのは自然の人の姿でしょう。
世に鬼のように云われる冷血漢でも、家庭ではよき夫であったり、やさしい父として心中に涙する
こともあります」
”他との保ち合いで人生が有意義になります”
”そこに人の情が自ずと湧いてくるものです”
このように表現されている中身は、どんなことだろうと、これまでも考えてきた。
サイエンズカレッジの検討会で、杉江さんが、「ここに、近親感って、書いてあるんだよね」と
ポツリと言った。
たしかに「近親感」と書いてある。
「あれ、ここ、じぶんは、どう読んできたかな。・・どうも親近感と読んできて、違和感が
起きなかった」
だれかが、「以前、誤植だと言っていた人がいた」と。
辞書には「近親感」というコトバは出てこない。
山岸さんは、機構の大事さを何回も繰り返し、言っている。
なんで、そこまで機構・制度の大事さを強調するのか。
人間とはどういうものか?
人と人で構成する社会は、人間とはどういうものかという見え方捉え方如何によって、
顕れてくる姿は、大きく変わるだろう。
”人の情が自ずから湧いてくる”
これをじぶんのなかに見て行くと、そいういものの実在を感じることが出来る。
我が子に対する気持ち、これも頭で考える以前に、じぶんのなかで湧いているものが
あるのを感じる。なにかで、妨げないかぎり。
我が子でない人には、湧いてくるものを感じないか?
どうなんだろう?
なにかで、心を閉ざしていないかぎり、我が子に対する気持ちに近いもの、もしくはほとんど
同じものが、じぶんのなかにあるのを感じる。
この辺を表現しようとしたら、「親近感」ではうまいこと、言い表せない。
「近親感」の方が、聞きなれないけど、よりじぶんの気持ちのありように近い。
そういう内実を心身ともに内に秘めている人間が、人間らしく、その人らしく、成長し、暮らす
には、個人の努力や精進だけではならないだろう。
そういう人と人が、その内実が、他から妨げられることなく発露し、発揮し得る、そういう仲間が
欲しくなるだろう。
でもそれだけなら、まだ足りないものを感じる。そういうことが、どの人も、そうしようとしたら、
容易に出来る機構や仕組みが不可欠になるのではないか。
これまで時間をかけて作ってきた機構・制度を前提にして、その改善だけでなるだろうか?
出発は、人間とはどういうものかの究明。
その究明に応じて、そういう人間が、そういう人生が実現し得る社会,機構や仕組みの究明。
そういう順序。
機構・制度は大事。身体の健康や物の豊満も、人が人らしく生きていくのに欠かせない。
でも、それだけでは解決できないものがある。
「しかも幸福条件には、心の豊かさが主要部分を占め、幸福なる人生を理想とする社会構成は、
人間愛の基調の上に組み立てねばならないのです」
”心の豊かさが主要部分を占め・・”
ここ、じぶんや周囲の人について、どう見ているか?
ここは、じぶんや、人ということで、もっとしらべていかないと見えてこないのでは・・
「こういうことは、今までに云い尽くされていましょうが・・」
そうだね、ほんとに、いままでも、どこでも、こういうことは言われてきたし、
じぶんでも思ってきた。
”人間愛”を、人がもともと心身ともに、健康正常になっていこうという作用を内在しているもの
というところに基盤をおくなら、そこをもとにして「幸福条件の凡てに、積極具現方式を採用したのです」
と山岸さんが言われていることがどんなことか、自分の目に見えてこないか、そこに焦点が当たってくる。
これは、社会に問題があるから、それを解決しようというところからでは、見えてこないのでは。
戦争が起こる現状を前提にして、仲良くしよう、平和になろうとしても、なかなかならないもの。
震災で、絆や、人と人のつながりや、暮らしの見直しが言われているけど、そこを考えている、
自分の出発しているところは、どこだろう。
震災でも、原発事故でも、大いに関心がある。
その関心の、わが身のなかの出所は?
この辺の究明、いま自分の中で動き始めたのを感じる。
「解説 ヤマギシズム社会の実態(一)
「第一章 概要」
「三 機構と人情社会に」
この「機構と人情社会に」のなかの、次の一節がこれまで何回も読んできて、好きだった。
「・・無軌道では混乱し、事が運びませんから、真の人間向きの、間違いない機構・制度を確立します。
しかし、そうして立派な道路機構が出来ても、同じ道を行く人の間に、他の人を跳ねとばし、白眼で
見交す冷たい気分があれば、決して愉快な人生旅行は出来ません。また、道を尋ねられても、
自分は自分、ひとはひとと、他に関せずの個人主義も、実は社会が自分一人限りのものでなく、必ず
何かで他の人との関連があり、人間は相対的であって、吾一人行かんも程度の差こそあれ、帰結する
ところ、他との保ち合いで人生が有意義になります。
本当に人間は一人になり切れるものでなく、そこに人の情が自ずと湧いてくるものです。
道連れ話し相手があると、遠路も忘れて愉快に過ごし、汽車や船で長旅すると、未知の人ともいつか
言葉を交し親しくなり、路傍で見かけただけの間柄でも、遠い他国で相逢うと、近親感を覚え語り合う
ようになり、純な子ども達が、特に早く馴染むのは自然の人の姿でしょう。
世に鬼のように云われる冷血漢でも、家庭ではよき夫であったり、やさしい父として心中に涙する
こともあります」
”他との保ち合いで人生が有意義になります”
”そこに人の情が自ずと湧いてくるものです”
このように表現されている中身は、どんなことだろうと、これまでも考えてきた。
サイエンズカレッジの検討会で、杉江さんが、「ここに、近親感って、書いてあるんだよね」と
ポツリと言った。
たしかに「近親感」と書いてある。
「あれ、ここ、じぶんは、どう読んできたかな。・・どうも親近感と読んできて、違和感が
起きなかった」
だれかが、「以前、誤植だと言っていた人がいた」と。
辞書には「近親感」というコトバは出てこない。
山岸さんは、機構の大事さを何回も繰り返し、言っている。
なんで、そこまで機構・制度の大事さを強調するのか。
人間とはどういうものか?
人と人で構成する社会は、人間とはどういうものかという見え方捉え方如何によって、
顕れてくる姿は、大きく変わるだろう。
”人の情が自ずから湧いてくる”
これをじぶんのなかに見て行くと、そいういものの実在を感じることが出来る。
我が子に対する気持ち、これも頭で考える以前に、じぶんのなかで湧いているものが
あるのを感じる。なにかで、妨げないかぎり。
我が子でない人には、湧いてくるものを感じないか?
どうなんだろう?
なにかで、心を閉ざしていないかぎり、我が子に対する気持ちに近いもの、もしくはほとんど
同じものが、じぶんのなかにあるのを感じる。
この辺を表現しようとしたら、「親近感」ではうまいこと、言い表せない。
「近親感」の方が、聞きなれないけど、よりじぶんの気持ちのありように近い。
そういう内実を心身ともに内に秘めている人間が、人間らしく、その人らしく、成長し、暮らす
には、個人の努力や精進だけではならないだろう。
そういう人と人が、その内実が、他から妨げられることなく発露し、発揮し得る、そういう仲間が
欲しくなるだろう。
でもそれだけなら、まだ足りないものを感じる。そういうことが、どの人も、そうしようとしたら、
容易に出来る機構や仕組みが不可欠になるのではないか。
これまで時間をかけて作ってきた機構・制度を前提にして、その改善だけでなるだろうか?
出発は、人間とはどういうものかの究明。
その究明に応じて、そういう人間が、そういう人生が実現し得る社会,機構や仕組みの究明。
そういう順序。
機構・制度は大事。身体の健康や物の豊満も、人が人らしく生きていくのに欠かせない。
でも、それだけでは解決できないものがある。
「しかも幸福条件には、心の豊かさが主要部分を占め、幸福なる人生を理想とする社会構成は、
人間愛の基調の上に組み立てねばならないのです」
”心の豊かさが主要部分を占め・・”
ここ、じぶんや周囲の人について、どう見ているか?
ここは、じぶんや、人ということで、もっとしらべていかないと見えてこないのでは・・
「こういうことは、今までに云い尽くされていましょうが・・」
そうだね、ほんとに、いままでも、どこでも、こういうことは言われてきたし、
じぶんでも思ってきた。
”人間愛”を、人がもともと心身ともに、健康正常になっていこうという作用を内在しているもの
というところに基盤をおくなら、そこをもとにして「幸福条件の凡てに、積極具現方式を採用したのです」
と山岸さんが言われていることがどんなことか、自分の目に見えてこないか、そこに焦点が当たってくる。
これは、社会に問題があるから、それを解決しようというところからでは、見えてこないのでは。
戦争が起こる現状を前提にして、仲良くしよう、平和になろうとしても、なかなかならないもの。
震災で、絆や、人と人のつながりや、暮らしの見直しが言われているけど、そこを考えている、
自分の出発しているところは、どこだろう。
震災でも、原発事故でも、大いに関心がある。
その関心の、わが身のなかの出所は?
この辺の究明、いま自分の中で動き始めたのを感じる。










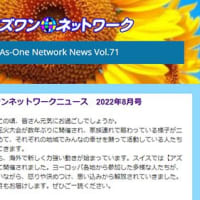






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます