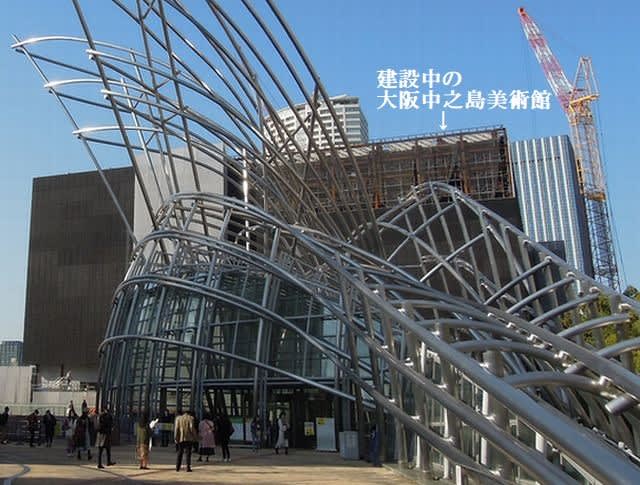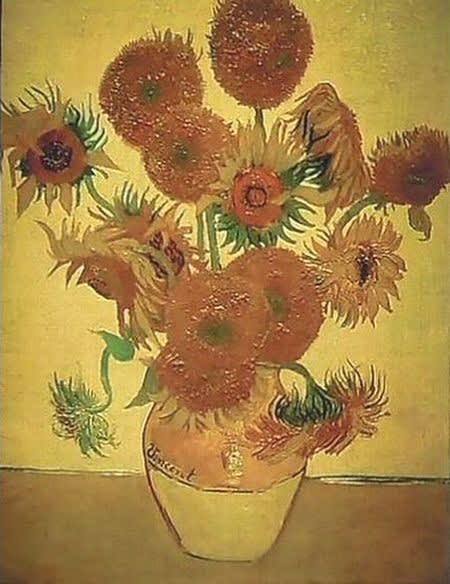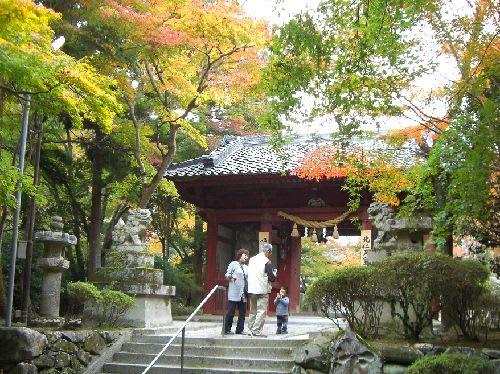諏訪神社で昼食をとり、諏訪神社にあった「川久保尋常小学校」が
磐手尋常小学校と合併した「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ行きます。
帰りのバスの時間を見ると・・・
川久保バス停留所 時刻表

JR高槻駅まで、13時07分のバスに乗って帰るのですが・・・
そのバスに乗り遅れると、15時37分までありません。
でもバスの時間までは、たっぷりと時間があるので
「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ向かいます。

川久保分教場跡へは「落合橋」を渡って直進ですが
左折すると「西教寺」へ行きます。

川久保分校(分教場)は
1905年9月15日 に、三島郡川久保尋常小学校として再独立。

校庭の端に、窯のようなものがありますが
新しいように見えます。

あっ!「二宮金次郎」さんの銅像があります。
以前に来た時は、気付かなかったので驚きました!
最近は見ることがない「二宮金次郎」さんなので
こうして残っているのは嬉しいですね。(^^♪

戦前の川久保地区は、林業が盛んで、くぬぎ、こなら等の雑木林が多く・・・
秋になれば、松茸は嫌になるほど取れた時もあるマッタケ山だったそうです。
松くい虫の被害などもあり、松茸は駄目になったそうです。
松くい虫の被害が無ければ、高槻の松茸が食べられたんですね~
嫌になるほど・・・食べたかったですね~ (^^ゞ

「かみおちあいはし」の手前まで戻ってきました。
橋の手前を右折して「西教寺」へ向かいます。

川面に紅葉は、絵になりますね。

この先の右に見える建物が

「西教寺」さんでした。
中には入らないので・・・

バス停に向かいます。

バス停前に戻ってきました。
川久保に流れる水は本当にきれいです。

まだ出発時間まで時間があるので
近くを散策・・・

陽の当たる紅葉に・・・

日陰の紅葉・・・や

根っこなどを見ていると
人の世を垣間見ているような気分に・・・(^^ゞ

「原立石」バス停留所からスタートして
牛地蔵→神峯山寺の紅葉→川久保までのハイキングは終わります。
磐手尋常小学校と合併した「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ行きます。
帰りのバスの時間を見ると・・・
川久保バス停留所 時刻表

JR高槻駅まで、13時07分のバスに乗って帰るのですが・・・
そのバスに乗り遅れると、15時37分までありません。
でもバスの時間までは、たっぷりと時間があるので
「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ向かいます。

川久保分教場跡へは「落合橋」を渡って直進ですが
左折すると「西教寺」へ行きます。

川久保分校(分教場)は
1905年9月15日 に、三島郡川久保尋常小学校として再独立。

校庭の端に、窯のようなものがありますが
新しいように見えます。

あっ!「二宮金次郎」さんの銅像があります。
以前に来た時は、気付かなかったので驚きました!
最近は見ることがない「二宮金次郎」さんなので
こうして残っているのは嬉しいですね。(^^♪

戦前の川久保地区は、林業が盛んで、くぬぎ、こなら等の雑木林が多く・・・
秋になれば、松茸は嫌になるほど取れた時もあるマッタケ山だったそうです。
松くい虫の被害などもあり、松茸は駄目になったそうです。
松くい虫の被害が無ければ、高槻の松茸が食べられたんですね~
嫌になるほど・・・食べたかったですね~ (^^ゞ

「かみおちあいはし」の手前まで戻ってきました。
橋の手前を右折して「西教寺」へ向かいます。

川面に紅葉は、絵になりますね。

この先の右に見える建物が

「西教寺」さんでした。
中には入らないので・・・

バス停に向かいます。

バス停前に戻ってきました。
川久保に流れる水は本当にきれいです。

まだ出発時間まで時間があるので
近くを散策・・・

陽の当たる紅葉に・・・

日陰の紅葉・・・や

根っこなどを見ていると
人の世を垣間見ているような気分に・・・(^^ゞ

「原立石」バス停留所からスタートして
牛地蔵→神峯山寺の紅葉→川久保までのハイキングは終わります。