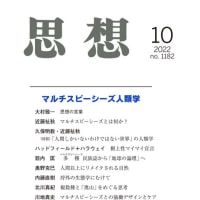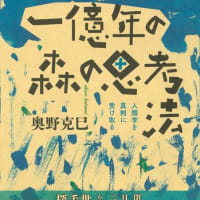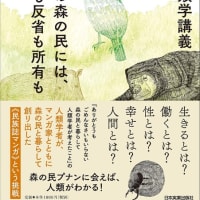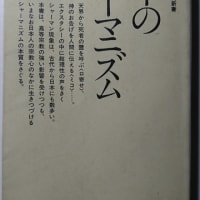先週の土日、I先生から誘われて、「コミュニティにもとづく参加型調査」(Community-Based Participatory Research, CBPR)のワークショップに参加した。
http://cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/CBPR2008_Japan.html
開き直って、「未開のスペシャリスト」であると自称する、わたしのような野蛮な人類学者が参加してもいいものかどうか、不安になって、I先生に、あらかじめ電話で尋ねたが、あなたにも何らかの役割があるだろうという微妙な返事だったので、余計に不安を抱きつつ参加したが、結論から述べると、ひじょうに得るところの多い、考えさせられる、チャレンジングなワークショップだった。
日本の地方都市で、日系人が抱える苦悩と問題に寄り添い、「確信犯的に」メディアや展示をつうじて、問題解決へと上昇していこうとする人類学者I先生の試みを、わたしは当初、人類学の延長線上で捉えていたが、それを、人類学という学問の枠組みを超え出てゆこうとする社会活動の文脈で考えれば、すんなりと理解できるどころか、じつに、有用な取り組みであるように思える。また、医療の文脈で、日系人の通訳を職業として確立することを訴えたMさんは、日系人の増加に伴って、今後ますます深刻化するであろう課題を、生々しい現場主義の観点から、報告してくれた。これらの取り組みの報告は、ことのほか、興味深いものだった。
さらに、「コミュニティにもとづく参加型調査(CBPR)」について、Jさんは、時間をかけて、丁寧に教えてくれた。教えてくれたというよりも、全員参加で、浮かび上がらせるためのファシリテータのような役割を担ってくれた。その意味で、CBPRの導入そのものが、全員参加で行なわれるという、じつに、手の込んだワークショップだったように思う。ある意味で、レクチャーが先にあってもよかったのかもしれないとも考えられるが、Jさんは、CBPRを実践するために、あえて、レクチャー・スタイルを自らに禁じたのかもしれない。CBPRは、時間がかかる(がゆえに、実りがあるのであろう)活動であるということも、同時に、わたしたちは知りえたように思う。
ところで、CBPRとは何か?それは、社会的格差がある状況で、その問題を解決するための調査&実践であると、わたしなりにまとめておきたい。社会的格差の状況の調査を行なっている専門家、研究者は、その問題状況を抱える人たちと、当該問題について話し合い、生の現実に十分に照らしながら、問題の解決を図るというのが、CBPRの手続きの柱である。専門家、調査者の視点というのは、それだけで、はじめから権威化されている。そのことをわきまえた上で、専門家、調査者は、問題状況を共有すべく、コミュニティに入り、教えるという態度ではなく、ともに問題とその解決について考えるという態度で、調査と実践の制度を高めていくというのが、わたしが感じたCBPRの手続きである。
その意味で、CBPRは、人にやさしい調査&実践の手法である。専門家、調査者は、ジャーゴンを使わないで、自らが客観的な観察者であるという尊大な態度を廃して、調査&実践に臨むことを要請される。Jさんによれば、どうやら、デモクラシーの実現という理想が、その手法には深く関わっているようだった。他方で、一部の(乱暴な)研究者たち(わたしを含む)がやり始めたように、「それはおかしい」「愚問だ」と口々に言い合いながら、真っ向から議論をするという研究者の議論のスタイルもまた、デモクラシーかもしれないと、ふと感じた。
新たな調査研究のありかたについて、とりあえずの感想。
(写真:CBPRのワークショップでは、わたしたちは、参加しながら学んでいった。「参加」とは何かについて、メンバーは、ホワイトボードに絵を描いた)