夫のいとこたちで結成されているいとこ会の恒例行事である餅つき大会。
毎年12月に開催されるビッグイベントだ。
昨年は年末に開催予定が、諸事情から延期となり、年明け2月に開催された。
出入りはあるものの、20人は集まっていただろうか。
男性陣は早めに会場入りして、もろもろスタンバイ。
前回、前々回は我が家の隣の親戚の家(空き家)が会場だったので、実質我が家が幹事状態。
私は2年連続、前日にもち米を20kg研ぐ、という使命があったが、
今年は別のイトコのお宅が会場だったので、余裕を持ってゆっくりと参加。
私の役割は、例年のし餅作り。

つきたてのお餅をのし餅用の袋に入れ、ひたすらめん棒で伸ばす。
毎年やってるので、ずいぶん手際もよくなった。
全部で18枚、無事に出来上がる。

のし餅のほかにも、つきたてのお餅で、あんこ餅、きな粉餅、大根おろしにからめた絡み餅、納豆餅など
女性のイトコ達がどんどん作っていく。

男性陣はひたすらお餅をつき続ける。
通りすがりの親子連れも飛び入り参加して、楽しんでいた。

餅つきが終わると、おでんを囲んで打ち上げ宴会の始まり

みんなの近況などを報告したりしながら、ゆったりと時は過ぎていく。
いつもは14時には解散するこの会だが、今日は、イトコのリーダーがなぜか16時までやろう!と宣言したので、
私は内心ドキドキだ
なぜなら、夫と私はこのあと押尾コータローのクリスマスコンサートに行かねばならない。
開演は18時。
会場は渋谷。
16時に終わると結構ヤバい
お開きの後、急いで帰って、粉だらけの服を着替え、コンサート会場である渋谷文化村オーチャードホールに着いたのは開演5分前。
よかった、間に合った
押尾さんのコンサートは通常一人だけれど、この日は弦楽四重奏も一緒。
一人の時とは違った雰囲気。
ふと見ると第一バイオリン奏者の金髪に見覚えが・・・。
ライブイマージュのレギュラーメンバー、NAOTOさんだ
なんだかちょっと得した気分。
クリスマスの定番、「ラスト・クリスマス」や
コンサートでは必ず演奏する「戦場のメリークリスマス」の「Merry Christmas Mr.Lawrence」
がクリスマス気分を盛り上げる。
「Merry Christmas Mr.Lawrence」のアレンジが今までと違う気がしていたら、夫も同じことを言っていた。
一人で演奏しているとは思えない「ボレロ」も圧巻だ。
母への感謝をこめた「Mother」でラストを締めくくり、じ~んとした気持ちのまま、アンコールへ。
アンコール1曲目の「Big Blue Ocean」では観客が一つになってのウェーブ。
ただ、私達は3階席だったので、今一つタイミングがあわず・・・。
2曲目はジョン・レノンの「Happy Christmas(War is over)」。
War is over~の部分を観客が大合唱。
世界の平和を願う気持ちが会場にあふれる。
そしてホントに最後の曲は「美しき人生」
温かい気持ちに満たされて、コンサートは終わった。
早朝からばたばたの1日で、全身ボロボロに疲れていて、コンサートで寝ちゃうんじゃないかと思ったけれど、
ちゃんと最後まで、ステキな演奏を堪能しました。
長い長い一日だったけれど、心地よい夜を過ごすことができて、満足満足
年末に向けてもうひと頑張りしないと・・・。
毎年12月に開催されるビッグイベントだ。
昨年は年末に開催予定が、諸事情から延期となり、年明け2月に開催された。
出入りはあるものの、20人は集まっていただろうか。
男性陣は早めに会場入りして、もろもろスタンバイ。
前回、前々回は我が家の隣の親戚の家(空き家)が会場だったので、実質我が家が幹事状態。
私は2年連続、前日にもち米を20kg研ぐ、という使命があったが、
今年は別のイトコのお宅が会場だったので、余裕を持ってゆっくりと参加。
私の役割は、例年のし餅作り。

つきたてのお餅をのし餅用の袋に入れ、ひたすらめん棒で伸ばす。
毎年やってるので、ずいぶん手際もよくなった。
全部で18枚、無事に出来上がる。

のし餅のほかにも、つきたてのお餅で、あんこ餅、きな粉餅、大根おろしにからめた絡み餅、納豆餅など
女性のイトコ達がどんどん作っていく。

男性陣はひたすらお餅をつき続ける。
通りすがりの親子連れも飛び入り参加して、楽しんでいた。

餅つきが終わると、おでんを囲んで打ち上げ宴会の始まり


みんなの近況などを報告したりしながら、ゆったりと時は過ぎていく。
いつもは14時には解散するこの会だが、今日は、イトコのリーダーがなぜか16時までやろう!と宣言したので、
私は内心ドキドキだ

なぜなら、夫と私はこのあと押尾コータローのクリスマスコンサートに行かねばならない。
開演は18時。
会場は渋谷。
16時に終わると結構ヤバい

お開きの後、急いで帰って、粉だらけの服を着替え、コンサート会場である渋谷文化村オーチャードホールに着いたのは開演5分前。
よかった、間に合った

押尾さんのコンサートは通常一人だけれど、この日は弦楽四重奏も一緒。
一人の時とは違った雰囲気。
ふと見ると第一バイオリン奏者の金髪に見覚えが・・・。
ライブイマージュのレギュラーメンバー、NAOTOさんだ

なんだかちょっと得した気分。
クリスマスの定番、「ラスト・クリスマス」や
コンサートでは必ず演奏する「戦場のメリークリスマス」の「Merry Christmas Mr.Lawrence」
がクリスマス気分を盛り上げる。
「Merry Christmas Mr.Lawrence」のアレンジが今までと違う気がしていたら、夫も同じことを言っていた。
一人で演奏しているとは思えない「ボレロ」も圧巻だ。
母への感謝をこめた「Mother」でラストを締めくくり、じ~んとした気持ちのまま、アンコールへ。
アンコール1曲目の「Big Blue Ocean」では観客が一つになってのウェーブ。
ただ、私達は3階席だったので、今一つタイミングがあわず・・・。
2曲目はジョン・レノンの「Happy Christmas(War is over)」。
War is over~の部分を観客が大合唱。
世界の平和を願う気持ちが会場にあふれる。
そしてホントに最後の曲は「美しき人生」
温かい気持ちに満たされて、コンサートは終わった。
早朝からばたばたの1日で、全身ボロボロに疲れていて、コンサートで寝ちゃうんじゃないかと思ったけれど、
ちゃんと最後まで、ステキな演奏を堪能しました。
長い長い一日だったけれど、心地よい夜を過ごすことができて、満足満足

年末に向けてもうひと頑張りしないと・・・。











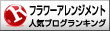








































































 と。
と。




