抜けるような青空の下、夫と私は喪服を着て、歩いて5分のお寺へと向かう。
この日は、隣に住んでいた、夫の親戚のおじいさんの七回忌だ。
夫やその家族は「おじさん」と呼んでいたが、実際は伯父ではなく義父のイトコにあたる人。
早くに父親を亡くした義父は義祖母と一緒に、本家であるこのおじさんの家で、大人になるまで兄弟のように暮らしたらしい。
私が夫と結婚したとき、義父はすでに病床についており、そののち20余年間介護が必要な生活を送ることとなる。
その間「おじさん」は夫の家族のことを気にかけてくれ、何かと面倒を見てくれていた。
ひょんなことから「おじさん」の土地に建物を建てるお手伝いをすることになり、
いつのまにか、お隣にすむようになっていた。
ある日、たまたま用事があって声をかけたら、体調を崩してこたつの中でぐったりしていたのを発見して以来3年間ほど、
介護っぽいことをすることになった。
介護と言っても、週に何日かの夕食運びや、病院の送迎、ヘルパーさんの手配など、
世間一般の介護をしている方に比べたらほんのプチ介護だ。
生涯独身で、一人で生きる覚悟を決めていた「おじさん」は決して甘えない。
基本的に自分でできることは自分でやり、いよいよの時だけ私たちが手を貸す。
具合が悪くてもとことんまで我慢するので、即入院って時もあった。
戦争中、シベリアに抑留されていたというから、我慢強さもハンパじゃない。
腰が痛い、と言うので、整形外科に連れて行ったり、内科にも行ったりしたけれど、80歳を過ぎるとだいたい老化で片付けられて
ちゃんと検査もしてもらえないうちに、ある年の大晦日、突然、モノが呑み込めない、と言う。
年越しそばを1cm位のぶつ切りにしてもだめ、飲み物も受け付けない。
お正月が明けて、病院に行ったらそのまま入院。
末期の胃がんだとわかり、1か月もたたないうちに亡くなってしまった。
きっとものすごく痛かったに違いないのに、そんな風に見せなかったのもすごいし、
ほとんど私たちに面倒をかけず、財産の処理もきちんと済ませていてあっぱれな最期だった。
もう丸6年もたったんだな~と月日の流れの早さをじわ~っとかみしめながら、お寺のご住職のお話を聞く。
あのとき中学の合唱大会を途中で抜け出して告別式に参列した次男も成人式を迎えた。
声が大きく、滑舌のいい、浄土宗のご住職が「明るく、楽しく、仲良く」と繰り返しおっしゃっている。
お焼香とは、香を焚いた後の煙が故人を供養しているらしい。
自分の知っている故人だけでなく、そのずっと前に亡くなったたくさんのご先祖の誰が欠けても
あなたがこの世に存在しなかったことを感じて、ご先祖様にも思いを馳せてほしいともおっしゃる。
このお寺のご住職のお話はとても分かりやすい。
お寺は数年前に建て替えたばかりで、新しくて、きれい。
本堂の天井に描かれている現世の季節の花や鳥、極楽の色鮮やかな世界。
ちょっと普段目にしない幻想的な雰囲気にしばし引き込まれていたけれど、
現実的な夫やその家族に「行くよ!」と言われて、本堂を出る。
ここで、写経でも教えていただきたいくらいだ。
お墓にお参りし、11人だけのこじんまりとしたお食事会もあっという間に終わり、七回忌は無事に終了。
お隣はずっと空き家のままだけれど、昨年に引き続き、2月に夫のイトコ会主催の餅つき大会の会場となる。
生前、私が次男と一緒に夕食を運んでいくと、お年寄りにも容赦ないヘビーなおかずでも、
こたつに入ってテレビを見ながら、にこにこと「ありがとう」と言ってくれる。
次男がこたつにもぐりこみ、「こっちの方がおもしろいよ」と勝手にアニメにチャンネルを変えるのを、
これまたにこにこと見ている姿を思い出すと、今でもちょっと切なくなる。
あんなふうに歳をとりたいな~と思う今日この頃である。
この日は、隣に住んでいた、夫の親戚のおじいさんの七回忌だ。
夫やその家族は「おじさん」と呼んでいたが、実際は伯父ではなく義父のイトコにあたる人。
早くに父親を亡くした義父は義祖母と一緒に、本家であるこのおじさんの家で、大人になるまで兄弟のように暮らしたらしい。
私が夫と結婚したとき、義父はすでに病床についており、そののち20余年間介護が必要な生活を送ることとなる。
その間「おじさん」は夫の家族のことを気にかけてくれ、何かと面倒を見てくれていた。
ひょんなことから「おじさん」の土地に建物を建てるお手伝いをすることになり、
いつのまにか、お隣にすむようになっていた。
ある日、たまたま用事があって声をかけたら、体調を崩してこたつの中でぐったりしていたのを発見して以来3年間ほど、
介護っぽいことをすることになった。
介護と言っても、週に何日かの夕食運びや、病院の送迎、ヘルパーさんの手配など、
世間一般の介護をしている方に比べたらほんのプチ介護だ。
生涯独身で、一人で生きる覚悟を決めていた「おじさん」は決して甘えない。
基本的に自分でできることは自分でやり、いよいよの時だけ私たちが手を貸す。
具合が悪くてもとことんまで我慢するので、即入院って時もあった。
戦争中、シベリアに抑留されていたというから、我慢強さもハンパじゃない。
腰が痛い、と言うので、整形外科に連れて行ったり、内科にも行ったりしたけれど、80歳を過ぎるとだいたい老化で片付けられて
ちゃんと検査もしてもらえないうちに、ある年の大晦日、突然、モノが呑み込めない、と言う。
年越しそばを1cm位のぶつ切りにしてもだめ、飲み物も受け付けない。
お正月が明けて、病院に行ったらそのまま入院。
末期の胃がんだとわかり、1か月もたたないうちに亡くなってしまった。
きっとものすごく痛かったに違いないのに、そんな風に見せなかったのもすごいし、
ほとんど私たちに面倒をかけず、財産の処理もきちんと済ませていてあっぱれな最期だった。
もう丸6年もたったんだな~と月日の流れの早さをじわ~っとかみしめながら、お寺のご住職のお話を聞く。
あのとき中学の合唱大会を途中で抜け出して告別式に参列した次男も成人式を迎えた。
声が大きく、滑舌のいい、浄土宗のご住職が「明るく、楽しく、仲良く」と繰り返しおっしゃっている。
お焼香とは、香を焚いた後の煙が故人を供養しているらしい。
自分の知っている故人だけでなく、そのずっと前に亡くなったたくさんのご先祖の誰が欠けても
あなたがこの世に存在しなかったことを感じて、ご先祖様にも思いを馳せてほしいともおっしゃる。
このお寺のご住職のお話はとても分かりやすい。
お寺は数年前に建て替えたばかりで、新しくて、きれい。
本堂の天井に描かれている現世の季節の花や鳥、極楽の色鮮やかな世界。
ちょっと普段目にしない幻想的な雰囲気にしばし引き込まれていたけれど、
現実的な夫やその家族に「行くよ!」と言われて、本堂を出る。
ここで、写経でも教えていただきたいくらいだ。
お墓にお参りし、11人だけのこじんまりとしたお食事会もあっという間に終わり、七回忌は無事に終了。
お隣はずっと空き家のままだけれど、昨年に引き続き、2月に夫のイトコ会主催の餅つき大会の会場となる。
生前、私が次男と一緒に夕食を運んでいくと、お年寄りにも容赦ないヘビーなおかずでも、
こたつに入ってテレビを見ながら、にこにこと「ありがとう」と言ってくれる。
次男がこたつにもぐりこみ、「こっちの方がおもしろいよ」と勝手にアニメにチャンネルを変えるのを、
これまたにこにこと見ている姿を思い出すと、今でもちょっと切なくなる。
あんなふうに歳をとりたいな~と思う今日この頃である。











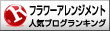






 と驚いたものだ。
と驚いたものだ。
































