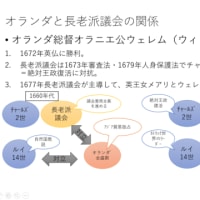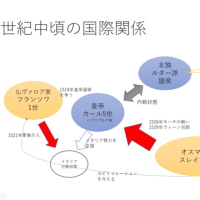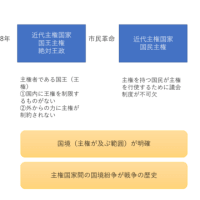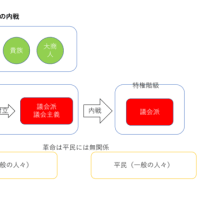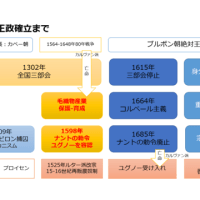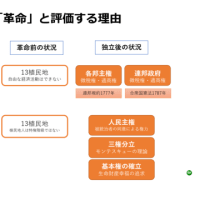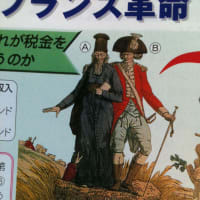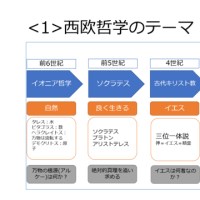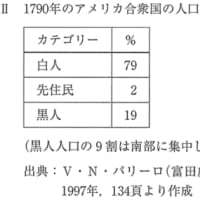2017東京大学世界史問題
問題文最初の2行が解答に至る鍵になっている。
この出題者は、帝国の共通点が現代にもつながっているという。グローバル世界における帝国の概念はグローバル企業などに連なっているから、古代から現代に続く共通点は普遍性だと解る。個々の民族や地域性や宗教などを超越した普遍が存在し、普遍性こそが古代から現代グローバル世界に繋がる帝国の概念だと考える。
この文脈に従ってローマ帝国を見ていく。しかしここで問題になるのが、いつまで書くのか?つまりローマ帝国は皇帝の性格が変容するからドミナートゥスまで書くべきかを検討する必要がある。その判断を可能にするのは、社会変化という単語。ローマの市民権拡大については指定語句から書くべきだと判断できるから、212年アントニヌス勅令は書くことになる。一方、ドミヌスは奴隷の主人という意味。皇帝が自由人を奴隷扱いしているが、皇帝の神格化によりローマ市民権を得た全ての自由人より超越する。この段階で皇帝が普遍性を持った。プリンキパトゥスは市民権を持つ人々の代表だったが、ドミヌスは市民を超越して神格化することで普遍的存在となった。それはローマ理念を代表するといえる。その意味でヨーロッパの皇帝はローマ帝国皇帝の権威を継承する。それは地理的概念ではなくローマ帝国の普遍性を示す概念で、中華という地理的概念を含む中国の皇帝とは明らかに異なる。
では、そこに至るまでの普遍性は何か?属州にいた異民族や異教徒にまでが持つ普遍性はローマ市民権。半島の自由人に広がった市民権はやがて全自由人に広がり、帝国の普遍に参加することを意味させた。ゲルマン移動期にローマ帝国の人々と彼らを分けたのは帝国に参加していた、つまりローマ市民権を持っていたという自覚だろう。
しかし、世界史ではローマ市民権の拡大までの期間は社会変化を扱わない。従って、形式的にせよ維持されていた共和制体が打ち切られ、属州は再分割され総督の権限は縮小し、官僚制によって帝国を維持するという社会の大変革まで書く必要があるとわかる。
またローマ市民権の他にも帝国の普遍は考えられる。それはラテン語だろう。ラテン語が持つ普遍性は古代から中世ヨーロッパに連なり、現代でも書き言葉として学術的には維持されている。指定語句に漢字があるが、ラテン語についても書く必要がある。
問題文最初の2行が解答に至る鍵になっている。
この出題者は、帝国の共通点が現代にもつながっているという。グローバル世界における帝国の概念はグローバル企業などに連なっているから、古代から現代に続く共通点は普遍性だと解る。個々の民族や地域性や宗教などを超越した普遍が存在し、普遍性こそが古代から現代グローバル世界に繋がる帝国の概念だと考える。
この文脈に従ってローマ帝国を見ていく。しかしここで問題になるのが、いつまで書くのか?つまりローマ帝国は皇帝の性格が変容するからドミナートゥスまで書くべきかを検討する必要がある。その判断を可能にするのは、社会変化という単語。ローマの市民権拡大については指定語句から書くべきだと判断できるから、212年アントニヌス勅令は書くことになる。一方、ドミヌスは奴隷の主人という意味。皇帝が自由人を奴隷扱いしているが、皇帝の神格化によりローマ市民権を得た全ての自由人より超越する。この段階で皇帝が普遍性を持った。プリンキパトゥスは市民権を持つ人々の代表だったが、ドミヌスは市民を超越して神格化することで普遍的存在となった。それはローマ理念を代表するといえる。その意味でヨーロッパの皇帝はローマ帝国皇帝の権威を継承する。それは地理的概念ではなくローマ帝国の普遍性を示す概念で、中華という地理的概念を含む中国の皇帝とは明らかに異なる。
では、そこに至るまでの普遍性は何か?属州にいた異民族や異教徒にまでが持つ普遍性はローマ市民権。半島の自由人に広がった市民権はやがて全自由人に広がり、帝国の普遍に参加することを意味させた。ゲルマン移動期にローマ帝国の人々と彼らを分けたのは帝国に参加していた、つまりローマ市民権を持っていたという自覚だろう。
しかし、世界史ではローマ市民権の拡大までの期間は社会変化を扱わない。従って、形式的にせよ維持されていた共和制体が打ち切られ、属州は再分割され総督の権限は縮小し、官僚制によって帝国を維持するという社会の大変革まで書く必要があるとわかる。
またローマ市民権の他にも帝国の普遍は考えられる。それはラテン語だろう。ラテン語が持つ普遍性は古代から中世ヨーロッパに連なり、現代でも書き言葉として学術的には維持されている。指定語句に漢字があるが、ラテン語についても書く必要がある。