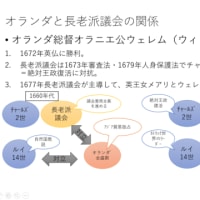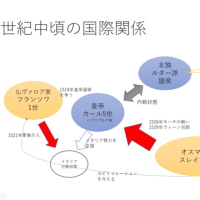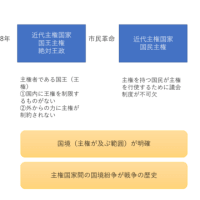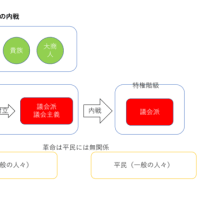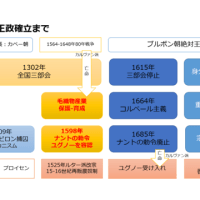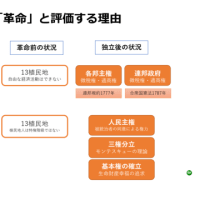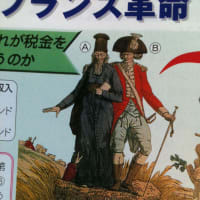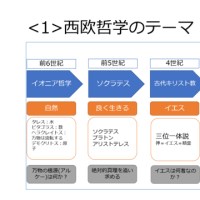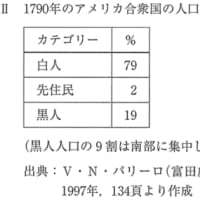2017東京大学世界史問題秦漢
中国について300字で論述することになる。問題文には長江流域を含めた中国とある。この部分が解答の鍵になる。長江流域には楚があり、秦による統一に最後まで抵抗した。楚は統一まで異なる文化圏を形成していた。
中国の皇帝は秦の始皇帝から出現したが、その意味は北極星。宇宙の中心の意味。これには地理的概念が含まれる。従って、中華がどこからどこまでを指すのか?が帝国には重要になる。ここで指定語句の漢字を使う。つまり漢字文化圏に参加している地域が中華に帰属する。ただし、古代帝国の時代にはまだ日本や朝鮮は漢字文化圏には入らない。余談だが、これらの周辺国まで中華に帰属させる国際関係を冊封という。
以上のことから、中国では帝国の地理的概念がどのように拡大していったのか、言い方を変えれば中華の範囲がどのように拡大していったのか?を考えていくことになる。このことを論述するのは重要で、だからこそ春秋戦国から論述するように求めたと考えるべきだろう。
甲骨文字は殷の王族が独占していた。一般の人々は甲骨文字を知らなかった。この文字の独占が殷末に崩れ、周が表意文字である漢字を使って殷の支配下にあった部族と同盟し殷を滅ぼした。当時、各部族は異文化圏で言葉も通じなかったが漢字が彼らの世界すなわち中華を成立させた。殷が周辺の部族を厳しく差別した時代が終わり、周による緩やかな連合体である中華が生まれ、ここから習俗も言語も異なる部族を内含する帝国のような中華が成立した。その意味で出題者は、周から書き始めさせた。だが、皇帝の称号はまだない。
以上みたように、周になるとこれらが一つの文化圏として犬戎などの異文化部族と対抗した。しかし、それぞれの旧部族に対する周の統治は間接的でそれぞれの部族を支配する諸侯と部族は宗族法で結びついていた。各個別に存在していた部族を宗族という。これが周の封建制。このように周では漢字が普遍性を示したが、戦国時代には各国が自立し漢字も幾種類か存在し普遍性を失った。
秦は中華の辺境に位置していたが、中国を統一すると自らを中華とした。社会の仕組みも大きく変化させ、宗族を解体する郡県制を採用した。前漢になると古い宗族の支配者は豪族として郷挙里選を通じて王朝に参加した。またそれぞれ各地の習俗や特徴ある文化は徐々に薄れていく。このような社会変化を象徴する出来事が始皇帝による漢字の統一だろう。始皇帝は各地さまざまに使用されていた漢字や度量衡を統一し、さらに郡県制で各地さまざまの独自制を排除した。
中国について300字で論述することになる。問題文には長江流域を含めた中国とある。この部分が解答の鍵になる。長江流域には楚があり、秦による統一に最後まで抵抗した。楚は統一まで異なる文化圏を形成していた。
中国の皇帝は秦の始皇帝から出現したが、その意味は北極星。宇宙の中心の意味。これには地理的概念が含まれる。従って、中華がどこからどこまでを指すのか?が帝国には重要になる。ここで指定語句の漢字を使う。つまり漢字文化圏に参加している地域が中華に帰属する。ただし、古代帝国の時代にはまだ日本や朝鮮は漢字文化圏には入らない。余談だが、これらの周辺国まで中華に帰属させる国際関係を冊封という。
以上のことから、中国では帝国の地理的概念がどのように拡大していったのか、言い方を変えれば中華の範囲がどのように拡大していったのか?を考えていくことになる。このことを論述するのは重要で、だからこそ春秋戦国から論述するように求めたと考えるべきだろう。
甲骨文字は殷の王族が独占していた。一般の人々は甲骨文字を知らなかった。この文字の独占が殷末に崩れ、周が表意文字である漢字を使って殷の支配下にあった部族と同盟し殷を滅ぼした。当時、各部族は異文化圏で言葉も通じなかったが漢字が彼らの世界すなわち中華を成立させた。殷が周辺の部族を厳しく差別した時代が終わり、周による緩やかな連合体である中華が生まれ、ここから習俗も言語も異なる部族を内含する帝国のような中華が成立した。その意味で出題者は、周から書き始めさせた。だが、皇帝の称号はまだない。
以上みたように、周になるとこれらが一つの文化圏として犬戎などの異文化部族と対抗した。しかし、それぞれの旧部族に対する周の統治は間接的でそれぞれの部族を支配する諸侯と部族は宗族法で結びついていた。各個別に存在していた部族を宗族という。これが周の封建制。このように周では漢字が普遍性を示したが、戦国時代には各国が自立し漢字も幾種類か存在し普遍性を失った。
秦は中華の辺境に位置していたが、中国を統一すると自らを中華とした。社会の仕組みも大きく変化させ、宗族を解体する郡県制を採用した。前漢になると古い宗族の支配者は豪族として郷挙里選を通じて王朝に参加した。またそれぞれ各地の習俗や特徴ある文化は徐々に薄れていく。このような社会変化を象徴する出来事が始皇帝による漢字の統一だろう。始皇帝は各地さまざまに使用されていた漢字や度量衡を統一し、さらに郡県制で各地さまざまの独自制を排除した。