朝日新聞ブログ「ベルばらkidsぷらざ」に連載中の「世界史レッスン」第40回目の今日は、「ヨーゼフ2世、水戸黄門になる」。⇒http://bbkids.cocolog-nifty.com/bbkids/2006/11/post_e065.html#more
ヨーゼフ2世は死後、水戸黄門とよく似た伝説の主になりましたが、かなり笑えるそのエピソードについて書きました。お読みください。
さてこのヨーゼフ2世、ミロシュ・フォアマン監督の映画「アマデウス」で、ひどくたどたどしくピアノを弾いていたが、実際の彼にはもう少し演奏技術があったといわれている。まんざら聴く耳をもっていなかったわけでもないことも、次のエピソードが証明していよう。
1782年、宮廷からの要請で、モーツァルトとクレメンティ(イタリアの作曲家)がピアノ競演をしたときのこと。優劣を争う正式な競技とは違い、あくまで娯楽の一環ではあったが、それでもそれぞれに応援団がついた。華麗なテクニックを誇るクレメンティの方が腕は上、と評価した人が多かった。
これに関して当時の人気作曲家ディッタースドルフが、ヨーゼフ2世と次のような会話をしたと、自伝に書いている。
ヨーゼフ「モーツァルトの演奏を聴いたことがあるか?」
ディッタースドルフ「3度ほどございます」
J「クレメンティは?」
D「聴きました」
J「彼の方がモーツァルトより優れていると申す者がいるが、どうか?忌憚なく述べよ」
D「クレメンティの演奏で優っているのはテクニックだけです。モーツァルトにはテクニックに加えて、音楽の趣というものがございます」
J「余もそう思う」
ただしヨーゼフがモーツァルトのよりサリエーリのオペラの方を好んでいたのは間違いない。「後宮からの誘拐」は音符が多すぎると思ったし、「フィガロの結婚」は長すぎて退屈し、あくびをこらえきれなかった。
まあ、わからないでもありません。妹の嫁いだ隣国では革命間近、自国の経済も逼迫と、政治で頭が一杯の彼には、せめてオペラは肩の凝らない気楽なものの方がいい。くたびれたサラリーマンがスポーツニュースを、くたびれたOLが恋愛ドラマを見る余力しか残っていないようなもので・・・
わたし?くたびれたときは清水義範を読んでウフフと笑っています。
☆新著「怖い絵」(朝日出版社)
☆☆アマゾンの読者評で、この本のグリューネヴァルトの章を読んで「泣いてしまいました」というのがありました。著者としては嬉しいことです♪
①ドガ「エトワール、または舞台の踊り子」
②ティントレット「受胎告知」
③ムンク「思春期」
④クノップフ「見捨てられた街」
⑤ブロンツィーノ「愛の寓意」
⑥ブリューゲル「絞首台の上のかささぎ」
⑦ルドン「キュクロプス」
⑧ボッティチェリ「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」
⑨ゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」
⑩アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディト」
⑪ホルバイン「ヘンリー8世像」
⑫ベーコン「ベラスケス<教皇インノケンティウス10世像>による習作」
⑬ホガース「グラハム家の子どもたち」
⑭ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」
⑮グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」
⑯ジョルジョーネ「老婆の肖像」
⑰レーピン「イワン雷帝とその息子」
⑱コレッジョ「ガニュメデスの誘拐」
⑲ジェリコー「メデュース号の筏」
⑳ラ・トゥール「いかさま師」
♪「メンデルスゾーンとアンデルセン」書評⇒http://www.meiji.ac.jp/koho/meidaikouhou/20060501/0605_10_booknakano.html
ヨーゼフ2世は死後、水戸黄門とよく似た伝説の主になりましたが、かなり笑えるそのエピソードについて書きました。お読みください。
さてこのヨーゼフ2世、ミロシュ・フォアマン監督の映画「アマデウス」で、ひどくたどたどしくピアノを弾いていたが、実際の彼にはもう少し演奏技術があったといわれている。まんざら聴く耳をもっていなかったわけでもないことも、次のエピソードが証明していよう。
1782年、宮廷からの要請で、モーツァルトとクレメンティ(イタリアの作曲家)がピアノ競演をしたときのこと。優劣を争う正式な競技とは違い、あくまで娯楽の一環ではあったが、それでもそれぞれに応援団がついた。華麗なテクニックを誇るクレメンティの方が腕は上、と評価した人が多かった。
これに関して当時の人気作曲家ディッタースドルフが、ヨーゼフ2世と次のような会話をしたと、自伝に書いている。
ヨーゼフ「モーツァルトの演奏を聴いたことがあるか?」
ディッタースドルフ「3度ほどございます」
J「クレメンティは?」
D「聴きました」
J「彼の方がモーツァルトより優れていると申す者がいるが、どうか?忌憚なく述べよ」
D「クレメンティの演奏で優っているのはテクニックだけです。モーツァルトにはテクニックに加えて、音楽の趣というものがございます」
J「余もそう思う」
ただしヨーゼフがモーツァルトのよりサリエーリのオペラの方を好んでいたのは間違いない。「後宮からの誘拐」は音符が多すぎると思ったし、「フィガロの結婚」は長すぎて退屈し、あくびをこらえきれなかった。
まあ、わからないでもありません。妹の嫁いだ隣国では革命間近、自国の経済も逼迫と、政治で頭が一杯の彼には、せめてオペラは肩の凝らない気楽なものの方がいい。くたびれたサラリーマンがスポーツニュースを、くたびれたOLが恋愛ドラマを見る余力しか残っていないようなもので・・・
わたし?くたびれたときは清水義範を読んでウフフと笑っています。
☆新著「怖い絵」(朝日出版社)
☆☆アマゾンの読者評で、この本のグリューネヴァルトの章を読んで「泣いてしまいました」というのがありました。著者としては嬉しいことです♪
①ドガ「エトワール、または舞台の踊り子」
②ティントレット「受胎告知」
③ムンク「思春期」
④クノップフ「見捨てられた街」
⑤ブロンツィーノ「愛の寓意」
⑥ブリューゲル「絞首台の上のかささぎ」
⑦ルドン「キュクロプス」
⑧ボッティチェリ「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」
⑨ゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」
⑩アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディト」
⑪ホルバイン「ヘンリー8世像」
⑫ベーコン「ベラスケス<教皇インノケンティウス10世像>による習作」
⑬ホガース「グラハム家の子どもたち」
⑭ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」
⑮グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」
⑯ジョルジョーネ「老婆の肖像」
⑰レーピン「イワン雷帝とその息子」
⑱コレッジョ「ガニュメデスの誘拐」
⑲ジェリコー「メデュース号の筏」
⑳ラ・トゥール「いかさま師」
♪「メンデルスゾーンとアンデルセン」書評⇒http://www.meiji.ac.jp/koho/meidaikouhou/20060501/0605_10_booknakano.html











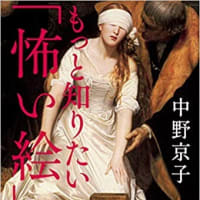








なるほど、労働で付かれきった大衆は、tvの下らないドラマ、音楽などで、憂さ晴らしをしているのですね。ドストエフスキーだの、モーツアルトだの、ましてやカントだのは、敬遠と言うか、知らない場合が多いみたい。前に、日記で書きましたが、
高校生でも、ヘミングウエイを知らないのが当たり前です。底辺高校だと、シエイクスピアの名前さえ知らないのがフツーだとか。そのくせ、「セカチュウ」とか、バンドなどには強い。学生もダメだし、文化は誰が支えているのでしょう?
むしろ彼は、母国語であるドイツ語の演劇の振興に熱心だったから、ジングシュピールも歓迎したようだし。
ただ、緊縮財政の関係もあって、派手なイタリアオペラを宮廷が抱えていられる時代ではなくなり、オペラもミサも、「短く簡潔に」という風潮はあったでしょうね。
その一方で、相変わらず、ヴィルトゥオーゾの音楽的曲芸のようなものを持て囃す人達がいる。
だから貴族たちは、時代の寵児であり、新興の母国の音楽家モーツァルトを引っ張り出しては、ピアノ演奏ではクレメンティ、オペラ作曲ではサリエリなどと競わせてみたのでしょうね。
でもそれは、ある意味では、「音楽家はイタリア人でなければ」という時代にあって、モーツァルトの天才ぶりを示すエピソード以外の何物でもないのではないでしょうか。
ただ、ディッテルスドルフが自伝に書いた回想は、文字通り受け取っていいかどうか、私はちょっと疑問。
というのは、モーツァルトは、もちろんウィーン定住時代も寵児ではあったのですが、死後の名声はそれを上回っていたように思うからです。
ニッセンが伝記を書き、コンスタンツェは遺児のクサーヴァーは、「ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト・ジュニア」として売り出す。
そういう、モーツァルトが「大作曲家」になった時代に、ディッテルスドルフが、亡き大作曲家と啓蒙君主の想い出を脚色しているように思えてなりません。
ちなみに、私は前回のウィーン資料研究滞在で、1817~1821年のケルンテン門脇宮廷オペラ劇場が、チケットの売り上げを当時の財務省に報告した文書を調査していて、改めてびっくりしたのです。
当時、1回の公演のチケットの売り上げが1000フローリンを超えると、まずは「大ヒット」。ところが、その大ヒットの殆どが、モーツァルトのオペラなのですね。
あとは、若干、それに迫る勢いがあるのは、ロッシーニくらい。でもモーツァルトの人気を超えるには至りません。宮廷楽長のヴァイグルなどの新作オペラのプリミエだって、1000フローリン売れればいい方。ところが、モーツァルトのオペラ、特に一番人気の「魔笛」などは、毎公演、実に2000フローリン前後の特大ヒットを飛ばすのですよ。
だから、モーツァルトのオペラ群、特にドイツ語で書かれたジングシュピールは、彼の生前の観客に理解してもらうためには、ちょっと先を行き過ぎていたということなのではないでしょうか。
死後30年近く経って、やっと聴衆・観客の耳と鑑識眼が彼の作品に付いてきたのです。
今秋のドイツ音楽学会では、モーツァルトのオペラ作品群に関するシンポジウムがあり、彼の作品が、ウィーンを超え、全ヨーロッパ的にヒットしたということを、ハンブルグ劇場の資料を駆使して発表した専門家がいました。さもありまん、です。
「フィガロの結婚」は、ドイツ語で上演されることも多かったようですが、様式的にはジングシュピールではなく、オペラ・ブッファ。
それにしても、ボーマルシェの市民革命思想と貴族階級への皮肉に満ちたこの戯曲が、モーツァルト作曲のオペラだから、ということで、皇帝に受け入れられてしまうところが何とも。
当時、問題のある歌詞に音楽が付くと、リートなどの場合には、「大衆煽動の原因になる」と厳しく取り締まられることが多かったのに、オペラの場合、「民衆の害のない憂さ晴らし」と大目に見られることが多かったようです。
それでも、目くじら立てず、「退屈で欠伸をする」というところが、お人よしのヨーゼフ皇帝らしくていいではありませんか。
(ひょっとしてモーツァルトは、題材が過激で問題のあるものであることが分かっていたから、敢えて、美しい旋律をのんびりと展開し、上演禁止にならないよう手を打ったのか……? もしそうだとしたら、天才的過ぎる……!)
いずれにしても、「魔笛」とフリーメーソン、「後宮からの誘拐」の太守セリムや、「ティト王」の慈悲……当時の音楽を聴いていると、何かと権力者の思惑や検閲に縛られ、現代作曲家のように、自由に書きたいことが書けず、甘美な音楽でくるんで上手にやんわりと表現せざるを得なかった当時の作曲家たちの悲哀を思わずにいられません。
(そうした社会批評を、台本上は検閲で削られても、即興のパントマイムやアドリブ等で表現してしまうようになるのは、ネストロイの時代。モーツァルトの時代の旅回り劇団の風刺は、そこまで芸術的に洗練されていなかったようです。だからこそ、良くも悪くも、モーツァルトは母国ドイツ語音楽劇振興の旗振り役になりえた……?)
彼の「医者と薬剤師」は当時「フィガロ」より人気があるといわれましたが、最近はめったに上演されないようで。
そんなことがあったのですね・・・
どうも、ピアノ科は鍵盤に向かう時間が多くって、
知識に欠けてしまっていると、
この年になって気がつきました。
(人生折り返し地点を過ぎております・・・)
私的には弾くならクレメンティよりモーツアルトが好きですが。
先生の世界史レッスン、とても楽しいですね。
まだ、過去記事を全部読むことが出来ていませんが、
時間を見つけて、読ませていただきます。
師匠が走る師走になりました。
お体に気をつけて、
ますますのご活躍を。
中野先生と皆さんのお話を興味深く読みました。
「クレメンティの演奏で優っているのはテクニックだけです。」とありましたが、もともとこの会話はドイツ語ではなんと書かれているのでしょうか?あるいは英語にはどのように翻訳されているのでしょうか?自伝を買いにくいのでお尋ねします。
Ericaさんの1817~1821年のケルンテン門脇宮廷オペラ劇場がチケットの売り上げを当時の財務省に報告した文書の調査の成果は発表されたのでしょうか?もし発表されていればどこで拝見できるかお知らせ頂きたくお願いします。
いずれもお手透きの時で結構ですのでご教授頂ければ幸いです。
ディッタースドルフの自伝ですが、わたしも原書は自分では手に入れられなかったので、国立音大に勤めている友人に頼んで図書館を使わせてもらい、そこにあった古書(ドイツでもすでに絶版でしょう)をコピーではなく直接翻訳したのです。というわけで、いま手元に原文はなく、申し訳ありませんがお教えできない次第です(ひょっとして国立国会図書館にはあるかもしれませんよ)。
Erikaさんへのご質問ですが、彼女からここへお返事があるといいですね!ブログのみのおつきあいで、お顔も本名も知らず、わたしからは連絡できませんので・・・
それにしてもビジネスマンの方で、ここまで詳しく研究されているとは!モーツァルト・ファンとバッハ・ファンは本格派が多いのですね。
また是非ご来訪ください。
ご丁寧にお返事ありがとうございました。
Dittersdorfの自伝は未だ見つかりません。古本屋に注文して探して貰うか、国立音大の友人に頼んで一緒に見に行って貰うかしようかと思っていましたが、ふとドイツのアマゾンには?と思いつき、見てましたらありました。
いえ、本はありませんでしたが、ClementiとMozartの競演についての感想の部分が本の紹介として出ていました。KunstとGeschmackでした。
«In Clementi's Spiel herrscht blos Kunst, in Mozart's aber Kunst und Geschmack.»
http://www.amazon.de/Karl-Dittersdorfs-Lebensbeschreibung-Ditters-Dittersdorf/dp/3784427308/ref=sr_1_1/303-9191474-6980206?ie=UTF8&s=books&qid=1179651340&sr=1-1
ClementiやMozartの生きた18世紀の事も知りたいと思っています。忙しかったので映画のマリー・アントワネットは見損なってしまいましたが、そのうちDVDが出たら買うことにして、先生の本を拝読させて頂くことにします。
Erikaさん:お待ちしています。お手透きの時にお願い致します。
アントワネット、ぜひお読みください!ツヴァイクの凄さを感じていただけると思います♪