5年前初めて鳴門の大塚美術館へ行ったとき、近くに「ドイツ館」なるものがあるのを知り、寄ってみて驚いた。こんな事実があったのか!(そういえば、ちらっと聞いた記憶があったけれど・・・)
--第一次世界大戦で日本は後出しジャンケンのごとく勝ち馬に乗り、中国の青島を攻めて、そこにいたドイツ人約5000人を捕虜にした。彼らは日本各地の収容所に入れられるが、そのうち1028名が鳴門の坂東俘虜収容所に送り込まれる。
今に至るまで語り継がれ、「ドイツ館」で当時の様子が展示されているそのわけは、この収容所が一種の奇跡であったからだ。会津出身の松江豊寿所長の指導のもと、捕虜たちはよそでは考えられないほどの自由を与えられ、西洋の進んだ文明を地元へもたらした。
彼らは収容所内に製パン所を作り、写真入り新聞「ディ・バラッケ」を発行し、地元民にスポーツ(まだ珍しかったサッカーやホッケーなど)や楽器を教え、ソーセージやブランデーの製法を伝え、石橋を建造し、さまざまな手作り品を展示即売し、コンサートを開いてベートーヴェンの第九を日本初演した。「ドイツさん」と呼ばれて親しまれた。
捕虜を甘やかしているとして陸軍省から再三呼び出しを受けたにもかかわらず、松江所長は自分のやり方を断じて変えなかった。会津っぽの面目躍如だし、彼がいかに当時としては珍しい、世界を見据えた教養人だったかがわかる。
所長がこうした大人物であったことに加え、日本人とドイツ人の共通項(規律を守り、礼儀正しく、清潔好き)も幸いしたのだろう。さらに言えば、この捕虜たちはプロの兵士より義勇兵が多く、インテリで専門職だった。3年という不自由な収容所生活にありながら、自分たちの専門を生かせたのはそのおかげでもある。
というようなことを「ドイツ館」で勉強して大いに面白かった。
で、先週また大塚美術館へ行くと、今度は「ドイツ館」のそばに「バルトの楽園」のオープンセットが観光地になっていたのでさっそく見に行く。
実際の収容所は6万平方メートルあったらしいが、セットは2万平方メートル。それでもかなり精巧に作られていて、なかなか楽しい。捕虜生活の様子がいろいろ想像できた。
ここまできたなら、どうしても映画を見ないわけにはゆかないでしょう。昨日見てきました。感想は・・・むむむ。惜しいなあ。こんなに面白い素材なのにどうしてこんなことになるのかなあ。
そもそもタイトルがひどい。「バルト」って、バルト海には何も関係ないはずなのにと思っていたら、ドイツ語のBart(バールト=髭)だという。日本人はみんなドイツ語できました? しかも「楽園」は「らくえん」ではなく「がくえん」と読むのだという(誰も読めんぞ!)
まるで教科書のように味気ない映画なのでした。ずらずら列記してあるだけで、映画的感興が少しもない。松江の人物像も、これではただの「いい人」。凄みがない(「生きて虜囚の辱めを受けず」の時代に我を通した人間なんだから、ちらとでも迫力を見せなければ・・・)。
もっと脚本を練り、演出をていねいにすれば、佳作になったかもしれないのに、残念なことでした。
結論。「大脱走」は傑作である。
☆新著「怖い絵」(朝日出版社)
☆☆アマゾンの読者評で、この本のグリューネヴァルトの章を読んで「泣いてしまいました」というのがありました。著者としては嬉しいことです♪
①ドガ「エトワール、または舞台の踊り子」
②ティントレット「受胎告知」
③ムンク「思春期」
④クノップフ「見捨てられた街」
⑤ブロンツィーノ「愛の寓意」
⑥ブリューゲル「絞首台の上のかささぎ」
⑦ルドン「キュクロプス」
⑧ボッティチェリ「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」
⑨ゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」
⑩アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディト」
⑪ホルバイン「ヘンリー8世像」
⑫ベーコン「ベラスケス<教皇インノケンティウス10世像>による習作」
⑬ホガース「グラハム家の子どもたち」
⑭ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」
⑮グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」
⑯ジョルジョーネ「老婆の肖像」
⑰レーピン「イワン雷帝とその息子」
⑱コレッジョ「ガニュメデスの誘拐」
⑲ジェリコー「メデュース号の筏」
⑳ラ・トゥール「いかさま師」
♪♪「メンデルスゾーンとアンデルセン」の書評はここ⇒http://www.meiji.ac.jp/koho/meidaikouhou/20060501/0605_10_booknakano.html
--第一次世界大戦で日本は後出しジャンケンのごとく勝ち馬に乗り、中国の青島を攻めて、そこにいたドイツ人約5000人を捕虜にした。彼らは日本各地の収容所に入れられるが、そのうち1028名が鳴門の坂東俘虜収容所に送り込まれる。
今に至るまで語り継がれ、「ドイツ館」で当時の様子が展示されているそのわけは、この収容所が一種の奇跡であったからだ。会津出身の松江豊寿所長の指導のもと、捕虜たちはよそでは考えられないほどの自由を与えられ、西洋の進んだ文明を地元へもたらした。
彼らは収容所内に製パン所を作り、写真入り新聞「ディ・バラッケ」を発行し、地元民にスポーツ(まだ珍しかったサッカーやホッケーなど)や楽器を教え、ソーセージやブランデーの製法を伝え、石橋を建造し、さまざまな手作り品を展示即売し、コンサートを開いてベートーヴェンの第九を日本初演した。「ドイツさん」と呼ばれて親しまれた。
捕虜を甘やかしているとして陸軍省から再三呼び出しを受けたにもかかわらず、松江所長は自分のやり方を断じて変えなかった。会津っぽの面目躍如だし、彼がいかに当時としては珍しい、世界を見据えた教養人だったかがわかる。
所長がこうした大人物であったことに加え、日本人とドイツ人の共通項(規律を守り、礼儀正しく、清潔好き)も幸いしたのだろう。さらに言えば、この捕虜たちはプロの兵士より義勇兵が多く、インテリで専門職だった。3年という不自由な収容所生活にありながら、自分たちの専門を生かせたのはそのおかげでもある。
というようなことを「ドイツ館」で勉強して大いに面白かった。
で、先週また大塚美術館へ行くと、今度は「ドイツ館」のそばに「バルトの楽園」のオープンセットが観光地になっていたのでさっそく見に行く。
実際の収容所は6万平方メートルあったらしいが、セットは2万平方メートル。それでもかなり精巧に作られていて、なかなか楽しい。捕虜生活の様子がいろいろ想像できた。
ここまできたなら、どうしても映画を見ないわけにはゆかないでしょう。昨日見てきました。感想は・・・むむむ。惜しいなあ。こんなに面白い素材なのにどうしてこんなことになるのかなあ。
そもそもタイトルがひどい。「バルト」って、バルト海には何も関係ないはずなのにと思っていたら、ドイツ語のBart(バールト=髭)だという。日本人はみんなドイツ語できました? しかも「楽園」は「らくえん」ではなく「がくえん」と読むのだという(誰も読めんぞ!)
まるで教科書のように味気ない映画なのでした。ずらずら列記してあるだけで、映画的感興が少しもない。松江の人物像も、これではただの「いい人」。凄みがない(「生きて虜囚の辱めを受けず」の時代に我を通した人間なんだから、ちらとでも迫力を見せなければ・・・)。
もっと脚本を練り、演出をていねいにすれば、佳作になったかもしれないのに、残念なことでした。
結論。「大脱走」は傑作である。
☆新著「怖い絵」(朝日出版社)
☆☆アマゾンの読者評で、この本のグリューネヴァルトの章を読んで「泣いてしまいました」というのがありました。著者としては嬉しいことです♪
①ドガ「エトワール、または舞台の踊り子」
②ティントレット「受胎告知」
③ムンク「思春期」
④クノップフ「見捨てられた街」
⑤ブロンツィーノ「愛の寓意」
⑥ブリューゲル「絞首台の上のかささぎ」
⑦ルドン「キュクロプス」
⑧ボッティチェリ「ナスタジオ・デリ・オネスティの物語」
⑨ゴヤ「我が子を喰らうサトゥルヌス」
⑩アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディト」
⑪ホルバイン「ヘンリー8世像」
⑫ベーコン「ベラスケス<教皇インノケンティウス10世像>による習作」
⑬ホガース「グラハム家の子どもたち」
⑭ダヴィッド「マリー・アントワネット最後の肖像」
⑮グリューネヴァルト「イーゼンハイムの祭壇画」
⑯ジョルジョーネ「老婆の肖像」
⑰レーピン「イワン雷帝とその息子」
⑱コレッジョ「ガニュメデスの誘拐」
⑲ジェリコー「メデュース号の筏」
⑳ラ・トゥール「いかさま師」
♪♪「メンデルスゾーンとアンデルセン」の書評はここ⇒http://www.meiji.ac.jp/koho/meidaikouhou/20060501/0605_10_booknakano.html











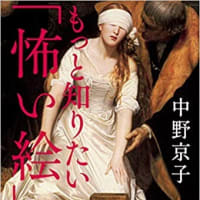







あの監督、まんざら戦争を知らない世代ではないのに、『きけ、わだつみの声』でしたか、あれも生ぬるかった……。だいたい兵隊さんたちが長髪なんだもの。それだけで迫力かいちゃう。
シベリアで捕虜になった日本人、ナボコフ劇場でしたっけ、仕事を与えられると、つい一生懸命やっちゃうのが、ドイツ人と日本人かな。
変な方に向いたときも傍から見れず、まっしぐら……なんて。
「髭のがくえん」だったのですね。
CMや予告じゃ、全然分かりませんでした。
収容所、以前アウシュビッツを訪れたことが
ありますが、戦争終結間際は本当に悲惨だった
ようです。でも、他の収容所(マイダネクや
ザクセンハウゼン等)に比べると衛生や
栄養面で良かったという話を聞き驚きました。
そうすると坂東の収容所は楽園のようだったで
しょうね。戦時中に他国の文化や知識を吸収
するという考えはなかなかの人で無い限り、
思い浮かびませんもんね。。
えーっ、長髪の兵隊?それはあんまりな映画ですね。「天国の門」はけっこう良かったのになあ・・・
ゆうひさん
このタイトルでわかる人はいないのではないでしょうか?わたしだって坂東へ行かなければ、気がつかなかったと思います。もっと素直なタイトルにすればいいのに、どういうセンスかなあ。
haruuraraさん
いろいろ歴史の勉強にはなるので、一見の価値はあると思います。そういえば、邦画にも字幕があるといいですよね。
ができました。
しかし、まるで今日の記事内容のごとく、最後の
1行ですべてが吹っ飛んでしまいました。
たしかに「大脱走」は素晴らしい映画です!!(笑)
TBの操作を誤りまして、不細工になりました。すみません。
「恐い絵」拝読しております。著者御本人様ですか?