
「知的財産とは何か?」について2種類の定義を示してセミナー受講者の皆様にどちらのイメージを持っているかをお訊ねしたところ、ほぼ半々に分かれる結果になったということを先日の記事に書きました。たいへん興味深い結果であったので、他のセミナーでも同じ質問をぶつけてみました。
技術者中心に参加されたあるセミナーでは、ほぼ半々の結果でした。
知財にあまり馴染みのない方が多かったあるセミナーでは、おおよそ7:3で第1説という結果になりました。
これだけ世間で知財、知財と言われているにも関わらず、「知的財産」の捉え方がこのように真っ二つに分かれているというのは、知財に関する議論をややこしいものにしている一因であるように思います。
例えば、「知財化」、「知的財産化」といった言葉が使われることがあります。
第2説であれば、「発明を特許権として権利化する行為」や「技術情報を営業秘密として管理する行為」が「知的財産化」ということになるのでしょうが、第1説で捉えている人からすると、「発明」も「技術情報」もそもそも「知的財産」なのだから、「それを『知的財産化』するってどういう意味なの?」ということになってしまいます。第1説で捉えていても、普通は「これは『権利化』のことを言っているのだな」と文脈から理解できるとは思いますが、この感覚の違いが実は意味を持ってくるのではないでしょうか?
発明やノウハウを生み出した人にとって、「これを『知的財産化』することが必要ですね」と言われるのと、「知的財産が生まれたので、『権利化』を進めましょう」と言われるのと、どちらのほうが自分の発明を尊重された印象を持ち、その後の手続に積極的に協力しようという気持ちになれるか。微妙な感情的な部分も考えると、個人的には「知的財産化する」より「知的財産を権利化する」のほうがベターであるように思います。
技術者中心に参加されたあるセミナーでは、ほぼ半々の結果でした。
知財にあまり馴染みのない方が多かったあるセミナーでは、おおよそ7:3で第1説という結果になりました。
これだけ世間で知財、知財と言われているにも関わらず、「知的財産」の捉え方がこのように真っ二つに分かれているというのは、知財に関する議論をややこしいものにしている一因であるように思います。
例えば、「知財化」、「知的財産化」といった言葉が使われることがあります。
第2説であれば、「発明を特許権として権利化する行為」や「技術情報を営業秘密として管理する行為」が「知的財産化」ということになるのでしょうが、第1説で捉えている人からすると、「発明」も「技術情報」もそもそも「知的財産」なのだから、「それを『知的財産化』するってどういう意味なの?」ということになってしまいます。第1説で捉えていても、普通は「これは『権利化』のことを言っているのだな」と文脈から理解できるとは思いますが、この感覚の違いが実は意味を持ってくるのではないでしょうか?
発明やノウハウを生み出した人にとって、「これを『知的財産化』することが必要ですね」と言われるのと、「知的財産が生まれたので、『権利化』を進めましょう」と言われるのと、どちらのほうが自分の発明を尊重された印象を持ち、その後の手続に積極的に協力しようという気持ちになれるか。微妙な感情的な部分も考えると、個人的には「知的財産化する」より「知的財産を権利化する」のほうがベターであるように思います。










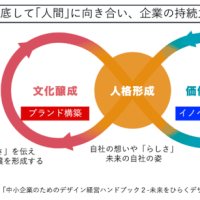
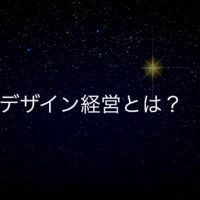



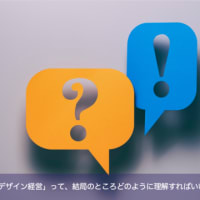
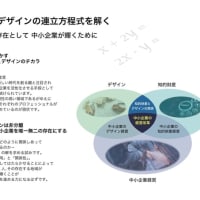


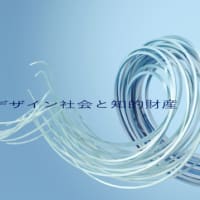
弁理士は、材木を見て、このあたりの枝は木炭に使えそうだと判断して、それを切り取り木炭に加工します。企業の知財部は木炭を火鉢に入れて、種火をつくり事業部門が暖をとりながら成長することを助けます。しかし、引きこもりのように家の中で暖をとっているだけでは事業は大きく成長を遂げることはできません。火鉢のそばで暖をとって温まりながら、汁粉を飲んで、ミカンを食べて外に出て、活発に仲間と遊ばねばなりません。
コメントありがとうございます。
いつもながら、久野様の喩え話には裏の裏まで話がつながっていて、その精緻さに驚かされます。